もうね、題名からして恐ろしい。

掛け衿の柄合わせで、上前と下前の両方にある場合、衿肩明きの位置を見極める事が難しい。
自分の仕立てによる衿肩回りの緩みを考え、合うように左右を調整するのだけど、ヘラの準備の時はちゃんと出来てても、いざ掛け衿を付けようと思ったらずれてた(切る前ね)・・なんて事は日常茶飯にあるので、揚げの縫いなおしはしょっちゅうする。
まぁ、見極めが悪いんだよ、って言われたらそうなんだけどね。
学生時代、初めて両方に柄合わせのある振袖を縫った時、間違えて仕立てた。
下前に画像のようなぼかしがうっすらあったのよね。
あの時は、裁ちの先輩から「肩明きの印はつけといたから」と言われ、なんの疑いもなく仕立てたらあら大変。裁った先輩、縫った私、担任と全く気がつかなくて、最後の最後で「肩明き、違ってんでぇ~」と叫ばれびっくり仰天。26年も前の事なのに、振袖の両方柄合わせのある分を見ると思いだされて嫌な気分になる。
結局、他の部分に似たような感じの柄位置があり、「とりあえず納めてみるけど返って来たら買い取りね」と言われだものの、返って来なかったから納まったんだろうね。
ここで改めて謝ります。
「26年前、大阪府界隈で、真っ青な振袖を買われたお方。
どうも、すいませんでした。 」
」
謝りたい人は、まだまだいっぱいいる・・・



掛け衿の柄合わせで、上前と下前の両方にある場合、衿肩明きの位置を見極める事が難しい。
自分の仕立てによる衿肩回りの緩みを考え、合うように左右を調整するのだけど、ヘラの準備の時はちゃんと出来てても、いざ掛け衿を付けようと思ったらずれてた(切る前ね)・・なんて事は日常茶飯にあるので、揚げの縫いなおしはしょっちゅうする。
まぁ、見極めが悪いんだよ、って言われたらそうなんだけどね。

学生時代、初めて両方に柄合わせのある振袖を縫った時、間違えて仕立てた。
下前に画像のようなぼかしがうっすらあったのよね。
あの時は、裁ちの先輩から「肩明きの印はつけといたから」と言われ、なんの疑いもなく仕立てたらあら大変。裁った先輩、縫った私、担任と全く気がつかなくて、最後の最後で「肩明き、違ってんでぇ~」と叫ばれびっくり仰天。26年も前の事なのに、振袖の両方柄合わせのある分を見ると思いだされて嫌な気分になる。
結局、他の部分に似たような感じの柄位置があり、「とりあえず納めてみるけど返って来たら買い取りね」と言われだものの、返って来なかったから納まったんだろうね。
ここで改めて謝ります。
「26年前、大阪府界隈で、真っ青な振袖を買われたお方。
どうも、すいませんでした。
 」
」謝りたい人は、まだまだいっぱいいる・・・















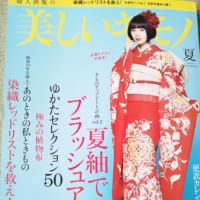


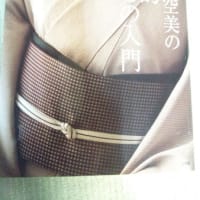
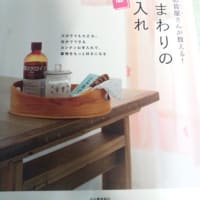

あるもんです、心の中の“モヤモヤ”は。。
振袖を頂いた時、掛衿柄合わせが上前だけだと小さくホッとする私。(両側にあってそれが
思い通りにピッタリついた時の達成感には負けるけど)
衿の柄 両方合ってるのは手間かかるって
案外着る人は知らない事かもね。
掛け衿以上に「やりがい」あるのは
「振り布!」です。(最近、ありますか~?)
以前、訪問着で「鳥の絵があんまり襟に近すぎる…」と、呉服屋さんに指摘されたことがありました。背紋の位置、スミ打ち、柄、それぞれバランスを取ったつもりでしたがギリギリになりました。私も『買い取り』にはならなかったからお客様に納品されたのでしょう。襟の柄合わせは冷や汗モノですね。
この「ほっ」は一体なんなんでしょう。(笑)
こればかりは、何年やっても気が抜けません。
振り布は、最近触ってませんねぇ。
私の所はフキのように出しますが、普通に縫うところもあるみたいで
驚いた事があります。染め屋さんの真意は・・・なんて。
袖巾を逆算して、まわしがけをする時、これまた悩みます。(笑)
だって、紋があったら肩明きは決まってるわけで、紋屋の責任。
柄位置は染め屋の責任で、それを縫い子のせいにされるのは
大分違うように思います。
幸いな事に私の所の呉服屋さんは、「紋屋が悪い」と言ってくれましたよ。
災難でした。