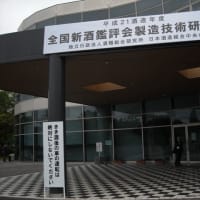日本酒の税法的名称は清酒である。酒イコール清酒であった。日本酒の代表的銘柄〇〇正宗の正宗はセイシュウと読めることから日本酒の銘柄として使われてきた。清酒は身近な言葉だったのだ。近年清酒という言葉は死語のごとく聞かれない。ここでは清酒と日本酒の両方の言葉を使わなければならないのは時代の流れだ。日本酒が一般名称といっても過言ではない。酒と言えば清酒を指していた時代は昭和40年(1965年)以前だった。清酒は昭和30年代半ばにビールに量的に抜かれるまでは日本の酒として君臨してきた。当時、宴会は生活の中に根づいていた。めでたい時、そうでないとき折り目節目で酒を飲む宴会した。そういうものを宴会文化とでもいうなら宴会文化は公務員の綱紀粛正コンプライアンスが求め始められきた昭和の終わりころから減少し、その流れが地方公務員に及んだ時息の根を断たれた。料亭は減少し地方で生き残っていた料亭も平成10年ころにはめっきり減った。公務員が大のお得意様だったのだろう。料亭の酒と言えばもちろん清酒(日本酒)だった。このころはまだ清酒の味は信頼されていた時代だったのかもしれない。
清酒は三増酒問題で品質を叩かれ昭和50年をピークに販売量を落とし続けている。いまやピークの30%でなお凋落のめどがたたない。量を追うものではないが量も大切な事項だ。量が無くなれば消費者の目に留まらなくなり存在すら意識されなくなる。量が減り続ける原因は何か。清酒だけが減り続けるのはなぜか。答えはひとつ不味い物が出回って消費者を失望させているからだ。
こういう仕事をしながら普段酒を飲まない人間だがスーパーのチラシを見ていてふと1000円以下の大吟醸って何かという疑問が起き購入してみた大手メーカーのもので880円(税別)だ。どうしてこんな値段で造れるのか売れるのか。答えはまずい、吟醸の品質コンセプト(個人の)にまったく合っていない。アルコール分は14°台、香りは吟醸香というよりアルコール臭が立ち味は米や麹の風味乏しくアルコール味でうすっぺらい。とても大吟醸どころか日本酒も名乗って欲しくないレベルだ。安いからコストをかけられないという生産者の言い訳をごもっともと理解してくれる物分かりのいい人はレアーだろう。いくら安くても消費者は大吟醸酒として買っているのである。大吟醸という名称の信頼性を揺らがせかねないと老婆心ながら思う。
品質名称と味で消費者を失望させないよう切に願う。
清酒は三増酒問題で品質を叩かれ昭和50年をピークに販売量を落とし続けている。いまやピークの30%でなお凋落のめどがたたない。量を追うものではないが量も大切な事項だ。量が無くなれば消費者の目に留まらなくなり存在すら意識されなくなる。量が減り続ける原因は何か。清酒だけが減り続けるのはなぜか。答えはひとつ不味い物が出回って消費者を失望させているからだ。
こういう仕事をしながら普段酒を飲まない人間だがスーパーのチラシを見ていてふと1000円以下の大吟醸って何かという疑問が起き購入してみた大手メーカーのもので880円(税別)だ。どうしてこんな値段で造れるのか売れるのか。答えはまずい、吟醸の品質コンセプト(個人の)にまったく合っていない。アルコール分は14°台、香りは吟醸香というよりアルコール臭が立ち味は米や麹の風味乏しくアルコール味でうすっぺらい。とても大吟醸どころか日本酒も名乗って欲しくないレベルだ。安いからコストをかけられないという生産者の言い訳をごもっともと理解してくれる物分かりのいい人はレアーだろう。いくら安くても消費者は大吟醸酒として買っているのである。大吟醸という名称の信頼性を揺らがせかねないと老婆心ながら思う。
品質名称と味で消費者を失望させないよう切に願う。