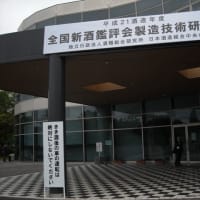日本酒(清酒)はどうやって現代に至ったのかあまり耳にしたことがない。ルーツはどぶろくであろうが今の清酒の形が出来上がったのは西暦年第1800年の灘、西宮の酒作りである。それ以前の酒は甘くて酸っぱいとろっとした酒であった。飽きやすい酒だった。灘・西宮の酒造りで酒の味が一挙に変化したのである。何杯でも飲めるの見飽きしない辛口になった。嗜好性が一挙に向上したのである。コペルニクス的とは言わないが味革命が起きた。酒造り技術の担い手は丹波の出稼ぎ杜氏であった。革新的な酒作りの技術は現代に引き継がれ、清酒の仕込み配合はその当時の基本を引き継いでいる。詳しくは日本醸造協会発行の酒造教本のとおりである。もっと詳しくは本ブログに記してある。
灘・西宮の酒造技術が全国に普及した過程は謎である。諸先輩や全国の酒屋さんの話の断片を拾い集めると江州商人と丹波の杜氏がタグ組んで一緒に全国で酒造りを始めたという。十一屋とか江州店の作り酒屋は多い。地方では依然として古い技術で野暮ったい酒(いなか酒)を造っていたので勝敗は明らかだった。瞬く間に灘・西宮の酒(本場の酒)が全国を席巻したのは当然の結果だった。
くだらん:上方から江戸に行くことを下ると言った。灘・西宮で造られた良い酒だけが江戸に下った(送られた)。くだらんとは江戸に送ることができない品質不良の酒をさす。
新技術が日本中に広まると酒造り集団が各地で誕生した。九州は築後杜氏、五島列島にも小さな杜氏集団が平成時代もあった。広島(安芸)杜氏、出雲杜氏、丹波杜氏、丹後杜氏、糠(福井)杜氏、能登杜氏、越後杜氏、志太(静岡)杜氏、信州杜氏、南部杜氏、山内(秋田)杜氏・・・令和になった今ほとんど残っていないと聞く。現代の技術の担い手は酒造会社、研究機関、大学になっている。日本醸造協会、もやしメーカーも根幹的な技をを保有している。
間もなく後期高齢者になるので下らない話でも残せば何かの役に立つかもしれないという気持ちです。文字で残さなければあったことも無かったと同じで記録するというのは大事です。
灘・西宮の酒造技術が全国に普及した過程は謎である。諸先輩や全国の酒屋さんの話の断片を拾い集めると江州商人と丹波の杜氏がタグ組んで一緒に全国で酒造りを始めたという。十一屋とか江州店の作り酒屋は多い。地方では依然として古い技術で野暮ったい酒(いなか酒)を造っていたので勝敗は明らかだった。瞬く間に灘・西宮の酒(本場の酒)が全国を席巻したのは当然の結果だった。
くだらん:上方から江戸に行くことを下ると言った。灘・西宮で造られた良い酒だけが江戸に下った(送られた)。くだらんとは江戸に送ることができない品質不良の酒をさす。
新技術が日本中に広まると酒造り集団が各地で誕生した。九州は築後杜氏、五島列島にも小さな杜氏集団が平成時代もあった。広島(安芸)杜氏、出雲杜氏、丹波杜氏、丹後杜氏、糠(福井)杜氏、能登杜氏、越後杜氏、志太(静岡)杜氏、信州杜氏、南部杜氏、山内(秋田)杜氏・・・令和になった今ほとんど残っていないと聞く。現代の技術の担い手は酒造会社、研究機関、大学になっている。日本醸造協会、もやしメーカーも根幹的な技をを保有している。
間もなく後期高齢者になるので下らない話でも残せば何かの役に立つかもしれないという気持ちです。文字で残さなければあったことも無かったと同じで記録するというのは大事です。