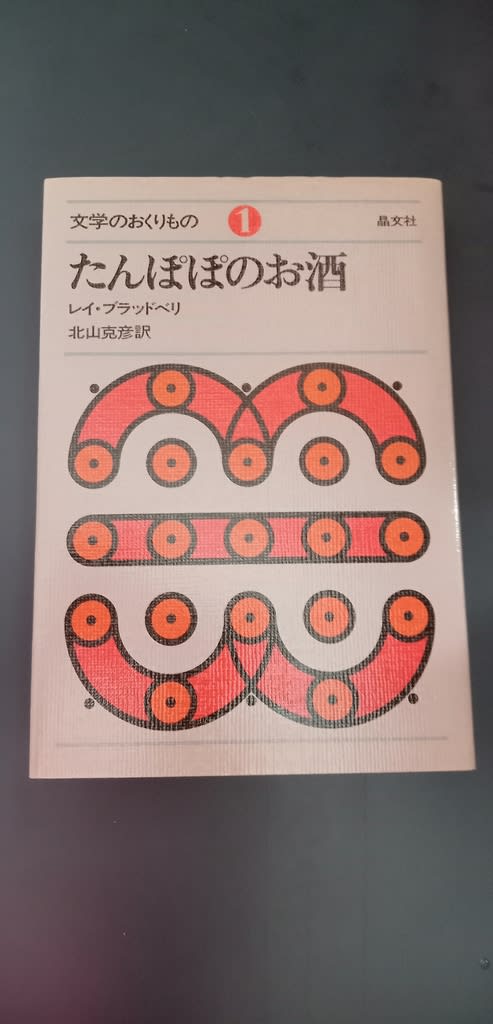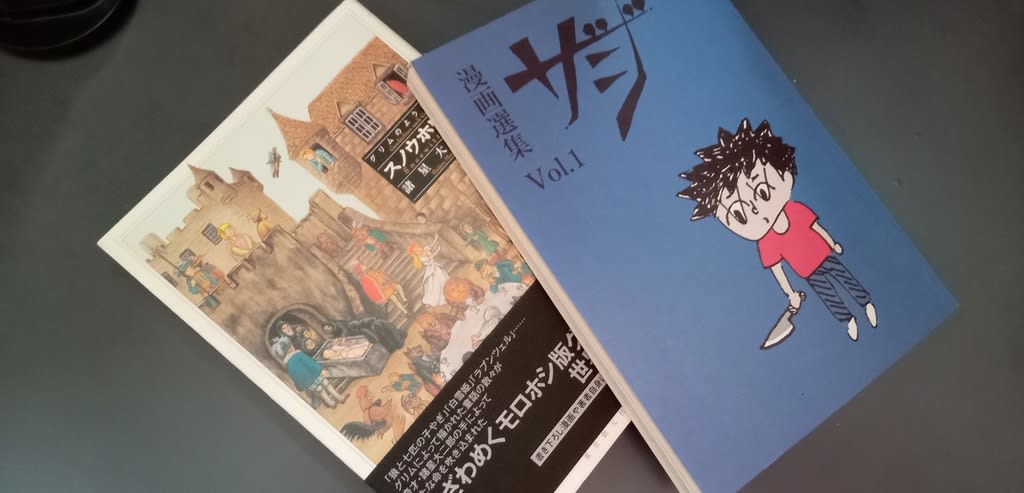20250215
2025.1.17より全国公開されている映画「敵」。
(監督・脚本:吉田大八、主演:長塚京三)
公開直後、観た人からの伝で、凄い作品だとのことで観に行きました。
しかし、胸中判然としないところもあり、先日、二回目を観てきたのです。
初回観た後に書店店頭には置いてなかった原作も、二回目の後には大々的に平積みされており入手。
小説「敵」は筒井康隆、断筆から復帰直後の1998年の作品です。今回、小説も読了したので、私なりの感想を残しておこうかな、と思いました。
小説「敵」と映画「敵」について
※以下ネタバレがありますので、これから映画を観る方、小説を読む方はくれぐれもご注意ください。
小説と映画ではラストが大きく違う。
ラストに至るまでの日常は、映画でも原作のテイストに実に忠実に描かれている。妄想とも夢とも見分けのつかぬ事象が頻発するようになる過程、死んだ妻、嫌な奴、敵等々。これらについて原作を正方向に鋭く膨らませている。
何が違う、といえば原作で主人公:渡辺儀助は死んでおらず、高潔な死に憧れつつ、ラストでは大きく心揺れる。非常に余韻を持たせる終わり方になっている。
一方、映画のラストは、儀助の自死(と思われる)後に残された家に親類が集う場面が付け足されている。従弟の子:渡辺槙男が物置で見つけた双眼鏡を覗くと・・・二階には階下を見おろす儀助の姿が!
ここで終わっている。
監督の吉田大八は、映画化に際し、筒井から一つだけ、注文というか、注意を受けたという。「儀助は認知症ではなく、あくまでも夢と妄想の人なのだ」と。
これを、無秩序に崩れていくのではなく、あくまでも自分の理性でギリギリまで記憶と老いに向き合うスタンスのことだと吉田は理解した。
筒井は「敵」の完成作品を観てすぐ「傑作です」というコメントを寄せたという。シナリオ確認の段階から吉田に期待するところ大であったのだろうが、大家に臆せずラストに異なった解釈を配置したことに対し、「自身の描き切れなかった部分を表出させてくれた」ことに向けた快哉だったのかもしれない。
小説の中では儀助は自死を決行するのは金の無くなった時期でであると決めている。その日は予想ができるので、家中の消耗品もこれに合わせ使い切れるように買い置きはしない。
ところが、予想を揺るがすような「敵」の出現。
「敵」とはつまり平たく言えば「耄碌(もうろく)」であろう。
金の無くなるより前に、自死の日程さえ分からなくなってしまう恐怖。
一気に認知症にでもなってしまえば、このような逡巡もなかろうに。
負けを潔く認め、自死の時期を早めるのか?
また会いたい人達もいる。もう少し生きたい・・・ここで終わる。
筒井が儀助の自死を匂わせる場面さえ描かなかったのは自死の賛美と受け取られかねないことへの恐れもあろうが、そこまで描くとやはり身も蓋もないのは明白であるからだろう。
そうはいっても、作者の「高潔な死」への憧れは作中から確かに伝わってくる。
一方、吉田の答えは映画の構成およびラストからエンドロールに見え隠れする。
先ず、作中四つの章立てをし、それぞれ「夏」「秋」「冬」「春」と名付けた。夏の章では日々静かに、しかし、着実に死へのカウントダウンをしていく元・大学教授の儀助を描く。そこにはストイックな死への快感さえ感じる。
しかし、儀助の決意も秋~冬にかけて様々な夢・妄想に浸食されていく。(小説では主要な登場人物の一人であった、バー・夜間飛行の菅井歩美などは映画では実在したかどうかもあやふやだ)楽しい夢、恐ろしい夢、そして妄想・・・日常との間(あわい)が急速に消えてゆく。
映画では儀助に「春」はやってこなかった。
これが吉田の一歩踏み込んだ「決断」。
代理人(?)による遺産分与の場面で家屋敷の相続人に指定された槙男が、ふと手にした双眼鏡で二階を覗くと、そこに儀助の姿。
ここは、映画初見の際、「春」の章自体が儀助の妄想なのではないか、とも考えた。(最後の場面は槙男が取り落とした双眼鏡のアップで終わる。そもそも、槙男なんていないのでは?)小説も映画も最後は曖昧なのか?
冬の章の最後、縁側にへたり込んだ儀助が呟く重要なセリフ。
「この雨があがれば春になる。春になればきっと皆にまた会える。」
「みんな どうしてるかな。早く逢いたいなあ。」
ここは、小説では、湯島、鷹司、菅井の名前を挙げて「逢いたい」と、言っている。しかし、映画ではこれらの名前が省かれているのだ。(なぜか椛島の名前は無いが・・・)
「あちら側」にいる妻や懐かしい人々に「早く逢いたい」と思わせるように仕向けられたのではないだろうか。
実際、私もそう思った。
小説では存命の湯島も、映画では既に「あちら側」にいるようであるし。
そして、私はあることによって、「春」の章が儀助の妄想や夢ではなく現実を表した場面だということに思い至る。
それは・・・
エンドロールの最後にひっそりと織り込まれていた。
ほんとうに小さな音なので、初回観たときには気付かなかった。
コーヒーミルで豆を挽く音・・・
そっとドアを閉める音・・・
廊下を静かに遠ざかっていく足音・・・
大切にしていた習慣・手回しミルで丁寧に挽いた豆で淹れたコーヒーを飲み、(冬の章ではカップ麺や菓子パンの生活に堕落してしまう!)数少ない友人たちには心中「ありがとう」を述べ、静かに去って行く。
実際行く先は二階寝室。何度も自死の予行演習をしたベッド脇・・・
これを暗示しているのではないか!?
私は、これを吉田監督からのメッセージと受け止めた。
吉田監督よ有難う。
「人生の最後くらい、じぶんでカッコよく決めさせてくれ」と。
それが「私の心意気」だ、と。
あからさまではなく、そっと置かれたメッセージにこそ人は心動かされるのだ。
敵の襲来に抗いきれなくなった儀助に残された最後の自尊の光。
「願わくは花の下にて春死なん・・・」を実行させてあげたのか。
まあ、以上が、私が鷹司靖子(瀧内公美)の原節子の再来としか思えない美しさに惹かれて二度見した結果、抱いた「感想」ということで・・・
菅井歩美役の河合優実も本当に芸達者で、主役の長塚京三を見事に手玉に取っていました。(昨年は八犬伝にも出てましたし、最近は本当ににエグイ役もこなしているようです)
評判も上々のようで、初回は平日にもかかわらず満席。(水曜日で割引き、というのもあるが、筒井ファンもしくは長塚ファンと思しき人生の先輩方で一杯でした)二回目も普通の割引なしの全くの平日にもかかわらず、七分の入りでした。
若い人の姿も多かった。