1983年2月に京都・奈良へ卒業旅行に行きましたが、この旅行での会長らしい面白エピソードが、「渋土器会」の名称の由来になっています。みなさん、覚えていますか?
「渋」は、渋谷の意味もあるのですが、京都の嵯峨野にある向井去来(松尾芭蕉の弟子)の草庵「落柿舎」で会長が詠んだ俳句の一節からとってあります。
男立ち 梅をもとめて 渋きかな
男9人の旅行だったので、本来は、「男たち」のはずなんですが、「男立ち(だち)」と濁ったのは、旅行前にAクンとBクンが吉原でソープしてきたからだと、会長が言っていたような……。いかにも会長らしいですね。
何が「渋い」のかわかりませんが、「渋きかな」のフレーズが可笑しくて、名称をつける時に拝借したわけです。
土器については、奈良か京都か忘れてしまいましたが、古刹の裏庭にころがっていた土塀のかけらを会長が拾って、真顔で
「これは、縄文土器の破片かもしれない」と言い張ったことからつけられたわけです。
超個性的な会長の思わぬ発想や行動は、みなを大いに楽しませてくれたはずです。振り回されることも多々ありましたが、永久に渋土器会の会長でいてほしかったです。<大>
「渋」は、渋谷の意味もあるのですが、京都の嵯峨野にある向井去来(松尾芭蕉の弟子)の草庵「落柿舎」で会長が詠んだ俳句の一節からとってあります。
男立ち 梅をもとめて 渋きかな
男9人の旅行だったので、本来は、「男たち」のはずなんですが、「男立ち(だち)」と濁ったのは、旅行前にAクンとBクンが吉原でソープしてきたからだと、会長が言っていたような……。いかにも会長らしいですね。
何が「渋い」のかわかりませんが、「渋きかな」のフレーズが可笑しくて、名称をつける時に拝借したわけです。
土器については、奈良か京都か忘れてしまいましたが、古刹の裏庭にころがっていた土塀のかけらを会長が拾って、真顔で
「これは、縄文土器の破片かもしれない」と言い張ったことからつけられたわけです。
超個性的な会長の思わぬ発想や行動は、みなを大いに楽しませてくれたはずです。振り回されることも多々ありましたが、永久に渋土器会の会長でいてほしかったです。<大>



















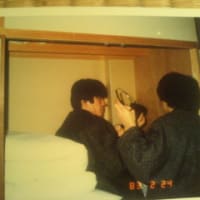
子供と二人で参拝し、八幡宮にも行きました。交通安全のお守り購入と御朱印帳記帳をしました。昔の菓子屋があった箇所のあたりには何もなかったですが、40年近く前のことを思い出していました。ついでに大学ものぞいてきましたが、入学試験当日にあたり、建物内部に入ることができず、学食を覗きたかった希望は果たせませんでした。
その後、渋谷駅を過ぎてセンター街を行ったのですが、渋谷駅の上には巨大なビルがたち、ヒカリエを圧倒する大きさでした。昔の東横線や学バス、東横のれん街などは全くなく、まさしく大都会でした。ただし、埼玉から出てきた田舎者のふさわしい居場所に感じられず、急いで立ち去り、昼食もセンター街奥の「渋谷餃子」という店で摂りました。結構いい味でした。
また、みんなで集まり、飲み会をしたいな・・・と思います。会長や大もいなくなり、集まることもなくなったけど、当時は大したことでもないことに時間をかけ、贅沢な季節だったと感じます。こんなことを感じるのは、年を重ねた証拠。
では、またね。
大も亡くなってから6年近くなる。今更ながら、年もとるわけだ。今年は7回忌に当たるのかな。多磨霊園にお墓があるのは覚えているが、具体的な場所はおぼろげであり、一人で行ってもきっと迷うでしょう。大のお墓まいりするために皆で集まるのはどうかなと思います。
これを見たら、連絡ください。