
http://blog.livedoor.jp/aryasarasvati/archives/42071109.html より転載、させていただいた記事です
新たに仕掛けられる情報戦
アイリス・チャンの“業績”を踏襲せよ! 「ホロコースト」と結びつけ反日攻勢
「南京大虐殺はアジアのホロコースト(ナチス・ドイツによるユダヤ人大量虐殺)だ」
壇上の発言者が声のトーンを上げると、多くの参加者がうなずいた。米カリフォルニア州サンフランシスコ近郊のミルピタス市にあるホテルの会議室。先月14~16日、中国系の反日団体「世界抗日戦争史実維護連合会(抗日連合会)」の2年に1度の研究会が開かれた。参加したのは北米やアジア、欧州の代表や中国の歴史学者ら約60人。
抗日連合会の幹部はこれまでも、南京事件とホロコーストを結びつける発言を繰り返してきた。ホロコーストを学ぶ機会の多い欧米を舞台に反日活動を展開するうえで、最も理解を得やすい手法だからだ。
壇上の発言者は続けた。
「われわれの力はまだまだ弱い。もっと力を注がなければならない」
参加者の一人は本紙の取材に「抗日連合会は今後『ハード』と『ソフト』の両面で国際社会に訴えていくのだと感じた」と話した。
ハード面とは博物館などのハコモノの設置だ。サンフランシスコでは、女性実業家、フローレンス・ファン(中国名・方李邦琴)を中心に抗日連合会も関与する形で、中国以外で初めて抗日戦を顕彰する「海外抗日記念館」を来年8月に開館する計画が進んでいる。
カナダ・トロントからの参加者も同様の記念館を設置したいと表明したといい各国に広がる恐れもある。
ソフト面では「南京大虐殺」や「戦時中における日本軍の蛮行」を宣伝する教材やビデオなどの発行、普及が計画されている。
登壇者は、中国政府が6月、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の記憶遺産に「南京大虐殺」と「慰安婦」を登録申請したことに触れ「登録が認められれば、(各国の)歴史教科書にも盛り込みやすい」と、抗日連合会としても働きかけを強める考えを示した。
1994年に発足した抗日連合会は設立20年の節目を迎えた。この間、米国や諸外国で反日宣伝活動を行ってきた。中国系米国人ジャーナリスト、アイリス・チャン(故人)の著書『ザ・レイプ・オブ・南京』(97年)の宣伝、販売はその「成功例」といえる。
「日本軍は南京で30万人の市民を虐殺し、2万-8万人の婦女子を乱暴した」などと書かれた“歴史”は事実誤認や無関係の写真掲載が出版当初から問題となったにもかかわらず、米メディアが称賛し、「日本軍の残虐さ」を植え付けるのに一役買った。
「アイリス・チャンがやったことを、われわれは踏襲しなければならない」
登壇者は参加者に向かってそう訴えた。会場にはチャンの両親の姿もあったという。(敬称略)
アイリス・チャンの“業績”を踏襲せよ!
「ホロコースト」と結びつけ反日攻勢
「40万人虐殺」米の教科書に堂々と載る屈辱 誤りは断てるか

米カリフォルニア州サンフランシスコ近郊のロスアルトス市の小高い丘の上にある広大な墓地。緑の芝生の間に整然と敷き詰められた墓碑の中に、アイリス・チャンの墓はあった。
「最愛の妻で母、作家、歴史家、人権活動家」。墓碑にはそう刻まれている。
同州サンタクララの自宅近くの路上に止めた乗用車の中で、拳銃自殺してから10年。命日の先月9日には親類や知人らが墓前に集まり、追悼した。
その様子を報じた中国メディア「人民網」によると「世界抗日戦争史実維護連合会(抗日連合会)」創設メンバーのイグナシアス・ディンもその場を訪れ、チャンと著書『ザ・レイプ・オブ・南京』についての思い出を語った。
「アイリスは小さい頃から祖母や父母から南京大虐殺について聞かされ、ずっと興味を持っていた。彼女は米国で何冊もの本を読んだが、英文の本の中には1冊たりとも日本軍の南京での暴行に関し報告はなかった。教科書にもなかった」
(それはつまり南京大虐殺はなかったってことでは・・・:筆者)
だから、チャンは「歴史を紹介する機会を作ろうとしたのだ」と。
日本の学者や歴史家らが再三、『ザ・レイプ・オブ・南京』の記述や写真の「誤り」や「偽り」を指摘したにもかかわらず、抗日連合会は宣伝、販売を強化し、米メディアを効果的に利用した。主要メディアが大々的に紹介することで、ベストセラーになり、全米各地の大学や図書館にも置かれるようになった。その結果「南京大虐殺」は米国の教育現場にも“史実”として顔を出している。
米大手教育出版社「マグロウヒル」(本社・ニューヨーク)が出している高校世界史の教科書「トラディションズ・アンド・エンカウンターズ(伝統と交流)」。この教科書には、旧日本軍が戦時中、慰安婦を強制連行したとする記述があり、日本の外務省が「不適切な記述」として、先月、記述内容の是正を要求したばかりだ。南京事件に関する記述も載っており、その項目はチャンの著作と同じ「ザ・レイプ・オブ・南京」と書かれている。
《日本軍は2カ月にわたって、7千人の女性を強姦(ごうかん)し、数十万人の非武装兵士と民間人を殺害、南京の住宅の3分の1を焼いた。日本兵の銃剣で40万人の中国人が命を失った》
南京住民は、「戦争への情熱と人種的優越感に駆り立てられた日本軍」の被害にあったとされ、その象徴が「ザ・レイプ・オブ・南京」だと主張されている。
南京事件から77年が経過した今月13日、南京市の「南京大虐殺記念館」での追悼式典で国家主席、習近平は「30万人の同胞が痛ましく殺戮(さつりく)された」と述べたが、その数字を上回る記述が米国の高校の世界史の教科書にあることは深刻だ。
慰安婦の項目にはこんな記述もある。
《慰安所設置のきっかけは、南京大虐殺からきた。多くの中国人女性が強姦された》
ロサンゼルスで中韓の反日行動を阻止しようと活動している日本人男性は「外務省は出版社に慰安婦の記述について抗議したというが、『南京』の件も一緒に是正要求したのだろうか。慰安婦についてだけだと、南京の記述は認めたことになってしまうのではないか」と危機感を募らせる。
サンフランシスコのチャイナタウンにある「文化センター」で今月13日、抗日連合会などが主催して南京事件の犠牲者を追悼する恒例の「南京祭」が開かれた。会場には「日本軍が占領した南京」や「虐殺」の写真が展示され、赴任して間もない駐サンフランシスコ中国総領事の羅林泉やサンフランシスコ市議、カリフォルニア州議会議員ら約400人が訪れた。
「アイリス・チャンの本で巻き起こした『南京大虐殺』キャンペーンを、戦後70年を機に、もう一度やろうとしているようだった」
会場を訪れた男性はそう語った。(敬称略)
産経ニュース2014.12.26
http://www.sankei.com/politics/news/141226/plt1412260012-n1.html
「アイリス・チャンの本で巻き起こした『南京大虐殺』キャンペーンを戦後70年を機に、もう一度やろうとしているようだった」
今まさに仕掛けられている最中じゃないの?だってメンバーが同じだもの

左:『ザ・レイプ・オブ・南京』アイリス・チャン氏
右:サイモン・ウィーゼンタール・センター エイブラハム・クーパー副所長
中央:徳留絹枝氏
→視界に入るノイズ:サイモン・ウィーゼンタール・センター(SWC)

http://www.foxnews.com/opinion/2014/12/29/unbroken-let-japanese-audience-see-jolie-film-learn-truth-about-pow-treatment/
日本人はアンジェリーナ・ジョリーの映画を見てどう捕虜を扱ったか知りなさい
byエイブラハム・クーパー&徳留絹枝だそうでございます
では皆様 日本兵鬼畜の所業「バターン死の行軍」で捕虜をどう扱ったかご覧ください
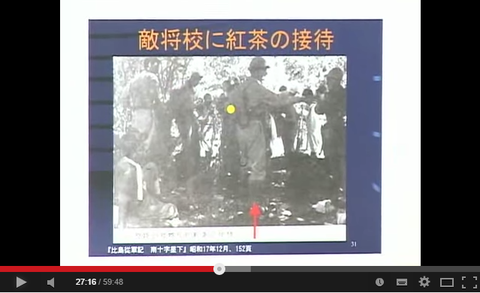
あろうことか紅茶をふるまっております!

捕虜を並ばせて診療させる・・・虐待前には健康チェックが欠かせません!
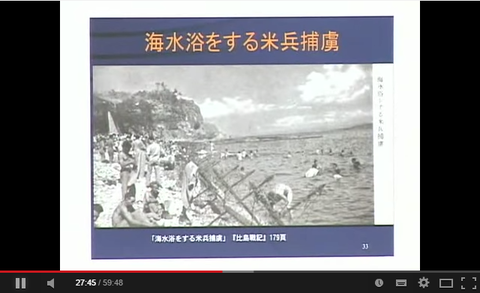
疲労困憊した捕虜に海水浴を強要!!
【youtube】GHQ焚書図書開封 第77回
(´・ω・`)恐ろしいですねぇ~~~~(棒)
憶測なんですけどね
ナチスの残党ってもうほとんどいないじゃないですか(年齢的にいって
だから新たなビジネスが必要なのかなぁ・・・と思うんでございます
以下、
産経の「アンブロークン」書評が何か変だと思ったら
http://blog.livedoor.jp/aryasarasvati/archives/42320276.html より
【早読み/先読み アメリカ新刊】
日本軍の捕虜となり、虐待に耐え抜き帰還した「アメリカン・ヒーロー」
Unbroken:A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption
不屈さ:生存と忍耐力そして贖罪に至る第二次大戦のある物語
By Laura Hillenbrand Radom House
発売以来、米主要各紙のベストセラーのトップの座を30週以上も占める史上でも珍しいロングランの売れ行きを見せている、今米知識人にとっては最もホットな本である。
主人公は、ニューヨーク生まれだが、カリフォル二ア育ちのルイス・ザンペリニ(現在も健在で94歳)というイタリア系アメリカ人二世。第二次大戦では両親の祖国は「敵国」だった。
イタリア系ということで幼年期はいじめに遭った。わんぱく小僧転じて中学時代はまさに不良少年だった。走るのだけは群を抜いていた。高校の頃から陸上選手として頭角を現し、名門南カリフォルニア大学陸上部に引っこ抜かれた。
期待通り、1936年ベルリンで開かれたオリンピックには中距離走のアメリカ代表として出場した。メダルにこそ届かなかったが、走りっぷりのよさが観戦していたヒトラーの目にとまり、握手をしたというエピソードの持ち主だ。今も健在で、カリフォル二ア州で悠々自適な生活を送っている。94歳だ。
その後、第二次大戦勃発と同時にザンペリニは米空軍に入隊。日本本土爆撃のミッションに向かう途中、戦闘機がエンジントラブルで墜落。
マーシャル群島沖を漂流すること47日間。グェゼリン島に漂着するが、そこで日本軍に捕まり、日本に連行された。日本に着くや、撃墜された米爆撃機パイロットだけを収容、尋問する横須賀海軍警備隊植木分遣隊(通称大船収容所)に入れられ、終戦まで過酷な尋問と拷問を受ける。罪のない市民を無差別に殺戮したことに対する恨み、憎しみもあっただろうが、それよりもなによりも、同収容所の最大の目的は敵パイロットから米軍の機密情報を聞き出すことにあった。
いってみれば、米軍にとってのキューバ・グアンタナモ収容所と同じだった。それだけに尋問は厳しかった。
著者は、アメリカ競馬史上に名を残した名馬シービスケットについて書いた「Seabiscit: An American Legend」(映画化され、アカデミー賞最優秀作品賞はじめ7部門を独占)が爆発的な人気を博し、一躍有名になった女流作家、ローラ・ヘレンブランド。短い文章で畳み掛けるスタイル。徹底した取材で得た事実を華麗な文章で描き出す才能は高い評価を得ている。
ザンペリニは、帰国後、自分を目の仇にしていじめ抜いた「人を痛めつけることで性的快感を覚えるサディスト、ワタナベ・ムツヒロ伍長」に対する復讐心に燃える。尋問や拷問の後遺症から精神状態がおかしくなり、真夜中に悪夢に悩まされる日々が続く。
そうした中、著名な伝道師、ビリー・グラハム師の集会に出て、キリスト教に入信。自殺した「ワタナベ」とは再会できなかったものの、母親に「今は彼に対する復讐心はない。安らかに眠ってくれ」とのメッセージを送るところでストーリーは終わっている。
「南京虐殺」「バターン死の行進」そして「捕虜虐待」の記憶
正直言って、米兵捕虜に対する日本軍の虐待や中国人に対する残虐行為を扱った本はあまり読みたくない。戦争で死んだ日本人のことは思い浮かべても、敵国や他国の死者たちを思い浮かべることはあまりない。日本人の多くは、これまでそうやって生きてきた。
十数年前、中国系アメリカ人二世、アイリス・チャンの「レイプ・オブ・南京」が、(そこに書かれた事実関係の正確さはともかくとして)米知識人の間では話題になった時も、日本人はなぜこの本がそれほどアメリカ人に読まれるのか、釈然としないものがあった。
最近でこそ「Tears in the Darkness: The Story of the Bataan Death March and Its Aftermath」(邦題「バターン 死の行進」が邦訳されているが、日本軍の米英捕虜に対する加害に目を向ける機会はあまりなかった。
2009年6月には、藤崎一郎駐米大使が米兵捕虜団体の会合に出席して謝罪。10年には岡田外相が「バターン死の行進」で生き残った元米兵捕虜と面会し、外相として初めて公式に謝罪した。こうした行動については保守派はもとより、原水爆被害者団体からも「一方的な謝罪の必要はない」といった批判の声も出ていた。
確かに、戦争をどうみるかは依然としてセンシティブだ。アメリカ人の大半は、ヒロシマ、ナガサキの話や多くの市民を無差別に殺戮した東京空襲(よほど教養のあるアメリカ人以外はその事実すら知らない)を聞きたがらない。
そのことを著者は早くも承知だ。主人公が収容された大船収容所に関する多くの日本語資料を入手したが、その翻訳の労をとった日本人の名前は一切公表していない。
今なぜ日本軍の残虐モノが取り上げられ、売れているのか
今、アメリカ人で日本を好感を持っている市民は82%(ギャラップ調査)で好感度は英国、カナダ、ドイツに次いで第四位。米国中にはトヨタやホンダの車が走り回り、国技である大リーグでは何人もの日本人選手が活躍している。第二次大戦などは遠い昔の話のようにも思える。
それなのに、今なぜ人気作家はこのテーマを選んだのだろうか。
冒頭、著者は、ウォルト・ホィットマンの「The Wound Dresser」の一節を引用している。南北戦争当時、ホイットマンが志願看護士として陸軍病院で働いた時の体験から生まれた詩だ。
「今、最も新しくて、最も深く、君(傷病兵)を襲っている恐怖とはなにか。激しい戦闘か、あるいは巨大な敵軍の包囲網か。心の奥底で君が恐れ戦いているのは」
傷ついた兵士たちの姿や積み上げられた兵士たちの切断された手足にホイットマンは衝撃を受ける。そこから死傷した兵士に「英雄」の姿を見るのだ。著者もまたザンペリニに「英雄」の姿を見ようとしたに違いない。
そのためか、この本の書評を書いたほとんどの評者は、「まるで映画を見るような描写」(ニューヨーク・タイムズ・ブック・レビュー)、「宝石商が宝石を鑑定するような著者の筆致」(ニューズウィーク)と、文章力の称賛に終始している。また「英雄」としてのザンペリニに惜しみない拍手を送っている。アメリカ人にとっては、ちょうど日本人が司馬遼太郎の「坂の上の雲」に出てくる滅私奉公の軍人たちに涙するのにも似た感情なのだろう。ひと言で言えば、お国のために肉体的にも精神的にも極限状態にまで追いやられた兵士の言動がアメリカ人の心の琴線に触れているのだろう。それが爆発的に売れている理由だろう。
日本人の心情にも精通している米ジャーナリストのピーター・エニス(「The Bottom Line」編集主幹)はこう見ている。
第二次大戦はまさに書き手にとっては宝の山。題材が埋もれている。確かに日本軍の捕虜収容所の実態が生々しく描かれているが、この本が売れていることと『反日』とはそれほど関係があるとは思えない。この本は、一個の人間としてのザンペリニの生き様を人気作家が書いたことが売れている理由だと思う」
この本が邦訳され、多くの日本人が読んだ時、どのような印象を受けるか。
たった60数年前に日米が敵として戦った第二次大戦。その記憶を一人一人がどう咀嚼しているかで、印象も変わるはずだ。
msn産経ニュース2011.8.6
http://sankei.jp.msn.com/world/news/110806/amr11080612010007-n1.htm
日本軍の米英捕虜に対する加害に目を向ける機会はあまりなかったと書いているが
バターン死の行軍というのはですね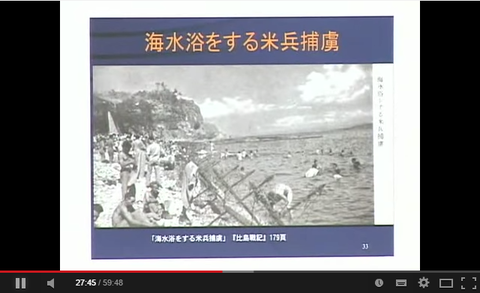
捕虜に海水浴させてたりするんで謝罪の必要なんかあるんですかね
他のサヨク新聞ならともかく産経が一体どうしたことだと思って著者を調べてみたら
高濱 賛(たかはま たとう、1941年 - )は、日本出身のジャーナリスト。アメリカ合衆国在住。
略歴
東京都1941年6月8日生まれ。1965年カリフォルニア大学バークレー校卒業(専攻はジャーナリズム・ 国際関係論)。
1967年読売新聞社入社。ワシントン特派員、総理官邸キャップ、政治部デスクを経て、同社シンクタンク・調査研究本部主任研究員。
1995年からカリフォルニア大学ジャーナリズム大学院客員教授、1997年同上級研究員。1998年パシフィック・リサーチ・インスティテュート上級研究員、1999年同所長。
ジャーナリストとして、日本では『SAPIO』、『潮』、『選択』、『外交』、『ブリタニカ国際年鑑』、『日経ビジネス・オンライン』、『時事通信Janet』などにアメリカ関連の記事、コラムを寄稿している。アメリカでは、『ロサンゼルス・タイムズ』、『羅府新報』、『JPRリポート』などに日本の政治・社会情勢について寄稿しているほか、NPRラジオ、ローカルテレビ局に随時出演している。
著書
『中曽根外政論―総理は何を目指しているのか?』 PHP研究所、1984年7月。
『レーガンの次は誰か?―「1988年」を狙う全実力者ファイル』 PHP研究所、1985年11月。
『新「憂国論」―私たちは今何をなすべきか』 アスキー、2000年2月。
『日本の戦争責任とは何か』 アスキー、2001年4月。
『アメリカの歴史教科書が教える日本の戦争』 アスコム、2003年7月。
『捏造と盗作―米ジャーナリズムに何を学ぶか』潮ライブラリー=潮出版社 2004年10月。
『アメリカの内戦』(マイケル・リンド著)訳 アスコム 2004年7月。
『マイティ・ハート』(マリアンヌ・パール著)訳 潮出版社 2005年4月。
『英語は8歳までにはじめなさい!』 アスコム、2007年4月。
潮出版社→創価学会系の出版社。
あ?(´・ω・`)何この人
よりによってマイティ・ハート翻訳した人なの!?
マイティ・ハート著者マリアンヌ・パール氏は熱心な創価学会員で
友人のアンジェリーナ・ジョリー主演、夫ブラッド・ピット製作で映画化したというあの
高濱賛講演依頼プロフィール
http://www.kouenirai.com/profile/2046.htm
日韓フォーラムといえばWC日韓共同開催したあの
嫌韓の産みの親とでもいうあの
→サッカーWC日韓共同開催の黒幕
なんだけど
日韓フォーラムHPによると
日韓フォーラムは、1993年に行われた細川護煕総理大臣と金泳三大統領との日韓首脳会談に基づき設置された民間レベルの政策協議のためのフォーラム
http://www.jcie.or.jp/japan/gt/kjf.html
とあるので1992年に活躍してたというのがよく分からず
日韓フォーラム、日本国際交流センター双方で検索しても高濱賛氏の名前がない
アイリス・チャンなど抗日連合の動きを書いた記事なども出てきて
http://www.history.gr.jp/~nanking/books_sapio02227_04.html
ちょっと困惑
そして捕虜虐待は確かにいけないことだが過酷な尋問と拷問は
「敵パイロットから米軍の機密情報を聞き出すことにあった」
がーん
この発想は全くなかったので
軍事を知らずして平和を語るなかれ(by勝谷誠彦)というのは本当だなぁ・・・と反省した次第
高濱賛氏については今後を注視(ΦωΦ)
以下、詳細 http://blog.livedoor.jp/aryasarasvati/archives/42320276.html
「アンブロークン」の内容を一蹴した日本海軍の歴戦の搭乗員たち
・



















