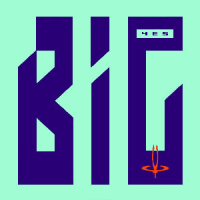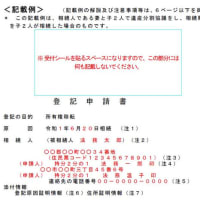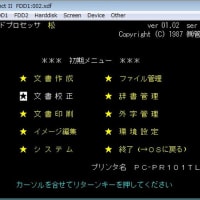内容は目次を書き連ねるだけで、わかる人にはきっと想像がつくだろう。
第1章 1971年、京都の高校で紛争があった夏
第2章 1971年、岡林信康が消えた夏
第3章 1971年、高橋和巳が死んだ5月
第4章 1969年、「善のウッドストック」と「悪のオルタモント」
第5章 1971年、「小さな恋のメロディ」に惹かれた初夏
第6章 1973年、ローリングストーンズ幻の日本公演
第7章 1968年、パリ五月革命の内実
第8章 毛沢東「文化大革命」を支持していたころ
第9章 左翼思想はどこでついていけなくなったか
僕なんかは共鳴しっぱなし。深夜ラジオを聴き始めた頃には岡林信康は既に第一線から退いていたし、高橋和巳はその後背伸びして読んだものだ。アメリカンニューシネマの話題作はみんな観たけれど、中学生にとって心がときめいたのは「小さな恋のメロディ」のほうだったな。それより少し前に時代が遡る学生運動のことは新聞やテレビで見聞きしていて、代々木系と反代々木系は何が違うのかも知らなかったが、こういう運動が社会を変革していくものだとただ漠然と思っていた。今にして思えば学生運動のピークは安田講堂占拠の頃だったのだろう。その熱気は徐々に退潮していき、あさま山荘事件から露見した連合赤軍のリンチ事件がとどめを刺した。
そうやって世の中は沈静化して、僕等の世代は「シラケ世代」と呼ばれるようになったが、その呼称には反発を覚えたものだった。決して自ら率先して行動を起こそうとは考えなかったくせに、いつかまたそういう状況が再び来ることを密かに期待して待っていた。長じて大学に入学して上京した頃は愚かにもやがて80年安保闘争があると思っていたのだが、実際にはそんなものはありゃしなかった。民青だの革マルだの中核派だの学内にそんな立て看板は散見されたが、誰も見向きもしなかった。今でも覚えているのは、郊外の山の中に移転した広大なキャンパスの中、どこのセクトだか覚えていないがヘルメットをかぶってシュプレヒコールを挙げながら練り歩く一団を、他の学生が遠巻きに眺めている光景。それは異様というよりも滑稽な光景だった。こんな風に醒めた見方しかできないのがシラケ世代と呼ばれる所以だろうけど。
全共闘世代に対する憧憬は年齢を重ねるとともに懐疑的なものに変わっていって、彼等の殆どは高邁な思想を持っていた訳ではなく、祭りの中でヒロイズムに酔っていただけなのだろうと理解したが、自分がその祭りに参加できなかった残念さはそうそう払拭できるものではない。島田雅彦じゃないけれど、左翼に対するちょっとねじれたコンプレックスはずっと持ち続けている。でも先日、自宅の古雑誌を整理していて何十冊か保存していた朝日ジャーナルを読み返し、今となってはその生硬な主張に気恥ずかしさを感じて殆ど処分してしまった。
この本は、そんな遅れてきた青年(少年)の心象風景を丹念に綴っているが、きっとそれほど売れないだろうな。だって、そんな思いに共感できる世代は非常に幅が狭くて、おそらく著者の±2年ぐらいだろう。それより上の世代は当事者の世代だし、それより下の世代は当時幼すぎてそんな思いを持たなかっただろうから。本の末尾に締め括りらしいことが書かれているが、結論なんてものではない。そもそも総括など必要なくて、あの時代のごく限られた世代でこういう思いを引き摺っている人間が一定数いる、という事実を記録しただけで充分でないかな。
(かみ)
最新の画像もっと見る
最近の「Book Review」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事