
土方歳三は新選組の副長として有名ですが、元は農家の末息子です。土方家は代々副業として薬を作って売り歩いていました。歳三は武州日野(東京都日野市)の石田村の出身、土地の名前から「石田散薬」と呼ばれていました。一般に石田散薬と呼ばれるのは打ち身・捻挫などに効く鎮痛剤でそのほかに「虚労散薬」と呼ばれる薬もあり、こちらは結核にかかった沖田総司に飲ませていたので、呼吸器系の薬ではないかと思われます。
虚労散についての細かい記述はありませんでしたが、石田散薬については本文中にも少し説明あありました。
減量は村のそばを流れている浅川河原でとれる朝顔に似た草で、葉に、トゲがあるそうだ。その草を土用の丑の日に採り、よく乾かして乾燥させ、後は黒焼きにし、薬研でおろして散薬にし、患者にはそれを熱燗の酒で一気に飲ませる。奇妙なほどに効いた。のちに池田屋ノ変のあと負傷した新選組隊士に歳三がひとりひとりに口を割るようにして飲ませてみたところ、二日ほどで打ち身のシコリがとれ、骨折も肉巻きがしなかったといわれる。
新潮文庫『燃えや剣・上』p15
ここに挙げられているトゲのある草は、一般にミゾソバ(溝蕎麦)と呼ばれ、別名ギュウカクソウ(牛革草・牛額草とも書く)とも呼ばれるタデ科の草本です。形が蕎麦に似ていて溝傍に生えることからミゾソバと言うようです。また、葉の形が牛の額に似ていることからギュウカクソウとか牛の額とも呼ばれています。
ミゾソバ自体は薬草としては認められていないようですが、実際に石田散薬が薬として服用されていた事実は興味深いです。日本薬局方は黒焼きにしてしまったものは薬品としては認められないと主張しています。しかしローストした西洋タンポポやコーヒーに至っても少なからぬ薬効が認められるので、まったくもってうさん臭いとは言い切れないものがあります。
実際に公的な機関でミゾソバを収穫して石田散薬を作ってみるワークショップなどもあるようです。参加してみたいですね。
虚労散についての細かい記述はありませんでしたが、石田散薬については本文中にも少し説明あありました。
減量は村のそばを流れている浅川河原でとれる朝顔に似た草で、葉に、トゲがあるそうだ。その草を土用の丑の日に採り、よく乾かして乾燥させ、後は黒焼きにし、薬研でおろして散薬にし、患者にはそれを熱燗の酒で一気に飲ませる。奇妙なほどに効いた。のちに池田屋ノ変のあと負傷した新選組隊士に歳三がひとりひとりに口を割るようにして飲ませてみたところ、二日ほどで打ち身のシコリがとれ、骨折も肉巻きがしなかったといわれる。
新潮文庫『燃えや剣・上』p15
ここに挙げられているトゲのある草は、一般にミゾソバ(溝蕎麦)と呼ばれ、別名ギュウカクソウ(牛革草・牛額草とも書く)とも呼ばれるタデ科の草本です。形が蕎麦に似ていて溝傍に生えることからミゾソバと言うようです。また、葉の形が牛の額に似ていることからギュウカクソウとか牛の額とも呼ばれています。
ミゾソバ自体は薬草としては認められていないようですが、実際に石田散薬が薬として服用されていた事実は興味深いです。日本薬局方は黒焼きにしてしまったものは薬品としては認められないと主張しています。しかしローストした西洋タンポポやコーヒーに至っても少なからぬ薬効が認められるので、まったくもってうさん臭いとは言い切れないものがあります。
実際に公的な機関でミゾソバを収穫して石田散薬を作ってみるワークショップなどもあるようです。参加してみたいですね。
 | 燃えよ剣〈上〉 (新潮文庫) |
| 司馬 遼太郎 | |
| 新潮社 |










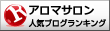
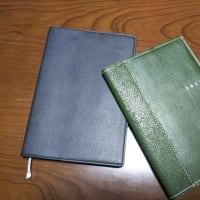














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます