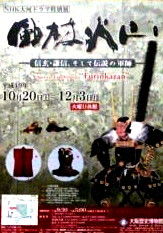信濃行3
3日目
別所線にて下之郷駅下車
「生島足島神社」日本の中心にあるとの事です。この日は七五三だったのか着飾った子供をつれた家族が何組もいました。
真田昌幸・信之等歴代の上田城主が神領を寄進し、社殿を再建したそうです。
「歌舞伎舞台」ここには武田信玄関係の起請文及び願文・朱印状が数多く展示されています(複製)。
上田に戻りしなの鉄道で坂城へ。
長野県一帯、武田氏ゆかりの人物の幟を掲げる中、ここは一味ちがいます。
「村上義清 誕生の地」まさに反旗を翻していますね。
坂城町鉄の展示館 記念展「村上義清と風林火山の時代」
村上義清は武田信玄を2度も破った猛将、信玄の北信濃進出は彼の為に遅れる事を余儀なくされた。砥石城を真田幸綱(幸隆)の謀略で失って以降、次第に武田軍に圧され越後に亡命。上杉謙信を頼る事となり、これが川中島での5度にわたる武田・上杉対決の一因となった。
展示品では城坂稲荷神社に奉納された、義清・信玄一騎討ちの絵馬や村上十八将図(複製)などが見ごたえありました。
しなの鉄道で小諸へ
「小諸城」写真の三の門への道は下り坂になっており「穴城」と呼ばれていたのが理解できます。
この城は武田信玄の命により山本勘助が縄張りをおこなったといわれています。
「鏡石」山本勘助が小諸城築城の時に研磨したと伝えられています、隕石との説もあるそう。
小諸を後にし、上田に戻りました。
翌日上田より長野を経由し特急しなので帰途につきました。