一体・・・一体これは誰なんだ・・・。と初っ端から思わず遠い目をさせてくれた彼。 最早、"You are not yourself!"は、執政家のキーワードなのか。何よりも辛いのは、彼が無能に見えること。無駄だと思い込んでいるのか、矜持が邪魔をしているのかローハンに援軍も要請せず、あからさまに無謀なオスギリアスへの特攻を強要し(戦略的な意義も見えてこない・・・)、オークの大軍が攻めてきたら乱心して士気を下げるようなことを喚き散らす。ああ・・・。ついでに言うと、ミナス・ティリスに非戦闘員の姿が多いのも(原作を読んでいる感じだともっと疎開させている)、ローハン軍より(総人口は多い筈なのに)ゴンドール軍が少ないのも、彼の臨戦体勢への無策のように思えてしまう。人として能う限りの事をやっても尚、国を守りきれない絶望、みたいなものが彼を形成する重要要素だと思っていたのにこれでは・・・!
遥か昔、中学だか高校だかの国語の教科書で、「性、狷介、自ら恃むところすこぶる厚く、賎吏に甘んずるを潔しとしなかった。」(『山月記』 中島敦 著)という一文を読んだ時に、(デネソールだ・・・!)と内心叫びました。つまり私の原作のデネソールのイメージは、その性狷介にして孤高、といったところでした。そして、"Unfinished Tales"には、デネソールの為人を表す文言として、"A masterful man, both wise and learned beyond the measure of those days, and strong-willed, confident in his own powers, and dauntless." 「支配者然とした男、賢く、今日における限界を越えて造詣が深く、そして強い意志をもち、己の力を恃むこと厚く、怖れを知らなかった。」そんな男だからこそ、彼の積み上げた全てが瓦解して狂気の内に、自らの人生に幕を引く姿が壮絶な悲劇なのでしょう。
神話的な部分を描ききれないからか、意図的に薄めたのかはわかりませんが、映画にはそのような傾向が見られるので、デネソールもその一環なのでしょう。長い間王なき玉座を守ってきた権力者が、突然王が帰ってきて迎え入れるのは不自然だ(いや、私はそこが好きなんだけれども。)、ということで当代の権力者を無能にして、アラゴルンがゴンドールを掌握するのを不自然に見せないように配慮したのかな、とも思う。実際掌握していたのは、ガンダルフでしたがね。
まあ、映画のデネソールとアラゴルンが出会わなかったのは、原作以上に幸せなことかもしれません。いや、一番恐ろしい事態というのは、ありえない事ながら原作デネソールと映画アラゴルンが出会うことか。血筋という天与の才を与えられている筈のアラゴルンが「私が望んだことではなかった・・・。」などと言っているのをデネソールが聞いたら憤死するだろーなーと。ソロンギル設定が生きている以上、二人は昔見えたことがあるはずだが、あの第一部、特にSEEの後ろ向きな馳夫さんが一体ゴンドールでどんな態度を取っていたのか、想像もつかない。
下記の如く誓いを立てた以上、映画デネソールを擁護したいとおもいますが、その際にパランティアの強力さがポイントでしょう。パランティアに毒されて狂気を深めた筈ですが、正当な所有者であるアラゴルンでさえもあんなにのた打ち回っているということは、映画版パランティアはそりゃあもう強烈なんですよ。だから、デネソールはもう数年前から完全に狂気に捕らわれてしまっていたのですが、その前は有能は支配者だったのです。イムラドリスへ旅立つ前のボロミアがオスギリアスで憂慮した顔をして見せたのは、パパが嫌いなのではなくて、その狂気の深さを憂いたのです。・・・全然弁護してないよ。
ジョン・ノブル氏のデネソール解釈
元々はもっと痩せた面差しのイメージでしたが、デネソールとしてノブル氏の風貌はかなりいいと思っていました。『王の帰還』公開前に彼のインタビューを読んで、意外ではありましたがかなり興味深かったです。
ボロミアとの関係は?との問いに「ボロミアはデネソールの最愛の息子。彼はデネソールの鏡像だった。大きく、強き戦士。ボロミアを失うことで、デネソールは彼自身を殺したようなものだ。」と応えていましたが、私はファラミアがデネソール似で、ボロミアは自身に似ていないが故に溺愛していたと思っていました。ただ、「鏡像」という表現は意味深長かもしれません、等身大の自分ではなく斯くありたかった自分を映し出している鏡であったのかも。そうであるために、希望とも言える長子を喪って精神のバランスを崩したかな、と。理想の自分としてのボロミアというのは、屈託なく祖国と民人を愛し、その同胞愛と自己愛との境界に悩むこともなく、弱きを助ける誇り高い輝ける騎士という姿かな、と。デネソールは多分、若き日にソロンギルと出会い、王が遠からず還ることを知り、王と民との双方に対して屈折した思いを抱いてしまったのではないかなと思われるんですよね。双方というのは、王に対してはその力がある(様に見受けられる)のにこの暗い時代にあって未だ還らぬ事に、民人に対してはその日が訪れた時に残酷なほど無邪気に歓呼して向かえるであろう事に。
「彼はファラミアを愛していた?」
「勿論だ、しかしファラミアはよりデネソールの亡き妻に似ていた。そして私は、彼女がこの世にいないことに対して腹立たしく思っていて、彼の息子との関係にそれが影響したのではないかと思っている。」
ロマンティックな解釈で、結構好きです。妻の死という人にはどうすることもできいことに対して、腹を立てるなんて人間的な愚かさが少しはあってもいいな、と・・・思っていた。映画を観たら、彼は人間的な愚かさなど山ほど持っていて、もういいです、という感じでしたが・・・。
ところで、兄弟共に顔立ちは母親似ではないかな、と思うのですが。(だって、エルフ以外の男では一番、美しいという描写が多いように思う。)ということは、中身ですか?原作ファラミアのような性格の美女って、すごく怖いような気がするのは私だけですか?そうですか。
デネソールのファラミアへの思いは同族嫌悪が混ざっていたと思う。人の心を読むことが出来、人よりも遠く深く見ることができる視野を持つが故に、蟠っていく心の闇といった部分が。そこに、このノブル氏のご意見「フィンドゥイラス似」というのを加味するとしたら、「人の心を読んだが、彼は人を軽蔑するよりは同情する方に心を動かした。」というファラミアの在り方は、フィンドゥイラス譲りの優しさからきている、ということにならないかな。人の心を読んで軽蔑するというのは自己防衛でもあったと思われるので、人を憐れんでいるファラミアは傷つくことも多かったと思うのですが、それが同じ能力を持つものとして、父として、デネソールは痛ましかったということが無きにしも非ずではないでしょうか。しかしそれを素直に認められない捻りの入った性格のお父上は、妻を失った哀しみと同様に腹立たしさに摩り替えてしまったのでした。なんて。脳内補完しすぎ。
それにしてもですね、日本ヘラルドの公式サイトにはなんで、ノブル氏のインタビューが割愛されているんですか。悪役だからいいだろう、という認識ですか?
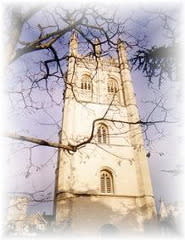
photo by psy
Magdalen College, Oxford
遥か昔、中学だか高校だかの国語の教科書で、「性、狷介、自ら恃むところすこぶる厚く、賎吏に甘んずるを潔しとしなかった。」(『山月記』 中島敦 著)という一文を読んだ時に、(デネソールだ・・・!)と内心叫びました。つまり私の原作のデネソールのイメージは、その性狷介にして孤高、といったところでした。そして、"Unfinished Tales"には、デネソールの為人を表す文言として、"A masterful man, both wise and learned beyond the measure of those days, and strong-willed, confident in his own powers, and dauntless." 「支配者然とした男、賢く、今日における限界を越えて造詣が深く、そして強い意志をもち、己の力を恃むこと厚く、怖れを知らなかった。」そんな男だからこそ、彼の積み上げた全てが瓦解して狂気の内に、自らの人生に幕を引く姿が壮絶な悲劇なのでしょう。
神話的な部分を描ききれないからか、意図的に薄めたのかはわかりませんが、映画にはそのような傾向が見られるので、デネソールもその一環なのでしょう。長い間王なき玉座を守ってきた権力者が、突然王が帰ってきて迎え入れるのは不自然だ(いや、私はそこが好きなんだけれども。)、ということで当代の権力者を無能にして、アラゴルンがゴンドールを掌握するのを不自然に見せないように配慮したのかな、とも思う。実際掌握していたのは、ガンダルフでしたがね。
まあ、映画のデネソールとアラゴルンが出会わなかったのは、原作以上に幸せなことかもしれません。いや、一番恐ろしい事態というのは、ありえない事ながら原作デネソールと映画アラゴルンが出会うことか。血筋という天与の才を与えられている筈のアラゴルンが「私が望んだことではなかった・・・。」などと言っているのをデネソールが聞いたら憤死するだろーなーと。ソロンギル設定が生きている以上、二人は昔見えたことがあるはずだが、あの第一部、特にSEEの後ろ向きな馳夫さんが一体ゴンドールでどんな態度を取っていたのか、想像もつかない。
下記の如く誓いを立てた以上、映画デネソールを擁護したいとおもいますが、その際にパランティアの強力さがポイントでしょう。パランティアに毒されて狂気を深めた筈ですが、正当な所有者であるアラゴルンでさえもあんなにのた打ち回っているということは、映画版パランティアはそりゃあもう強烈なんですよ。だから、デネソールはもう数年前から完全に狂気に捕らわれてしまっていたのですが、その前は有能は支配者だったのです。イムラドリスへ旅立つ前のボロミアがオスギリアスで憂慮した顔をして見せたのは、パパが嫌いなのではなくて、その狂気の深さを憂いたのです。・・・全然弁護してないよ。
ジョン・ノブル氏のデネソール解釈
元々はもっと痩せた面差しのイメージでしたが、デネソールとしてノブル氏の風貌はかなりいいと思っていました。『王の帰還』公開前に彼のインタビューを読んで、意外ではありましたがかなり興味深かったです。
ボロミアとの関係は?との問いに「ボロミアはデネソールの最愛の息子。彼はデネソールの鏡像だった。大きく、強き戦士。ボロミアを失うことで、デネソールは彼自身を殺したようなものだ。」と応えていましたが、私はファラミアがデネソール似で、ボロミアは自身に似ていないが故に溺愛していたと思っていました。ただ、「鏡像」という表現は意味深長かもしれません、等身大の自分ではなく斯くありたかった自分を映し出している鏡であったのかも。そうであるために、希望とも言える長子を喪って精神のバランスを崩したかな、と。理想の自分としてのボロミアというのは、屈託なく祖国と民人を愛し、その同胞愛と自己愛との境界に悩むこともなく、弱きを助ける誇り高い輝ける騎士という姿かな、と。デネソールは多分、若き日にソロンギルと出会い、王が遠からず還ることを知り、王と民との双方に対して屈折した思いを抱いてしまったのではないかなと思われるんですよね。双方というのは、王に対してはその力がある(様に見受けられる)のにこの暗い時代にあって未だ還らぬ事に、民人に対してはその日が訪れた時に残酷なほど無邪気に歓呼して向かえるであろう事に。
「彼はファラミアを愛していた?」
「勿論だ、しかしファラミアはよりデネソールの亡き妻に似ていた。そして私は、彼女がこの世にいないことに対して腹立たしく思っていて、彼の息子との関係にそれが影響したのではないかと思っている。」
ロマンティックな解釈で、結構好きです。妻の死という人にはどうすることもできいことに対して、腹を立てるなんて人間的な愚かさが少しはあってもいいな、と・・・思っていた。映画を観たら、彼は人間的な愚かさなど山ほど持っていて、もういいです、という感じでしたが・・・。
ところで、兄弟共に顔立ちは母親似ではないかな、と思うのですが。(だって、エルフ以外の男では一番、美しいという描写が多いように思う。)ということは、中身ですか?原作ファラミアのような性格の美女って、すごく怖いような気がするのは私だけですか?そうですか。
デネソールのファラミアへの思いは同族嫌悪が混ざっていたと思う。人の心を読むことが出来、人よりも遠く深く見ることができる視野を持つが故に、蟠っていく心の闇といった部分が。そこに、このノブル氏のご意見「フィンドゥイラス似」というのを加味するとしたら、「人の心を読んだが、彼は人を軽蔑するよりは同情する方に心を動かした。」というファラミアの在り方は、フィンドゥイラス譲りの優しさからきている、ということにならないかな。人の心を読んで軽蔑するというのは自己防衛でもあったと思われるので、人を憐れんでいるファラミアは傷つくことも多かったと思うのですが、それが同じ能力を持つものとして、父として、デネソールは痛ましかったということが無きにしも非ずではないでしょうか。しかしそれを素直に認められない捻りの入った性格のお父上は、妻を失った哀しみと同様に腹立たしさに摩り替えてしまったのでした。なんて。脳内補完しすぎ。
それにしてもですね、日本ヘラルドの公式サイトにはなんで、ノブル氏のインタビューが割愛されているんですか。悪役だからいいだろう、という認識ですか?
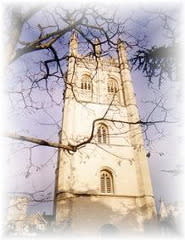
photo by psy
Magdalen College, Oxford










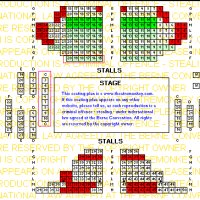















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます