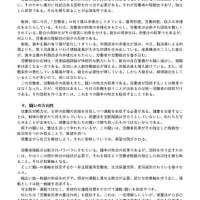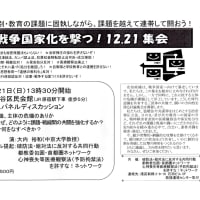自民党の憲法改悪策動は、安倍の死去によって停滞している。安倍の後を引き継いだ岸田内閣は、憲法改悪に安倍ほどは熱を入れていない。岸田にとって憲法問題は、党内旧安倍への政治的配慮、自己の党内政治基盤の安定のための方便であり、憲法改悪の籏を下ろしたわけではないので、危険な状態に変わりはない。現在は、自民党の裏金キックバック問題で、自民党への逆風が強く、先の3選挙区の補選では、二つの選挙区に候補者を擁立できず、唯一候補者を立てた選挙区で、立憲の候補者に完敗した。岸田への逆風となっている。岸田の在任期間は短くなりそうである。
しかし、3選挙区で全勝した立憲民主党は、政権を担う力があるのだろうか。彼らが政権を取ったとき、どのような政策を実施するのか?自民党との差別化をどの点に置くのか?明確に福祉国家の実現の方向性を示せるか、経済政策を大企業優先から、労働者民衆に基礎を置いた福祉政策重視の政策を提起し、労働者民衆の多くの支持が得られるかどうかである。大企業に忖度した中途半端な福祉政策では、労働者民衆の多くの支持は得られないだろう。
一方で、国際情勢は、ウクライナやガザをめぐる情勢は、戦争による多くの兵士や民間人が死んでいる。その事は、労働者民衆にとってどんな意味があるのか?アメリカの大学で学生がイスラエルへの抗議や、イスラエルの軍事援助をしているバイデン政権を批判している。学生たち若者がこうした言動をするのは、戦争が国家の支配者にとって何らかの意味があったとしても、労働者民衆にとっては無意味なもの、というより有害なものという認識なのでる。国家の行為と労働者民衆・若者との認識が乖離していることを示している。労働者民衆・若者が自分たちの手に政治の実権を握ることを意識することが必要である。それこそが真の民主主義である。その実現に向け一歩前進して欲しい。その役に、以下の文章が役に立つと確信する。これは日本国憲法に関する意見であるが、戦後世界と根本的問題とその本質を明らかにし、労働者民衆の課題を示していると確信している。
長文であるが、さごまで読んで欲しい。
1,戦後憲法は、労働者民衆の闘いで勝ち取ったものではない。
それは、日本帝国主義が連合国(主に米国)に負け、連合国の方針(民主化と再び侵略戦争を起こさせない=9条)に基づいて作られた。ちなみに、天皇制存続は、連合国の総意ではなく、マッカーサーの強い意向だった。アメリカ本国政府は、その判断を尊重した。
ところが、49年中国毛政権の誕生と50年の朝鮮戦争の始まりによって、東アジアにおける冷戦体制(=米ソの対立と依存の関係=戦後世界秩序)が明瞭に姿を現した。アメリカは日本を極東における「反ソ、反共」の砦にする戦略に組み込む方針を明確にする。それを拒否すれば、日本はソ連に組みすることになるので、日本資本主義・支配階級はアメリカ側を選択するしかなかった。
2,戦後体制はどのようにして形成され、その政治性階級性は何であろうか?
それは、戦前に準備され、戦中に基本線が形成され、戦後明確となる。
第1次大戦の最中に、ロシアで労働者の革命が起こり、労働者国家が成立したことは、この世界大戦が資本主義の危機の表現であり、直ちに労働者革命に転化する状況になったことを示した。
資本主義経済の極めて深刻な危機は、ブルジョア民主主義の統治システムの弱体化、その思想も衰えるので、左右の政治勢力が力を増し、対立が激化する。
ドイツでも大戦の終戦間際の1918年11月はじめ、兵士・労働者の革命的闘争が起こったのも、そのことを示している。その結果、帝政は廃され、共和国となる。
18年11月11日、ドイツは連合国と休戦協定を結ぶ。革命運動は23年まで継続されるが、反革命勢力による武力攻撃によってそれは失敗に終わる。
イタリアは、第1次大戦の戦勝国であったが、領土獲得を実現できず、戦後インフレとなり、20年、農民の土地占拠、農業労働者のスト攻勢が相次ぎ、鉱業都市では経営側のロックアウトに対抗して労働者の工場占拠が広がった。緊迫した情勢となり、左右の対立が厳しくなった。
ムッソリーニが登場し、反労働者・農民勢力を組織し勢力を拡大。1921年、各地のファシスト勢力を結合してファシスト党を結成し、1922年「ローマ進軍」を組織した。混乱を恐れた国王は、ムッソリーニを首相に任命。ムッソリーニはその後、ファシスト党による独裁体制を確立。反対派を厳しく弾圧した。
ファシストが権力を握ったことは、左翼の危機でもあった。
第1次大戦後、一時的に危機は収まったかに見えたが、資本主義の矛盾は解消されたわけではなかった。
1929年の世界大恐慌の発生は、資本主義の蓄積された矛盾の大爆発で、最大の危機であった。階級対立はより先鋭となり、革命の客観的条件は成熟していた。しかし、主体の側=革命勢力就中共産党の準備は不十分だった。その原因は、コミンテルンにあった。
コミンテルン=共産主義インターナショナルは、世界革命の指導部として1919年3月、レーニンの努力でモスクワに本部を置いて創立された。
ロシア10月革命で誕生した労働者国家ソ連は、社会主義建設を目指していた。レーニンは、ソ連の社会主義化の展望を先進資本主義国の労働者革命の勝利と、その勝利した労働者階級の援助・協力により、ロシアの後進性を克服できると考えていた。とりわけドイツの労働者革命の成功とドイツの進んだ工業力はソ連を助けると。それ故、コミンテルンの役割は大きかった。
しかし、1924年のレニン死後(レーニンは1922年5月、別荘で倒れ、それ以降公務を十全に果たすことが出来なくなり、党の実権はスターリンを含むごく少数の幹部に握られる。)、ロシア共産党(ボルシェビキ)の主導権を巡って、書記長スターリンとトロツキー左翼反対派の対立が大きくなる。スターリンは書記長という地位を利用して、トロツキーとその仲間を党の要職から排除していく。トロツキーは社会主義化の展望を、レーニンと同様国際革命に求めていた。これに対抗するスターリンは、国内の経済が厳しい状況にあり、また国際革命の一時的停滞状況を背景に「一国社会主義」を打ち出す。それは、当時のソビエトロシアの社会・経済の現実を背景にしたものであったので、それなりのリアリティーがあった。
一国社会主義論は、他国の革命に依存しないで、社会主義を実現しようという主張であったので、国際革命を重視しない。がこれは、マルクス・レーニン主義ではないので、ここからマルクス・レーニン主義の堕落が始まることとなる。
コミンテルンは本来、世界革命のための指導部であったが、スターリンはロシア10月革命の栄光を我が物としたので、コミンテルンを支配するようになる。ロシア共産党の主導権争いは、コミンテルンにも及びトロツキー派はここからも排除されたので、コミンテルンは一国社会主義論を受け入れる。
こうして、コミンテルンも又「一国社会主義」論が基本的理論となる。この論が、革命運動に甚大な悪影響をもたらしていく。
ソ連一国で経済を発展させることは極めて困難なので、経済発展のために資本主義国の援助を必要とした。そのため、資本主義国における革命運動に手心を加えることとなった。
また、一国社会主義論は、自国だけで社会主義を実現できるという立場なので、他国の革命がなくても良く、コミンテルンの世界革命指導部の役割を重要視しなくなる。
こうして、コミンテルンの方針は、革命運動において自国帝国主義の打倒より、ソ連の「一国社会主義」実現のための行動を優先させるようになる。
また、スターリンは、10月革命の際、帝国主義諸国が干渉戦争を仕掛け、領土を切りとろうと試みたことを忘れていなかったので、「ソ連の防衛」を重要視していた。この観点もコミンテルンの基本的な方針となっていく。
一国社会主義論は、帝国主義諸国に対する革命闘争を最重要課題としない、また、帝国主義諸国の経済援助・貿易を重視したので、コミンテルンの帝国主義諸国における革命闘争指導・方針は、不徹底なものとなった。さらに、コミンテルンは労働者国家ソ連の防衛を優先的課題としたので、各国共産党の戦略戦術はそのようなものとなった。
この点が最も良く現れたのが、中国の国共合作である。
この事の具体的例が中国革命の局面に出てくる。清朝末期の中国は、欧米帝国主義国と日本帝国主義によって、盛んに食い物にされた。特に日本帝国主義=近代天皇制国家は、満州を切り取り更に中国中原をも侵略し、植民地化しようとしていた。こうした、状況に対して中国国内の反封建=反清朝勢力=孫文を中心とする勢力が台頭し、清朝を倒し近代国家建設を目指した。
その勢力は、孫文=国民党と中国共産党であった。1920年代、国民党の影響力は共産党より遙かに大きかった。国民党はブルジョア政党であったが、コミンテルン・ソ連は国民党の方に多く支援した。金・人共に。中国共産党は、コミンテルンに革命党としては未だ不十分と見なされた。
コミンテルンは、1923年1月、共産党員が国民党に加入するよう指示する。中国共産党の指導部には反対する声もあったが、コミンテルンに逆らうことは難しかったので、指示に従う。
*中国共産党と国民党との関係に関する共産主義インターナショナル執行委員会決議(1923、1、12)
(引用『コミンテルン・ドキュメントⅡ』P19 現代思潮社)
一、中国における唯一の真剣な民族革命的グループは、一部は自由主義的ー民主主義的なブルジョアジーと小ブルジョアジー、 一部はインテリゲンツィヤと労働者とに基礎を置く国民党である。
二、同国における独立の労働者運動はまだ幼弱であり、そして中国に対する中心的任務は、帝国主義者と国内の封建的手先であるが故に、かつまた、労働者階級は全く独立の社会的勢力として、まだ十分に分化していないながらも、この国民ー革命問題の解決に直接の利害を持っている故に、共産主義インターナショナル執行委員会は国民党と若いCCP(中国共産党)との行動が統合されることを必要と考える。
三、従って、現状ではCCPの党員が国民党にとどまることを便宜とする。
以下略
これが、よく知られている第1次国共合作である。この方針は、スターリン・コミンテルンの単なる過ちではない。
国共合作のスターリンの狙いは、日本帝国主義の中国侵略を阻止することであった。国民党と共産党が対立し争っていたら、日帝の侵略を阻止することは難しい。それでは、ソ連防衛が危うくなるとスターリンは考えた。国共合作はソ連防衛にとって最重要課題だった。
国共合作の問題点の二つ目は、国民党と共産党は対等の関係ではなく、国民党に共産党員が加入し、国民党の方針の下で活動することであった。共産党員は、自分たちの党のための活動をすることは出来なかったので、労働者民衆にその宣伝が出来ず、影響力を拡大することも出来なかった。
この時代のように「戦争と革命の時代」において、経済発展の遅れた国で、それ故労働者の組織も思想も未発達であれ、客観情勢は革命化する。主体の側の組織も思想も闘いを通して急速に発展する。この時代における、各国労働者の第一の任務は「自国帝国主義打倒」である。また、植民地・半植民地においては、第一の任務は外国帝国主義とそれとつながっている買弁ブルジョアジーの打倒で、この場合民族主義者との共闘はあり得る。ただし、民族主義者が帝国主義と買弁ブルジョアジーと闘う限りにおいてである。労働者階級の任務は、そこにとどまらないし、とどまってはいけない。労働者革命に向かって引き続き前進しなければならない。
このようには問題を立てないスターリン・コミンテルンの方針は、各国労働者の革命闘争の足を引っ張る事となる。
中国における国共合作の失敗は、蒋介石による上海クーデター(1927.4)によって、中国労働者階級と中国共産党員の最良の人々を失うことで明確になった。蒋介石の本性はファシストであることも同時に明らかになった。しかし、コミンテルンは、それ以降も国民党をより多く支援する。
中国革命を第一義的に追求するなら、労働者階級を組織しその政治的・階級的独立を確立しそれを堅持し、誰が敵かを明確に示し、今どのような戦い方をするべきかを提起することが革命党の任務だった。だが、コミンテルンと・スターリンはそうしなかった。
こうして、中国における労働者は、的確な方針が示されないまま、自然発生的な闘いを帝国主義と軍閥に対し挑んでいき、抑圧されていった。中国では、組織された労働者の闘いはことごとく敗北させられた。労働者は個々に分断され、その階級性は充分担保されなかった。
中国において毛沢東は勝利したが、それは、ロシア10月革命とは異なる階級的性格だったのはそこに起因する。
第1次大戦後、イタリアでファシズムが権力の座についたこと、またドイツの1918~19年の革命的労働者の闘争は、時代が革命か反革命か、又は社会主義対ファシズムという危機の時代に入ったことを示していた。
こうした時代状況において、スターリン・ソ連・コミンテルンの変容を見ていこう。
1923年、ドイツ革命失敗 中国:第1次国共合作
1924年、スターリン「一国社会主義論」
1925年、日ソ基本条約:国交樹立
1927年、上海クーデター(国共合作の失敗)
28年、コミンテルン、「社会ファシズム論」~社会民主主義は主たる敵。
33年、ドイツ:ナチ党・保守派と連立内閣。ヒットラー首相に。全権委任法。独裁体制樹立。
ソ連、米国と国交を結ぶ。
34年、ソ連国際連盟に加盟
35年、コミンテルン7回大会~社会ファシズム論を廃し、反ファッショ人民戦線を呼びかける。
*これは、ブルジョアとの統一戦線の呼びかで、革命闘争の放棄を意味していて、スターリンの意思の表明で、ルーズベルトとチャーチルへのメッセージだった。
コミンテルンは、この年以降、解散までの間、あまり活動していない。
37年、第2次国共合作
39年8月、独ソ不可侵条約~ソ連にとっては、時間稼ぎ。
41年6月22日、独ソ戦、始まる。
41年4月、日ソ中立条約
41年8月、大西洋憲章(ルーズベルトとチャーチル)
41年12月、太平洋戦争、開始
43年1月、カサブランカ会議(ルーズベルトとチャーチル)無条件降伏を要求
43年2月、ソ連、ドイツに勝利
43年6月8日、コミンテルン解散
5月15日の「共産主義インターナショナルの解散を勧告する共産主義インターナショナル執行委員会幹部会の決議」の 一部引用する。(出典;コミンテルン・ドキュメントⅢP443 現代思潮社)
「・・・1919年に設立された共産主義インターナショナルの歴史的役割は、労働者階級運動の内部の日和見主義的な分子による通俗化と歪曲からマルクス主義の諸原理を擁護すること、真の労働者階級の政党の最前線に立っている多数の国における労働者の前衛の強化の促進を助けること、および、彼らが自己の経済的・政治的利益を防衛しファシズムとファシズムが準備中の戦争とに反対する闘争を遂行し、ファシズムに対する主要な砦としてのソヴィエト連邦を支持するために労働者の動員を助ける ことであった。」
*この文言からは、世界革命の任務に関する言及がない。ここにあるのは、その任務を放棄した姿である。
43年9月、イタリア無条件降伏
43年11月、カイロ会談(ルーズベルト、チャーチル、蒋介石)カイロ宣言
11月28日、テヘラン会談(ルーズベルトとチャーチルとスターリン)
45年2月、ヤルタ会談(米、英、ソ)ヤルタ協定
45年5月、ドイツ、無条件降伏
45年7~8月、ポツダム会談三国首脳(米:トルーマン、英:チャーチル→アトリー、スターリン) ポツダム宣言
このような過程は、世界各国の階級闘争の敗北の過程であり、その事実を踏まえてソ連・スターリンは米国と戦後の支配秩序(=対立と依存の関係)を共同で形成していく。いわゆる冷戦体制と言われているものである。それは、スターリン・ソ連が世界革命の障害物になったことを示していた。
3,戦後世界秩序と米国の世界戦略に組み込まれた日本と日本国憲法
① アメリカの対日占領政策の初期のねらい
日本はポツダム宣言を受け入れ、無条件降伏し、連合国軍(主力は米国)に占領される。
連合国の対日占領政策の柱は、民主化(封建性の排除)と戦争遂行勢力の排除、戦争実行力=軍備・軍隊の解体だった。
政策立案は極東委員会(11カ国で構成。後に2カ国参加。)の権限であった。活動開始までは、占領軍総司令官であるマッカーサーにその権限があるとされた。
極東委員会にはソ連も参加。日本をどちらの影響下に置くかという主導権争いがあった。極東委員会の活動開始は、46年2月26日の予定だった。その間、マッカーサーは、自分の権限を行使(米国本国政府の了解を得ながら)し、対日占領政策を矢継ぎ早に具体化していく。アメリカは主導権争いで優位に立ち、日本をアメリカの影響下に置くこととなる。
マッカーサーの対日占領政策遂行における最大の関心事は、占領を問題なく終了させることだった。そのための最重要の懸案事項は、「天皇制」を存続させるか廃止するか、また、戦争責任を問うかどうか。
天皇制廃止の声は、ソ連やオーストラリアや東南アジアの諸国にあった。戦争責任についても、極東裁判の被告人席に立たせようという声もあった。オーストラリアの極東裁判の戦犯候補リストに天皇の名前があった。
天皇制を廃止したり、天皇を戦犯にしたりすれば、日本国内に暴動が起きることをマッカーサーは心配し、それは避けなければならないと考えた。そのためには、天皇制存続と戦犯回避が必要だった。
また、一方で天皇制の存続は、アジア諸国に再侵略の不安を強く抱かせることも事実であった。
この二つの相反する事柄を併存させるために、マッカーサーがとった方策が、憲法に「天皇の象徴化」と戦争と武力の放棄を明記した「9条」を明文化することだった。
② 戦後世界秩序と労働者階級の闘い
戦後世界秩序は、戦前戦中の過程を経て形成された米国とソ連による「対立と依存」の関係として構築された。この関係は、決して体制の矛盾や問題点を解消したものではなく、逆に様々の矛盾や問題点を生み出し、噴出させた。それは、労働者民衆の闘争や暴動として現れた。特に1960年代に、ソ連圏では、チェコの「プラハの春」やポーランドでおこり、西側ではフランスの学生運動や日本の学生運動、また、アメリカではベトナム反戦運動があった。時にはベトナムのように国同士の戦争というかたちで。こうした様々な紛争・闘争は、世界秩序=「対立と依存」の関係を突き破ることが出来なかった。それは、米ソの対立の溝に沿って、反米か反ソに引き裂かれ、労働者の階級性・政治性は解体されたのです。
何故か?それは、戦後世界支配秩序から独立した労働者階級の政治性・階級性が形成されていなかったからである。
③ 米国の世界戦略とそれに組み込まれる日本
戦中は、米ソの関係は依存の側面が強かったが、戦後、世界は米ソの対立と依存による秩序が基軸となり、対立の側面が強く出てきた。特に極東では、中国で国民党と共産党が内戦を争っていて、共産党が優勢となり、1949年に共産党が政権を樹立し、また50年には北朝鮮が韓国に侵入し朝鮮戦争が始まり、日本に駐留していた米国軍が国連軍として参戦し、また中国は義勇軍を派遣した。極東における、軍事的緊張が一気に高まった。アメリカは、日本の再軍備を強く要請。日本は断ることが出来ず、時の首相吉田茂は受け入れる。
冷戦体制は、はじめにヨーロッパで、明瞭な姿を現した。見てみよう。
1946、3 チャーチル「鉄のカーテン」発言
47、3 米大統領トルーマン=ドクトリン:「ソ連封じ込め」政策を発表
47、6 米国務長官マーシャル・プラン発表。このプランの具体化として48年、ヨーロッパ経済 協力機構(OEEC)が西側16カ国(後に西独、スペインが加入で18ヶ国)で発足
47、10 ソ連、コミンフォルム設立(参加:ソ連、東欧諸国、仏・伊の共産党)
48、6 コミンフォルム、ユーゴを追放
48、6 ソ連、ベルリン封鎖
49、1 コメコン(経済相互援助会議)設立。OEECに対抗して
49、4 北大西洋条約(12カ国)=北大西洋条約機構(集団安全保障機構で、対ソ軍事ブロック)
49、9 ドイツ連邦共和国(旧西独)が誕生。再軍備も
49 ドイツ民主共和国(旧東独)が誕生
55 ワルシャワ条約機構(東側の軍事ブロック)成立
こうした、ヨーロッパと東アジアで、米ソの対立関係が明瞭となる中、アメリカは「ソ連封じ込め」を世界戦略として打ち出す。この戦略において東アジアでは、日本が重要な役割を果たすことを期待された。日本はアメリカの世界戦略に組み込まれ、動かされていくことになり、憲法も又同様であった。
4,戦後憲法の成立過程の問題
① 国民投票がなかった
それは何故か?誰の責任か?帝国議会で審議、改正手続きだったから。その責任はマッカーサーにある。憲法制定議会選挙を行い、審議し国民投票という民主的手続きを踏むと、時間がかかり、極東委員会が発足し、口を出すことになる。その場合、天皇制の存続が怪しくなる。否定されるかも知れない。それはマッカーサーが描いたシナリオではなかった。彼のシナリオでは、天皇制存続は必要だった。それを確実にするためには、極東委員会が発足(2月26日)する前に憲法を変える筋道を作り、極東委員会が口を出す時間的余地をなくすために、反民主的改正手続きという方法をとったと考えられる。
つまり、天皇制存続は反民主的な手法と切り離せない関係なのである。
② 占領下で行われた(=国家主権がない状況)ので「押しつけ憲法」論の根拠に
この点は、事実である。それを自民党改憲推進派は、改憲の一つの理由にしている。
・ポツダム宣言を受け入れた。無条件降伏を受け入れたので、文句は言えない。
・GHQは、はじめ政府に憲法改正案を作るよう指示した。が当時の政府の改憲草案は、とても民主的とは言えない、明治憲法の焼き直し程度であった。これは、対日占領政策の柱の一つ、民主化を実現するものではなかった。
・天皇制存続は、当時の日本政府、支配階級の最重要事項だった。この点についての米国の世論は、天皇の戦争責任と天皇制廃止の声が圧倒的だった。さらに、1946年1月9日、極東国際軍事裁判に向けてオーストラリアが提出した戦犯リストには、天皇の名があった。オーストラリアは極東委員会で最終決定することを要求していた。このように、天皇の戦争責任問題が占領政策の国際的枠組みの中に投げ入れられ、米国の手に負えなくなる前に天皇制存続の方向性を決定づけなければならないと米国政府とマッカーサーは考えた。また、米政府は、占領政策遂行にとって、天皇訴追と廃止が悪い影響を与えることを危惧。現地の最高司令官の判断を尊重。
マッカーサーは、天皇制存続、訴追しない方針を本国政府に伝えた。
占領下でマッカーサーの政治的判断で、天皇ヒロヒトの戦争責任と天皇制存続が担保されたのである。極東委員会のヘゲモニーで占領政策が進められ、また、改憲内容に介入されたら、それは難しかっただろう。
こうした歴史の経緯を見るとき、「押しつけ憲法」という主張は、天皇制存続の根拠を危うくするものである。天皇制を擁護している自民党の上記主張は、論理的に破綻しているが、自民党はこの事を理解していない。
天皇ヒロヒトの政治責任を問わないことが、戦後日本の国家社会における官僚達や政治家の中に無責任体質をはびこらせている。
5,憲法条文上の問題
天皇制と9条~9条の平和主義と侵略戦争の最高責任者である天皇制存続の併存は、倫理的には矛盾した関係である。何故、整合性のない両者が併存することになったのか。
マッカーサーと米国政府は、天皇制存続の立場に立つと結論を出したが、一方、日本に侵略されたアジア諸国は、天皇ヒロヒトの戦争責任追求と、日本の再度の侵略戦争を強く警戒していた。彼らは、日本の侵略戦争は天皇制とは切り離せない関係として認識していたから。その認識は当然である。マッカーサーは、この矛盾した両者を並立させなければならなかった。その結果、政治行為と切り離した象徴天皇制と戦争と武力の放棄を明確にした9条を憲法に入れた。
天皇を象徴にして、政治と切り離したことは、明治憲法に比べれば大きな改善に見えるが、国民統合の役割は機能している。戦前ほどその機能は強力ではないが、自民党や右翼は政治的に利用しようとしている。また、彼らは、天皇制の権威を高め統合力をより強めようとしている。学校における「日の丸・君が代」の強制は、そのことを示している。
天皇が代替わりして、戦争責任論はヒロヒトの時より、大幅に後退しているが、戦争の責任は個人の問題もあるが、制度の問題でもある。象徴であれ、戦争責任のある天皇が君主的立場にいることは、日本の国家社会全体が、侵略戦争への謝罪の意識を希薄にしている原因である。それは、支配層にも反映されているので、アジア諸国の人々との認識のずれを生み出し、日本への批判の原因ともなっている。
6,戦後憲法の本質~砂川裁判・最高裁判決が明らかにしたもの
砂川裁判の持つ意味は、日本国憲法の本質上、決定的に重要な意味を持つので、ご存じのない人もいるかも知れないので、砂川裁判とは何かを見てみよう。
砂川裁判とは、1957年、東京都砂川町(現在立川市に編入)の米軍基地(現在は返還され、公園などになっている)に数メートル入ったデモ参加者23人が逮捕され、うち7人が起訴された事件の裁判である。1959年3月30日、東京地裁刑事第13部、伊達裁判長の判決は、「米軍駐留は憲法9条違反」と断じた。判決の要点(創元社:『治安国家崩壊』より引用)は
「①憲法第9条は、日本が戦争する権利も、戦力を持つことも禁じている。一方、日米安保条約では、日本に駐留する米軍は、日本防衛のためだけでなく、極東における平和と安全の維持のため、戦略上必要と判断したら日本国外にも出動できるとしている。その場合、日本が提供した基地は米軍の軍事行動のために使用される。その結果、日本が直接関係のない武力紛争に巻き込まれ、戦争の被害が日本に及ぶ恐れもある。
したがって、安保条約によりこのような危険をもたらす可能性を持つ米軍駐留を許した日本政府の行為は、『政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きないようにすることを決意』した日本国憲法の精神に反するのではないか。
②そうした危険性を持つ米軍の駐留は、日本政府が要請し、それをアメリカ政府が承認した結果であり、つまり日本政府の行為によるものだと言える。米軍の駐留は、日本政府の要請と、基地の提供と費用の分担などの協力があるからこそ可能なのである。
この点を考えると、米軍の駐留を許していることは、指揮権の有無、米軍の出動義務の有無にかかわらず、憲法第9条2項で禁止されている戦力の保持に該当するものと言わざるを得ない。結局、日本に駐留する米軍は憲法上その存在を許すべきではないと言える。
③刑事特別法は、正当な理由のない基地内への立ち入りに対し、1年以下の懲役又は2000円以下の罰金もしくは科料を課している。それは軽犯罪法の規定よりも特に重い。しかし、米軍の本駐留が憲法第9条第2項に違反している以上、国民に対し軽犯罪法の規定よりも特に重い刑罰をあたえる刑事特別法の規定は、どんな人でも適正な手続きによらなければ刑罰を科せられないとする憲法第31条[適正手続きの保障]に違反しており、無効だ。従って、全員無罪である」
「伊達判決」は日米両政府に大きな衝撃をあたえた。「米軍駐留は憲法違反」と言う判決は、当時全国各地の米軍基地反対闘争や安保条約改定反対運動を勢いづけ、進行中の安保条約改定協議の障害となるばかりでなく、新安保条約の成立を否定するもの。日米両政府は、この伊達判決を覆すために必死になる。安保改定時期が迫っているので、時間的余裕はなく、迅速に伊達判決をひっくり返えさなければならなかった。
日本政府と最高裁長官は、4月30日、高裁を飛び越えて最高裁で審理するという跳躍上告というウルトラ技を出す。きわめて異常。さらに、最高裁は異常な早さで判決を出す。これも、日米両政府の意向にしたがったもの。
最高裁の判決は、1959年12月16日。裁判長は最高裁長官の田中耕太郎であった。
最高裁判決:主文「原判決を破棄する。本件を東京地方裁判所に差し戻す」
判決文の最大の問題点は以下にある。
「日米安保条約は我が国の存立の基盤に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものだ。だから、その内容が違憲か合憲かの法的判断は、その条約を締結した内閣と、それを承認した国会の高度の政治的、自由裁量的判断と表裏一体をなしている。それ故、違憲か合憲かの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない。」と述べているが、次のようにも書かれている。「米軍の駐留は憲法9条、98条2項、前文に適合こそすれ、これらの条章に反して違憲無効であることが一見きわめて明白であるとは、とうてい認められない。」
「違法か合憲かの判断は、原則としてなじまない」と言いながら伊達判決に言及して「米軍の駐留は憲法9条、98条2項、前文に適合こそすれ・・・」と書いているが、ここでは憲法判断をしているではないか。これは明確に矛盾であり、論理が破綻している。この矛盾破綻は、結論ありきの政治的判決だから生じたものだ。伊達判決を覆すことが日米政府と最高裁長官との間で密約であったからである。
日本国憲法は権力を縛る力がないことが明らかになった。逆に、権力と支配階級にとっては、日本国憲法は利用する道具に過ぎない。
日本国憲法の本質の2番目は、日米安保法体系のほうが憲法体系より優位にある点である。
日本には、「憲法体系」と「安保法体系」の二つの法体系があり、併存している。これ自体が異常。
安保法体系とは、日米安保条約と、その附属協定である日米地位協定・特別法である。
そして、この「安保法体系」によって米軍は、「憲法体系」に制約されない基地運営や訓練実施や戦闘作戦への出動など軍事活動の自由という特権を保障されている。「安保法体系」に含まれる特別法は主なもので22あり、安保特別法・安保特例法と総称されている。
例えば、航空機の安全や飛行場施設や航空運送事業などに関して規定する、航空法という一般の国内法がある。それは「憲法体系」の中の法律の一つ。一方「安保法体系」に含まれる特例法の一つとして「地位協定の実施に伴う航空法特例法」が制定されている。これにより米軍は、航空法の定める規定の適用を免除されている。
その例をいくつか次に示す。
①飛行場・航空保安施設設置の許可義務。②「耐空証明」不帯用機の航空禁止 ③夜間飛行の際の灯火義務 ④飛行禁止区域の遵守 ⑤最低安全高度の遵守 ⑥巡航高度の遵守 ⑦速度制限の遵守 ⑧編隊飛行の禁止
このように航空法の適用除外があるから、米軍機は騒音公害をもたらす爆音を出しながら、最低安全高度(人口密集地では最も高い障害物の上端から300メートル、それ以外のところでは地面や建物などから150メートル)も守らずに、日本全国各地で危険な低空飛行を行っている。
ちなみに、首都東京の空には、「横田空域」という米軍専用の空域があり、日本の航空機は許可なしには飛行することが許されていないので、民間航空機は、それを避けて成田や羽田に離着陸している。
こうして米軍によって、日々日本の人々の生活と安全は脅かされている。
日本国憲法は、日本人の生活と安全を守る力を十全には保持できていない。それは、自民党・保守政治権力と米軍によって奪われた。
さらに、民有地が米軍基地の建設・拡張のために提供されるときも、米軍に有利な安保特別法がある。「地位協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」である。駐留軍用地特措法あるいは米軍用地特措法とも呼ばれる。同法には、日本政府が民有地所有者と軍用地の賃貸借契約が出来ない場合、強制使用、強制収用する手続きが定められている。同法第3条で、「駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正かつ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は収用することが出来る」
日本政府(ほとんどが保守自民党政府だが)は、これを盾に民有地を米軍のために強制的に取り上げてきた。「適正かつ合理的」と誰が判断するのか?日本政府は政治的な判断をするので、客観性がない。では裁判所か?砂川裁判の判決を見れば、裁判所も政治的であるので、客観性がない。公的な機関はどこも客観性に乏しいので、この文言は、死文化している。最終的には政府と裁判所のへりくつによる判断によるのだろう。全く主権者たる民衆をコケにしている。
砂川判決が示したものは、日本国憲法が日米安保法体系の前に無力であるという事実である。日本の国家主権は、駐留米軍によって大きく制限されている。これで独立国家と言えるのか?蛇足ながら、日本の右翼は、この現実を批判していない、これほど民族主義、国家主権が侵害されているのに。
7,戦後政治の歴史の中で、日本国憲法は保守政治・政党の道具として利用されてきた。
戦後日本の復興は、50年の朝鮮戦争による特需がきっかけとなって進んだ。同時に、この朝鮮戦争によって、東アジアにおける冷戦体制=戦後世界秩序は、明確な姿を現し、アメリカの対日方針の変化をもたらした。日本は、極東におけるソ連勢力封じ込め戦略の重要な柱として位置づけられる。アメリカはそのために再軍備と経済の発展を要求する。
世界秩序としての冷戦体制において、アメリカ勢力圏とソビエト勢力圏との直接的衝突は、朝鮮戦争とベトナム戦争とキューバ危機である。が、それぞれの勢力圏の内部での労働者民衆の叛乱・暴動・運動はしばしば起きた。
日本と現憲法は、このような世界の激動にさらされていく。憲法の試練は、朝鮮戦争が始まり、アメリカが日本に再軍備を要求したことである。そのためには9条改憲が必要とアメリカはアドバイスをした。しかし、時の日本政府は、解釈改憲で対応する。国民世論は「再軍備」賛成が53%以上だったが、国会の護憲派が3分の1を越えていたので無理と判断。時の首相吉田は、米国の再軍備要求を受け入れたが、経済再建を優先し「軽武装」方針を打ち出した。
次は、砂川裁判。
そして、ベトナム戦争もまた、憲法にとって厄災であった。ベトナム戦争で、日本にある米軍基地から、爆撃機や空母などが出かけ攻撃していたから。日本は戦争に巻き込まれた。砂川裁判の伊達判決の①が指摘したことが現実になった。米軍の軍事行動に日本が好むと好まざるとにかかわらず、巻き込まれ危険にさらされる状態になった。憲法は無力であった。
次は、沖縄返還である。沖縄は、太平洋戦争で戦場となり多くの民間の犠牲者を出した。その後も米軍が駐留し、支配していた。講和条約が成立し、日本は独立を回復したが、沖縄はアメリカの施政権下に置かれ、憲法が適用されなかった。72年、沖縄は日本に返還され、憲法が適用されることになったが、しかし、米軍基地と米軍は、日米安保条約とその関連特別法によって憲法適用外となった。そのように決めたのは、沖縄の人々の総意ではなく、日本の保守政党政府であった。それは日本全国の米軍基地も同様であったが、沖縄の犠牲は遙かに大きかった。憲法は、沖縄の人々の生活と安全を担保することが出来なかったし、現在もまだ出来ていない。
② 戦後日本の政治は、55年以降、ほとんど保守自民党が支配してきた。
自民党は、日本国憲法を「押しつけられた」と主張している。それは事実だろう。だが、彼らがそれを問題にするのはお門違いではないか。第1に、戦前の日本国家・支配階級が侵略戦争を仕掛け、あげくに連合国に負け、無条件降伏したのだから、文句を言う権利はない。文句を言う権利があるなら、それは労働者民衆である。憲法作成過程に何ら関与できなかったし、国民投票もできなったのだから。
第2には、支配階級と保守政党は国家権力を支配し、憲法に縛られることもなく、上述したようにそれを利用しながら戦後政権を長期間維持し、労働者民衆を支配してきた。
米国は、日本国憲法作成に大きな影響力を発揮したが、朝鮮戦争勃発以降、日本国憲法を重視しなくなった。再軍備を要求しそのために9条改憲を示唆した。米国にとって、冷戦体制=世界支配体制下で、米国勢力圏の結束と軍事力・経済力・政治力を強化することが、最優先事項であった。極東アジアにおけるパワーバランスにおいて、日本の果たす役割は非常に重要であった。
米国にとっては、日本国憲法より日米安全保障条約に基づく軍事基地とそれらの様々な特権のほうが重要だった。
91年、ソ連の崩壊。冷戦体制=戦後の世界秩序体制は終焉した。
新たな世界秩序は、構築できていない。米国の「一強体制」と言われたが、実態はそのようになっていない。米国の力=経済力・軍事力は相対的に低下している。
国同士の利害対立が露骨になってきた。それを、調停する力のある国はない。米国にはもはやそのような力はない。
中国の巨大化とロシアのプーチンの反米意識と言動は、世界を混乱させている。
民主主義が衰え、専制・独裁政治が拡大している。
民主主義(ブルジョアの)の衰えは、貧富の差が拡大して、中間層が没落している状況が原因の一つである。専制政治の登場と拡大は、経済的発展のいきずまりの反映。経済の発展は、製造業の中心は、発展途上国に移りつつある。特に、技術は簡単に移転する。自動車なども、今やどこの国でも製造できる。ただ、電気自動車や全自動化は、金もかかるので、簡単ではないが。
先進国においては、情報産業が大きな利潤を生み出している。
全体として、危機的状況が深刻化しつつある。出口が見えない。
こうした世界的危機状況は、戦後労働者階級が自己の階級性を確立してこなかった反映である。
戦後世界秩序に対して、そこにおける労働者階級の利害を明確にできなかった左翼の責任である。
戦後体制は、戦前戦中における階級闘争の敗北の結果形成されたものである。従って、その総括が必須であったが、それがなしえなかったからである。ここに、私たちの重要な課題がある。
このような世界史的状況を背景として、自民党の改憲攻勢が提起されている。それ故、自衛隊を名実ともに軍隊にし、世界的危機に備えると言う口実が一定程度のリアリティーをもつ。また、緊急事態条項も同様である。しかし、一方で、自民党は改憲を声高に叫んでいるが、2015年の安倍内閣の時の「安全保障関連法」は解釈改憲であった。この前段階で、安倍は内閣法制局長を集団的自衛権行使容認の人物に交代し、法案を成立させた。こうした重要法案を内閣の憲法解釈の変更だけで、成立させたやり方は、労働者民衆をコケにしたやり方で、このような連中が改憲を提起することは許せない。
改憲を提起するなら、これまでの行為を反省し現行憲法を遵守することを、宣誓してからにするべきだ。
自民党の改憲案には、日本の未来像が提示されていない。現状の世界秩序が混沌としている状況に対し、これをどう止揚しようとしているかを示さなければ、改憲はただ目先の自分たちの恣意的なプランでしかない。改憲をもてあそんでいるもので、許せない。
8、現憲法は、労働者階級にとってどのような意味があるのか?
現憲法は、支配階級にとって、押しつけられたものであるが、同時に被支配階級である私たち労働者にとっても押しつけられたものであるが、それは明治憲法に比べて遙かに民主的であったので、大いに歓迎された。それ故、現憲法の本質(=ブルジョア民主主義)を見えにくくさせた。また、それは、支配階級も利用したが労働者階級も大いに利用した。組合運動、労働運動、政治運動、その他の社会運動もかなり自由に活動できることになり、戦前のような弾圧をされることはなかった。 もちろん、それらの運動が、支配階級にとって容認できる範囲の場合という条件がついていたが、それは戦前より遙かに厳しくなかった。憲法が一定の基準を示していて歯止めの役割を果たしていたからである。
そうした、状況に私たち左翼やリベラル派は甘えていた。だが、それは罠で、現憲法はブルジョア民主主義を表現したものであり、労働者階級の思想とは相容れないという本質を有していて、現憲法を擁護することは、そのブルジョア民主主義に取り込まれるのである。
支配階級も被支配階級である労働者階級も互いに利用してきたが、支配階級たる保守政治・政党は政治権力を握り続け、より多く利用し、自分勝手に都合のいいようにそれを解釈して来た。労働者に不利な解釈運用が行われてきたので、労働者に不利な状態も多々生まれてきた。それを、労働者階級は、追求し是正させることがなかなか出来なかった。「再武装=自衛隊の存在」、「砂川裁判最高裁判決」、2015年「安全保障関連法」などが代表的な例である。
労働者階級が、現憲法の本質を理解しつつ十全に活用するためには、保守政治権力に対抗する力(労働者階級の団結)が必要であったが、その力を持つことが出来なかったし現在も持ち得ていない。それはどうしてなのか。この点に関しての基本を本文書の1~7で述べた。しかしこれだけでは、労働者の階級性を確保することは不十分である。
現在の労働者の置かれている状況と資本の有り様の現実を見ていかなければならない。
戦後、特に今日、「労働者」の有り様は多様化してきている。雇用形態、労働形態、収入の多様化をもたらしている。それは、労働者の利害の多様化をもたらし、労働者は分断され団結を難しくされている。組合の弱体化がその現実に拍車をかける。組合の弱体化は、多様化の結果でもあるが、何よりも、労働者の階級性の弱さの反映である。
一方、戦後の資本主義も有り様が変化してきている。利潤追求の多様化が進み、今日、製造業による利潤よりも、第3次産業とりわけ情報産業が大きな利潤を生み出している。この点は、アメリカが顕著である。産業構造のこうした変化が、資本主義の利潤追求の多様化をもたらし、社会の有り様も変化し、労働者や労働組合を巻き込む。
労働組合の右傾化・労使協調路線が支配的な勢力になり、組合の存在意義が大幅に減少し、組織率は低くなる一方である。反対に少人数労働組合が増える。非組合員も増え続けている。また、労働条件の悪化している職場が増え、組合の必要性が増している。しかし大組合は、御用組合化しているところが多いので、役には立たない。
この労働者、労働組合の実態は、闘いの敗北の結果である。労働者が団結することは簡単ではなくなった。だが、可能性はあるし、今日の危機を救うことが出来るのは唯一労働者の団結だけである。その団結を作り出すには、多様化し分断させられている労働者の状況を分析し、その根源的利害を明確にすることが第1に必要。その利害を代表し闘う組織を形成することである。こうした取り組みにとって、憲法が活用できるなら活用し、活用できなければ、自力で闘うことである。
9,闘いの方向性
改憲反対勢力は、主体の危機の克服を目指しつつ運動を形成する必要がある。護憲を主張することは、戦後の歴史から何も学んでいない。現憲法を支配階級は守ろうとしていないし、私たちも守らせることが出来ない。現憲法が私たちの闘いで勝ち取ったものではないからである。
現下の闘いは、憲法を巡って争われているが、この闘いは、労働者民衆がその独立した階級性・政治性をつかみ取ることで、展望を持つ。
現憲法から自己を解放しよう。それに固執していては、展望は閉ざされる。
労働者階級は分断されバラバラにされている。闘争の敗北の結果であるが、団結を作り出すためには、やはりこの間の敗北の総括が必要で、それを踏まえて労働者階級の独立した政治性を勝ち取ること。それが結集軸となる。
どこに闘いの基軸を設定するか~非正規雇用労働者、生活保護世帯、差別選別されている様々な人々。
幅広い統一戦線の形成をめざす。既存の運動と異なる観点が必要。新たな結集軸を作り出し、運動としては統一戦線を追求する。
守る闘争・運動ではなく、具体的な獲得目標をかかげて運動・闘いを形成すべき。
私たちは「労働者民衆の憲法作成」を提起する。これは、一見理解しにくいが、現憲法から自己を解放するためには、自分たちの力で、自分たち自身のための憲法草案を作成し、成立を目指すことだと確信している。
*なお、憲法改悪を阻止する上で、本文書だけでは不十分であるが、闘いの基盤を用意したと思っている。改悪反対闘争すすめていくのには、別途具体的方針が必要となる。