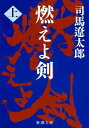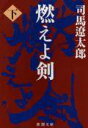読書
2014-08-11 | 読書
ゆっくり過ごす夏休みは読書をすることにした。
することにしていても、本を買い込むだけで終わることも多いのだけど、なんだか順調に読めているので、感想文です。
1冊目は、「困っているひと」
症例がほとんどないといわれる難病を発症した大学院生のお話。
闘病記ではないと、作者が冒頭に書いているとおり、病気がどうのこうのという話ではあんまりありません。
病気のことも書かれてはあるけど、そこが主ではないです。
病気になって、タイトル通り「困った」ということが、大学で難民についてフィールドワークをしていたという著者らしい視点で書かれていると思いました。
著者は病名が確定するまで、1年かかって、それもあちこちの医療機関でお手上げっていう状態で。
やっと受け入れてくれた病院でも、治療は手探りという状態で、そんな中で自立する、ということを著者は実行して行きます。
なんで、自立しないといけないかっていうと、そうでないと前に進めないから。
まだ、病気も治ってないのに、重病なのに、でも、生きるためには、前に進まないといけない。ということに、著者は治療の果てに気が付くのです。
そして今度は病気だけでなく社会制度にも戦いを挑んでいく。
難病、といってもいろいろありまして、特定疾患と呼ばれる病気は100以上あるのだそうですよ。
そのうち、公費で治療ができるのは半分くらい。
難病でも患者数が多いと対象にならなかったり、逆に患者数が少なくっても対象になってなかったり。
社会システムがそもそもおかしい、っていうのが著者の主張でもあります。
例えば、病院て、3か月以上ってなかなか入院できないんですよね。
3か月経ったら退院せなあかん、という話をうちの祖母のときにも聞いた気がする。
それは3か月経つと病院に入る診療報酬が極端に少なくなるから、らしい。
で、著者はそのために3か月目に退院、ということを余儀なくされます。しかも2回も!
そのくだりを読みながら、ふと思ったのは、私が昨年入院してたのは4か月半、だったのだけど、正確には1か月と3か月半で、それは入院して1か月目に薬が効かなくて、悪性腫瘍の疑いがぬぐいきれないからと、PET検査をするために1日だけ退院したからで、医大にはPET検査の設備がなくって、社会保険か何かの関係で、同時に2つの病院にはかかれないらしくって、でもPETは自費だったのだけど。
形だけっていうわけにはいかなくて、ほんとに荷物を全部持って帰らされて、で、翌日検査を終えて(医大からすぐの別の病院だったから)当日再入院したのでした。
このときはいろいろ憤慨してて、しかしこの期間を差し引いても3か月以上病院にいたわけで、そこはそれ。退院間近といえば間近だったのだけど、良心的な措置だったのかなぁと思い至りました。そおっと感謝しとこう。
と、自分の闘病生活と重ね合わせつつ読みました。
特にふつうに生活できないってことがどれだけ大変かってことを私も味わってしまったので、困っているひとというのは他人事ではなくて身近な話なのでした。
明るく軽いタッチで描かれていますが、しっかりちゃんとずっしりなテーマです。
2冊目は、月と6ペンス。
40(奇しくも今の私と同じ歳!!)になって、それまでの職業を辞め、妻子を捨てて画家になった男とそれに係わった小説家もろもろのお話です。
語り手の小説家は小説家としての性分から、この男が気になってしまう。
死後、世界的に評価されることになったという、画家という職業にしては珍しくないストーリーを、彼に係わった人々を交えながらその生涯を語っていくというもの。
途中、実在する画家の話なのかと思いましたが、ゴーギャンにインスピレーションを得たというだけで、フィクションとのことでした。
でも、タヒチが出てきたあたりから、ゴーギャンだ、と思い、ゴーギャンの絵を思い浮かべながら読み進めた。
フィクションなんだけど、ゴーギャンも同じ気持ちだったかもしれないと思うとゴーギャンの絵が見たいと思ってしまって、いつか見に行きたいなと思いました。
『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』
することにしていても、本を買い込むだけで終わることも多いのだけど、なんだか順調に読めているので、感想文です。
1冊目は、「困っているひと」
症例がほとんどないといわれる難病を発症した大学院生のお話。
闘病記ではないと、作者が冒頭に書いているとおり、病気がどうのこうのという話ではあんまりありません。
病気のことも書かれてはあるけど、そこが主ではないです。
病気になって、タイトル通り「困った」ということが、大学で難民についてフィールドワークをしていたという著者らしい視点で書かれていると思いました。
著者は病名が確定するまで、1年かかって、それもあちこちの医療機関でお手上げっていう状態で。
やっと受け入れてくれた病院でも、治療は手探りという状態で、そんな中で自立する、ということを著者は実行して行きます。
なんで、自立しないといけないかっていうと、そうでないと前に進めないから。
まだ、病気も治ってないのに、重病なのに、でも、生きるためには、前に進まないといけない。ということに、著者は治療の果てに気が付くのです。
そして今度は病気だけでなく社会制度にも戦いを挑んでいく。
難病、といってもいろいろありまして、特定疾患と呼ばれる病気は100以上あるのだそうですよ。
そのうち、公費で治療ができるのは半分くらい。
難病でも患者数が多いと対象にならなかったり、逆に患者数が少なくっても対象になってなかったり。
社会システムがそもそもおかしい、っていうのが著者の主張でもあります。
例えば、病院て、3か月以上ってなかなか入院できないんですよね。
3か月経ったら退院せなあかん、という話をうちの祖母のときにも聞いた気がする。
それは3か月経つと病院に入る診療報酬が極端に少なくなるから、らしい。
で、著者はそのために3か月目に退院、ということを余儀なくされます。しかも2回も!
そのくだりを読みながら、ふと思ったのは、私が昨年入院してたのは4か月半、だったのだけど、正確には1か月と3か月半で、それは入院して1か月目に薬が効かなくて、悪性腫瘍の疑いがぬぐいきれないからと、PET検査をするために1日だけ退院したからで、医大にはPET検査の設備がなくって、社会保険か何かの関係で、同時に2つの病院にはかかれないらしくって、でもPETは自費だったのだけど。
形だけっていうわけにはいかなくて、ほんとに荷物を全部持って帰らされて、で、翌日検査を終えて(医大からすぐの別の病院だったから)当日再入院したのでした。
このときはいろいろ憤慨してて、しかしこの期間を差し引いても3か月以上病院にいたわけで、そこはそれ。退院間近といえば間近だったのだけど、良心的な措置だったのかなぁと思い至りました。そおっと感謝しとこう。
と、自分の闘病生活と重ね合わせつつ読みました。
特にふつうに生活できないってことがどれだけ大変かってことを私も味わってしまったので、困っているひとというのは他人事ではなくて身近な話なのでした。
明るく軽いタッチで描かれていますが、しっかりちゃんとずっしりなテーマです。
2冊目は、月と6ペンス。
40(奇しくも今の私と同じ歳!!)になって、それまでの職業を辞め、妻子を捨てて画家になった男とそれに係わった小説家もろもろのお話です。
語り手の小説家は小説家としての性分から、この男が気になってしまう。
死後、世界的に評価されることになったという、画家という職業にしては珍しくないストーリーを、彼に係わった人々を交えながらその生涯を語っていくというもの。
途中、実在する画家の話なのかと思いましたが、ゴーギャンにインスピレーションを得たというだけで、フィクションとのことでした。
でも、タヒチが出てきたあたりから、ゴーギャンだ、と思い、ゴーギャンの絵を思い浮かべながら読み進めた。
フィクションなんだけど、ゴーギャンも同じ気持ちだったかもしれないと思うとゴーギャンの絵が見たいと思ってしまって、いつか見に行きたいなと思いました。
『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』