久々のアップです。もうバタバタしてタテコンでいたものですから
全然時間がさけませんでした。
前回「千早振る」で狂歌が出て来ましたので、あれからずっと何か
面白い狂歌でもないかと探していたのですが、狂歌狂詩の天才と
いえばやはりこの人以外にはなかろうと思います。
江戸時代に狂歌師として名をはせた太田南畝です。
このひとは江戸の生まれで父親が御徒職についていたため本人も
そのあとを継いでいますが、身分的には一番低い侍といったところ
でしょうか。そのかわり暇な職業で時間もたっぷりありましたから
人生の前半を遊び抜いた狂歌師として著名な存在でした。
ただし幼いころより勉学につぐ勉学で知性も教養もかなりのレベルの
ひとでしたので、松平定信の寛政の改革により新たに創られた学問所
ではトップの成績で卒業するほどでした。
後にはこの優秀さがものを言い役人として大阪や長崎へ転勤したり
しています。人生の前半を狂歌で遊び後半は真面目な役人生活を送
っています。長崎勤務のときは、世界一周をして帰国した仙台の漂
流民を乗せたロシア船のレザノフにも船上で面会をしています。
このとき南畝は初めてコーヒーを飲んだらしく、苦くて飲むもんじ
ゃない、という感想を残しています。
ともあれこの南畝という人は大変筆まめで、やたらに書きまくり
メモ程度のものから日記、紀行記、漢文集、狂歌集と本当にいろ
いろと書き残しています。今手元にあるものは有朋堂の太田南畝集
という小本で大正7年の印刷です。東京市神田区錦町の住所が
印刷所となっています。
では,この中から狂歌をいくつかご紹介いたします。
百人一首のパロディものですよ。
いかほどの洗濯なればかぐ山で衣ほすてふ持統天皇 持統天皇
このたびはぬさも取敢えず手向山まだその上にさい銭もなし 菅家
山里は冬ぞさびしさまさりけるやはり市中がにぎやかでよい 源宗干朝臣
ひさかたの光のどけき春の日に紀の友則がひるね一時 紀友則
徳利はよこにこけしに豆腐汁あまりてなどか酒のこひしき 参議等
またしてもじじとばばとのくりごとに昔は物を思はざりけり 中納言敦忠
八重むぐら茂れる宿のさびしさに恵慶法師のあくび百遍 恵慶法師
瀧の音は絶えて久しくなりぬるといふはいかなる旱魃のとし 大納言公任
大江山いく野のみちのとほければ酒天童子のいびききこえず 小式部内侍
うらみ侘びほさぬ袖だにあるものを此四五日は雨の日ぐらし 相模
眼と口と耳と眉毛のなかりせばはなよりほかに知る人もなし 前大僧正行尊
友もなく酒をもなしに眺めなばいやになるべき夜半の月かな 三條院
何ゆえか西行ほどの強勇が月の影にてしほしほとなく 西行法師
きりぎりすなくや霜夜のさむしろに後京極殿寝たり起きたり 後京極摂政前太政大臣
花さそふあらしの庭の雪やらでふりゆくものは牛のきんたま 入道前太政大臣
とまあ、南畝の手にかかるとあの百人一首もハチャメチャであります
。思わずクスクスと笑ってしまい良くもまあこんなに出来るものだと
感心させられます。
狂歌はもともと和歌の下地が要求されるもので相当の教養がないと
できません。シャレのセンスもないとだめですね。
順次また取り上げていきますから今回はこれにておしまい。
全然時間がさけませんでした。
前回「千早振る」で狂歌が出て来ましたので、あれからずっと何か
面白い狂歌でもないかと探していたのですが、狂歌狂詩の天才と
いえばやはりこの人以外にはなかろうと思います。
江戸時代に狂歌師として名をはせた太田南畝です。
このひとは江戸の生まれで父親が御徒職についていたため本人も
そのあとを継いでいますが、身分的には一番低い侍といったところ
でしょうか。そのかわり暇な職業で時間もたっぷりありましたから
人生の前半を遊び抜いた狂歌師として著名な存在でした。
ただし幼いころより勉学につぐ勉学で知性も教養もかなりのレベルの
ひとでしたので、松平定信の寛政の改革により新たに創られた学問所
ではトップの成績で卒業するほどでした。
後にはこの優秀さがものを言い役人として大阪や長崎へ転勤したり
しています。人生の前半を狂歌で遊び後半は真面目な役人生活を送
っています。長崎勤務のときは、世界一周をして帰国した仙台の漂
流民を乗せたロシア船のレザノフにも船上で面会をしています。
このとき南畝は初めてコーヒーを飲んだらしく、苦くて飲むもんじ
ゃない、という感想を残しています。
ともあれこの南畝という人は大変筆まめで、やたらに書きまくり
メモ程度のものから日記、紀行記、漢文集、狂歌集と本当にいろ
いろと書き残しています。今手元にあるものは有朋堂の太田南畝集
という小本で大正7年の印刷です。東京市神田区錦町の住所が
印刷所となっています。
では,この中から狂歌をいくつかご紹介いたします。
百人一首のパロディものですよ。
いかほどの洗濯なればかぐ山で衣ほすてふ持統天皇 持統天皇
このたびはぬさも取敢えず手向山まだその上にさい銭もなし 菅家
山里は冬ぞさびしさまさりけるやはり市中がにぎやかでよい 源宗干朝臣
ひさかたの光のどけき春の日に紀の友則がひるね一時 紀友則
徳利はよこにこけしに豆腐汁あまりてなどか酒のこひしき 参議等
またしてもじじとばばとのくりごとに昔は物を思はざりけり 中納言敦忠
八重むぐら茂れる宿のさびしさに恵慶法師のあくび百遍 恵慶法師
瀧の音は絶えて久しくなりぬるといふはいかなる旱魃のとし 大納言公任
大江山いく野のみちのとほければ酒天童子のいびききこえず 小式部内侍
うらみ侘びほさぬ袖だにあるものを此四五日は雨の日ぐらし 相模
眼と口と耳と眉毛のなかりせばはなよりほかに知る人もなし 前大僧正行尊
友もなく酒をもなしに眺めなばいやになるべき夜半の月かな 三條院
何ゆえか西行ほどの強勇が月の影にてしほしほとなく 西行法師
きりぎりすなくや霜夜のさむしろに後京極殿寝たり起きたり 後京極摂政前太政大臣
花さそふあらしの庭の雪やらでふりゆくものは牛のきんたま 入道前太政大臣
とまあ、南畝の手にかかるとあの百人一首もハチャメチャであります
。思わずクスクスと笑ってしまい良くもまあこんなに出来るものだと
感心させられます。
狂歌はもともと和歌の下地が要求されるもので相当の教養がないと
できません。シャレのセンスもないとだめですね。
順次また取り上げていきますから今回はこれにておしまい。











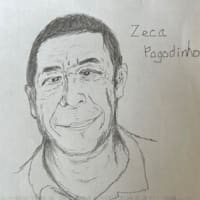
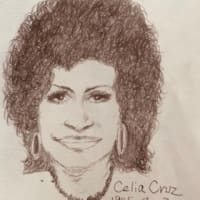












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます