16~20代の頃の記憶といえば、鮮烈であったはずなのに...
17編の短編集、すべてよんだのに、思い出せないものもいくつか...
まあ、老化現象を嘆くのは、おいといて
改めて、感じたことを綴ってみる。
・ねじまき鳥と火曜日の女たち
マルボロを吸う、16歳の女の子
お久しぶりという感じでした。よく覚えています。
ねじまき鳥クロニクルの原風景を再確認する。
・眠り
眠らずにいれるということ。
トリップハイ
村上文学の特徴ですが、登場する小説、音楽を無性に
読みたくなり、聴きたくなります。
なので私は、『アンナ・カレーニナ』を読んでいる最中
(もなかではないです...)です。
・納屋を焼く
これを以前読んだとき、16歳の、足りないおつむで
『納屋を焼く』ということは
どういうことなのか一生懸命かんがえた気がする。
今回、なんとなく感じたのは、『メモリー・クリア』
頭の中に、いっぱいになった、くだらない情報を流し去る。
まあ、こんなことを考えるのは私くらいでしょうか?
・窓
主人公が大学生の頃ペン・ソサイエティーという
文章の添削・会員へのアドバイスの手紙を書くというアルバイトを
していたという話。
この短編集のなかで、今の私には一番心に残る話でした。
そのフレーズです。
会員たちは実にいろいろな手紙を僕あてに送ってくれた 。....(中略)
彼女たちの伝えるそれらのメッセージは僕には、二十一歳か二十二歳の
大学生にとっては、奇妙に非現実的なものに感じられた。
それらはおおかたの場合リアリティーというものを欠いて
いたように思えたし、
ある場合には全面的に無意味なことであるようにも思えた。
でも僕に人生の経験が欠けているということだけが
その原因ではなかった。
今になってみればわかるのだけど、ほとんどの場合、
物事のリアリティーというのは伝えるべきではないのだ。
それは作るべきものなのだ。
そして意味というものはそのから生まれるものなもだ。.....
この作家と同じ、時を生き、そして彼の新刊を自分の言語で
そのまま読むことができることを
感謝しています。
イスラエルでのスピーチは心を打つものでした。
でも真に心をうつフレーズは作品のなかにあると
感じています。










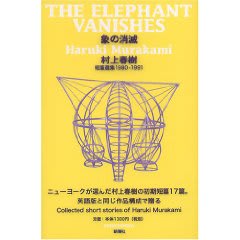










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます