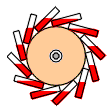
私は物理の理解力は恐らく小学校か中学校レベルで止まっている。そのおかげで子供のような夢のようなことを考えることがある。例えばそのひとつが永久機関で、未だに実現可能ではないかと思っている。
日常会話で永久機関の話題を取り上げることはほとんどないが、その原理や試みについて調べてみよう。
永久機関
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E4%B9%85%E6%A9%9F%E9%96%A2
永久機関(Perpetual motion)とは外部からエネルギーを受け取ることなく、仕事を行い続ける装置である。
古くは単純に外部からエネルギーを供給しなくても永久に運動を続ける装置と考えられていた。しかし、慣性の法則によれば外力が働かない限り物体は等速直線運動を続けるし、惑星は角運動量保存の法則により自転を続ける。そのため、単純に運動を続けるのではなく、外に対して仕事を行い続ける装置が永久機関と呼ばれる。
これが実現すれば石炭も石油も不要となり、エネルギー問題など発生しない。18世紀の科学者、技術者はこれを実現すべく精力的に研究を行った。しかし、18世紀の終わりには純粋力学的な方法では実現不可能だということが明らかになり、さらに19世紀には熱を使った方法でも不可能であることが明らかになった。永久機関は実現できなかったが、これにより熱力学と呼ばれる物理学の1分野が大いに発展した。
第一種永久機関
第一種永久機関とは、外部から何も受け取ることなく、仕事を外部に取り出すことができる機関である。これは熱力学第一法則(エネルギー保存の法則と等価)に反した存在である。機関が仕事をするためには「外部から熱を受け取る」、「外部から仕事をなされる」のどちらかが必要で、それを望む形の仕事に変換するしかないが、第一種永久機関は何もエネルギー源の無いところからひとりでにエネルギーを発生させている。これは、エネルギーの増減が内部エネルギーの変化であるという、熱力学第一法則に第一種永久機関が逆らっていることを意味している。
科学者、技術者の精力的な研究にも関わらず、第一種永久機関が作り出されることはなかった。その結果、熱力学第一法則が定式化されるに至った。
第二種永久機関
熱力学第一法則(エネルギー保存の法則)を破らずに実現しようとしたのが第二種永久機関である。 仕事を外部に取り出すとエネルギーを外部から供給する必要ができてしまう。 そこで仕事を行う部分を装置内に組み込んでしまい、ある熱源から熱エネルギーを取り出しこれを仕事に変換し、仕事によって発生した熱を熱源に回収する装置が考えられた。 このような装置があればエネルギー保存の法則を破らない永久機関となる。
仮に第二種永久機関が可能としても、定義よりエネルギー保存は破らないため、その機械自体の持っているエネルギーを外部に取り出してしまえば、いずれその機械は停止する。本機械は「熱効率100%の熱機関」であって、その機械自体をエネルギー源として使用できるわけではない。
第二種永久機関を肯定する実験結果は得られておらず、実現は否定されている。第二種永久機関の否定により、「熱は温度の高い方から低い方に流れる」という熱力学第二法則(エントロピー増大の原理)が確立した。これによって総ての熱機関において最大熱効率が1.0(100%)以上になることは決してないため、仕事によって発生した総ての熱を熱源に回収する事は不可能であるということになり、第二種永久機関の矛盾までもが確立されるに至った。前述の海水の熱により推進する仮想的な船の例では、「加速時に船の近傍の海水が周りより冷たくなり、減速時に船の近傍の海水が周りより熱くなる」という、現実には起こりえない事態が発生する(無論、これは熱力学第二法則に反する現象である)。
これまでに提案された永久機関の詳細は以下のURLで紹介されている。
永久機関の話
http://www.e-one.uec.ac.jp/~tito/jugyou/eikyu/eikyu.htm
このような説明を見てもいまひとつ腹に落ちないところが悲しいところだが、人類が長きにわたって永久機関に挑み、その否定的発展が進んだことがよくわかる。やはり人類にとって永久の夢であると言えよう。何といっても永久機関はエネルギー問題を解決できる鍵なのだ。
であれば、私自身も「いつかどこかで永久機関は達成できる」と思い続けることにしよう。大人が子供心を失わないほうが世の中は楽しいはずだ。
| Trackback ( 0 )
|
|