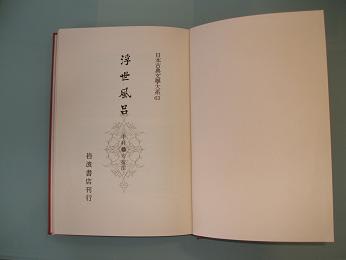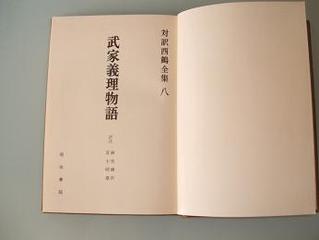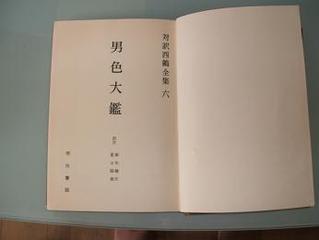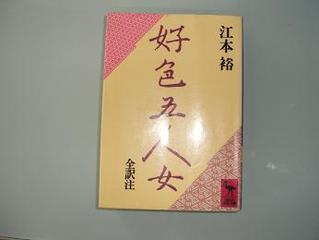『黄表紙・洒落本集』水野 稔校注 日本古典文学大系59 岩波書店
金々先生栄花夢 恋川春町 画作
金むらや金兵衛がまどろみける夢 いづみやの七珍万宝ことごとく譲り受け放蕩三昧零落
「人間一生のたのしみも、わづかにあわ餅一臼の内のごとし」補注に邯鄲の「栄花のほどは五十年、さて夢の間は粟飯の、一炊の間なり」がある。
高慢斉行脚日記 恋川春町 画作
高慢斉万屋(ばんおく)が俳諧の修行に出ている間、高弟法外とその弟子にきんきん天狗が乗りうつり、風流自堕落遊里勝手も万屋の才覚で目覚めけり
見徳一炊夢(みるがとくいっすいのゆめ) 朋誠堂喜三二
栄華屋夢次郎という邯鄲の枕をかして夢商売をする者の所へ、百万両分限蘆の屋清右エ門のせがれ清太郎が五十年の栄華の夢をみんと、千両盗み出してやってきた。丸山では唐言あそびにはまった。
御存商売物(ごぞんじのしょうばいもの) 北尾政演 画作
八文字屋の読本が「どうぞして、青本その外の地本にけちをつけん」と赤本、黒本の草草紙を引き入れ策略を練るが、唐詩選、源氏物語に意見され・・・・
大悲千禄本(だいひのせんろくほん) 芝 全交作 北尾政演 画
面の皮屋千兵衛不景気のあまり千手観音の手を切取り一本一両で貸出す。手を失った平忠度、茨城童子、手くだのしらない女郎、無筆もの等々。天明三、四年頃の観音開帳による莫大な儲けと不景気を素材
莫切自根金生木(きるなのねからかねのなるき) 唐来参和 作 千代女 画
こった題名。万万先生七珍万宝蔵に満ちて万事上手くいくのはよろしくないと、なんとか金蔵を減らすべく、福は外鬼は内と無担保金貸し、傾城買い、博打と何をやっても一行に減らぬ。泥棒の入り安いようにしておいたら、泥棒は盗品まで置いていく始末
江戸生艶気樺焼(えどうまれうわさのかばやき) 山東京伝 作 北尾政演 画
うぬぼれの代名詞ともなった艶二郎登場 天明五年刊 京伝代表作の一つ。うそ心中で浮名を流したいばっかりの道行が本気ととられ丸裸
文武二道万石通 朋誠堂喜三二 作 喜多川行麿 画
定信の文武奨励策を背景に「ぬらくら」武士判別のため箱根七湯めぐり。”うがち”ねらいも「穴をくわしくさがしたがれど、見物にはいちいちわかりかねます。」と微妙。
孔子縞干時藍染(こうしじまときにあいぞめ) 山東京伝 作 北尾政演 画
寛政元年刊寛政改革最盛時下の未来聖代の物語。有徳の町人は金銀をほとこすのが最上の仁徳とばかり施すも「酢のこんにゃくのといって」受取ってもらえず。追いはぎは「ゆききの人をまちうけ、とっつかまへて、おのれは真っ裸になり、衣服、大小、金銀をくくしつけてにげる。」折角入込の湯屋(混浴)を造っても誰も入らない。(寛政三年 入込湯停止令)。あげく天は空より金をふらせ給う。
心学早染クサ 山東京伝 作 北尾政美 画
律儀者の理太郎の皮肉へなんとか入らんという悪魂は、理太郎がうたたねをしたすきに善魂をしばりあげついにその皮肉に入ることに成功した***
敵討義女英(かたきうちぎじょのはなぶさ) 南杣笑楚満人 作 歌川豊国 画
将棋のいざこざから口論となり双方の親がなだめ一旦はおさまったようにみえたが、子どうしは密かに決闘一人は斬られついに敵討ちとなる。洒落もうがちも笑いも全くみられない反黄表紙的作品と評者。読本的で合巻形態にすすむ過程を示すものという。
以上黄表紙編
遊子方言 田舎老人多田爺(・・・ただのじじい)作
江戸洒落本の定型を確立した傑作との評だが、今一つ面白味つかめず。
辰巳之薗 夢中散人寝言先生
岡場所深川の情景の夢描写 「問ひませう。」の言葉遊び。化けるは何かで「茶釜は、やかん。息子は、とつざま。かぼちゃは、とうなす。娘は、かかさん。」とにぎやか。これが遊里の遊びとかや。
道中粋語録 山手馬鹿人
作者は大田南畝。軽井茶話の副題があるように軽井沢の湯屋情景。ぼたもち好きの遊女が「信濃者とつて大喰するやうにいはっしゃりますけれど、・・・このくらいのぼたもちだら、17、8もくへば沢山だもし。」だそうな。「わしら・・・床さはいっちゃ勤めとやらおっぱなれて女夫逢い(めうとあひ)だもし。・・そんなら帯をとこかいな・・帯もふんどしもおっ取って、股ぐら割込みなさろ。それからはあ、わしがえへようにすべえさ。・・これでよいかいな・・もっと引付けなさろ。それよかんべへが。」堪忍信濃の善光寺。
卯地臭意 鐘木庵主人
両国橋での夜鷹と客の掛け合い。夜鷹には亭主がいて二人でお仕事。
通言 総マガキ 山東京伝
艶二郎、わるい志庵、きたり喜之助の三馬鹿トリオにその他の客がからみストーリーより部分の描写がこまやか。古典引用、うがちで京伝ものでも難解。
かつて万象亭(まんぞうてい)が京伝の瑣末とも思える人物衣装描写を「写実の過ぎたるものの低きにおちた」かの如く難じたことがあるらしい。石川はそれは通客の資格をもって京伝の世界に入るための「入国査証」のようなものであり、万象亭がどう語ろうがそれで京伝のいる世界はくずれないと弁じている。『江戸文学掌記』 石川淳 講談社文芸文庫
傾城買四十八手 山東京伝
京伝洒落本中最高傑作とされたもの。しっぽりとした手、やすひ手、身ぬかれた手等々それぞれに挿話があるが、夫婦の約束のある男女の交情を描いた”真の手”がとりあえず作者の心境の投影か。「傾城に真があって、運のつき」寛政二年刊(京伝は遊女と二度結婚したとか)
錦之裏 山東京伝
京伝手鎖五十日実刑となった三部作の一つ。青楼昼之世界との副題付き。勘当された男と遊女夕霧が目出度く結婚の運びとなるハッピーエンド物語のどこが幕府の癇に触れたか。淋病の薬の成分の一つに「女陰毛三すじ黒焼き」とやったのがまずかった?
傾城買二筋道 梅暮里谷峨
前段「夏の床」はそっぺいのなき二十四、五歳のいろ男だが半か通の五郎、相方は二十一、二美人の須磨衣。指切り髪切りで遊女の心がわかるというのは昔の事よ、と通ぶってみたが結局ふられた。「冬の床」は不男文理と遊女一重(ひとえ)の人情話である。
以上洒落本編
追加
時代世話二挺鼓 山東京伝 歌麿門人 行麿 画 日本古典文学全集 小学館
平将門を平貞盛、藤原秀郷連合軍が征伐するという故事をふまえ、なます造りや、七変化、文字の早書、やがら鉦の早打ちなどの早業競争でこらしめる。将門には影武者六人がおり、田沼一派と田沼家紋、七曜星が飛び交い、田沼の失脚を婉曲に暗示する、うがちの妙。