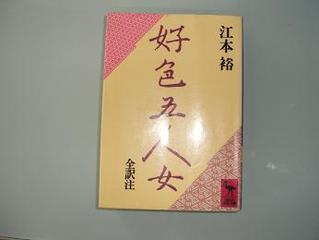
『好色五人女』 井原西鶴 江本裕 全訳注 講談社学術文庫
お夏清十郎、樽やおせん、おさん茂兵衛、八百屋お七、おまん源五兵衛と五つの実在事件をもとにした西鶴のモデル小説である。 しかしおまん事件のように真相のはっきりしないものや、樽やおせん事件のようにかなり脚色されているものもあり(本書解説)西鶴が事件にヒントを得て創作したものと考えるのが無難だろう。
おさん茂兵衛話のように、からかい半分で身代わりになり身を許してしまいそのまま不義にのめりこもうと決意する女心も、ありかなとは思うが、放火で処刑されたお七の死を知った吉三郎が「兄分の人帰られての首尾、身のたつべきにあらず。」と念友を気にするのもありかよ、 という感じだ。
尚本書刊行の前年貞享2年に『西鶴諸国はなし』が出ており、その巻4の2に本書のテーマにつながる話の指摘がある(474頁)。 これは大名の姪御と下級武士の駆落ち事件であり、発覚後男は処刑、女も座敷牢で自害を迫られるが独身であるから不義ではないと断固拒否仏門に入るというもの。 結末の「我すこしも不義にはあらず。」の一言が閃光を放つが「夫ある女の・・・死別れて後夫を求むるこそ、不義とは申すべし。・・・」に死別でも再婚を許さぬ当時の理不尽さがうかがえる。そのような時代であった。
お夏清十郎、樽やおせん、おさん茂兵衛、八百屋お七、おまん源五兵衛と五つの実在事件をもとにした西鶴のモデル小説である。 しかしおまん事件のように真相のはっきりしないものや、樽やおせん事件のようにかなり脚色されているものもあり(本書解説)西鶴が事件にヒントを得て創作したものと考えるのが無難だろう。
おさん茂兵衛話のように、からかい半分で身代わりになり身を許してしまいそのまま不義にのめりこもうと決意する女心も、ありかなとは思うが、放火で処刑されたお七の死を知った吉三郎が「兄分の人帰られての首尾、身のたつべきにあらず。」と念友を気にするのもありかよ、 という感じだ。
尚本書刊行の前年貞享2年に『西鶴諸国はなし』が出ており、その巻4の2に本書のテーマにつながる話の指摘がある(474頁)。 これは大名の姪御と下級武士の駆落ち事件であり、発覚後男は処刑、女も座敷牢で自害を迫られるが独身であるから不義ではないと断固拒否仏門に入るというもの。 結末の「我すこしも不義にはあらず。」の一言が閃光を放つが「夫ある女の・・・死別れて後夫を求むるこそ、不義とは申すべし。・・・」に死別でも再婚を許さぬ当時の理不尽さがうかがえる。そのような時代であった。



















