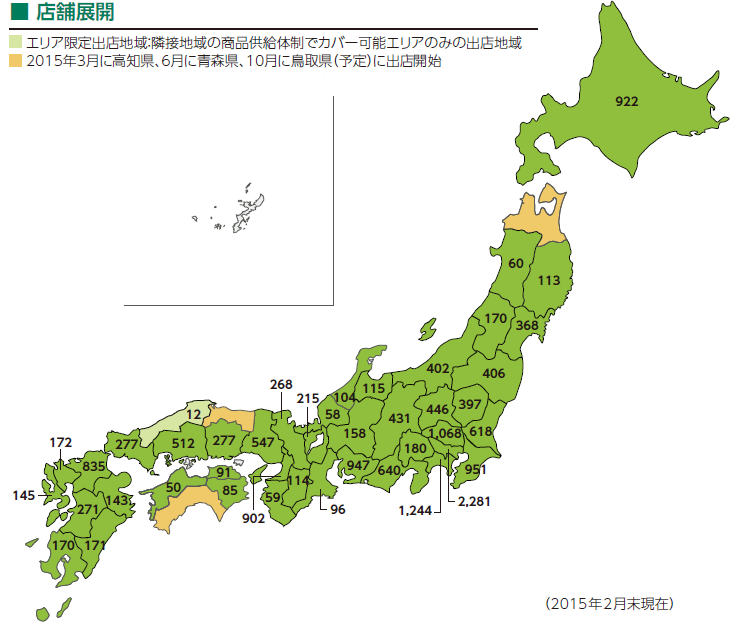イノベーションの和訳は何か。
経営学などでしばしば用いられる、「イノベーション」や「パラダイム」、「プラットフォーム」といった英語の和訳するよりも、そのままで横文字で使われることが多い。
シュンペーターによれば、イノベーションとは「新結合」であるとされる。あるいは、中国では、イノベーションは「創新」と訳されるという。
1.技術革新という和訳の起源
イノベーションを「技術革新」と訳したのは、昭和31年(1956 年)の経済企画庁による年次経済報告(「経済白書」とも言う。)とされる。
昭和31年(1956 年)の年次経済報告は、「もはや『戦後』ではない」という言葉でも有名である。
この経済白書の中の一節「技術革新と世界景気」において、次のように書かれている。
「投資活動の原動力となる技術の進歩とは原子力の平和的利用とオートメイションによって代表される技術革新(イノベーション)である。技術の革新によって景気の長期的上昇の趨勢がもたらされるということは、既に歴史的な先例がある。」[1]
高度経済成長の時代にある日本において、イノベーションの和訳として「技術革新」というイメージはしっくりしたのかもしれない。しかし、イノベーションとは、技術革新だけを指すものではない。何か古いものと新しいものが結びつくこと、あるいは新しいもの同士が結びつくことによるイノベーション、すなわち「新結合」という考え方がある。
2.新結合(シュンペーター)
シュンペーターは、新結合の要素として、
(1) 新しい財貨
(2) 新しい生産方式
(3) 新しい販路の開拓
(4) 原料あるいは半製品の新しい供給源の獲得
(5) 新しい組織の実現
を挙げている[2]。
このように、技術革新のみならず、工程の革新やビジネスモデルの革新といった新しさもまた、イノベーションとしての現れと言えるのである。組織の変革や制度の変革などによるイノベーションもまた、ありうることである。
(2015年6月12日:記事更新)
===(参考文献)===
[1] 年次経済報告(昭和31年(1956年)「技術革新と世界景気」)
http://www5.cao.go.jp/keizai3/keizaiwp/wp-je56/wp-je56-010303.html
[2] Schumpeter, J. A.(1926) Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 2(シュンペーター, J. A., 塩野谷祐一, 中山伊知郎, 東畑精一訳(1977)『経済発展の理論:企業者利潤・資本・信用・利子および景気の回転に関する一研究(上)』,岩波書店(岩波文庫)183頁)
経営学などでしばしば用いられる、「イノベーション」や「パラダイム」、「プラットフォーム」といった英語の和訳するよりも、そのままで横文字で使われることが多い。
シュンペーターによれば、イノベーションとは「新結合」であるとされる。あるいは、中国では、イノベーションは「創新」と訳されるという。
1.技術革新という和訳の起源
イノベーションを「技術革新」と訳したのは、昭和31年(1956 年)の経済企画庁による年次経済報告(「経済白書」とも言う。)とされる。
昭和31年(1956 年)の年次経済報告は、「もはや『戦後』ではない」という言葉でも有名である。
この経済白書の中の一節「技術革新と世界景気」において、次のように書かれている。
「投資活動の原動力となる技術の進歩とは原子力の平和的利用とオートメイションによって代表される技術革新(イノベーション)である。技術の革新によって景気の長期的上昇の趨勢がもたらされるということは、既に歴史的な先例がある。」[1]
高度経済成長の時代にある日本において、イノベーションの和訳として「技術革新」というイメージはしっくりしたのかもしれない。しかし、イノベーションとは、技術革新だけを指すものではない。何か古いものと新しいものが結びつくこと、あるいは新しいもの同士が結びつくことによるイノベーション、すなわち「新結合」という考え方がある。
2.新結合(シュンペーター)
シュンペーターは、新結合の要素として、
(1) 新しい財貨
(2) 新しい生産方式
(3) 新しい販路の開拓
(4) 原料あるいは半製品の新しい供給源の獲得
(5) 新しい組織の実現
を挙げている[2]。
このように、技術革新のみならず、工程の革新やビジネスモデルの革新といった新しさもまた、イノベーションとしての現れと言えるのである。組織の変革や制度の変革などによるイノベーションもまた、ありうることである。
(2015年6月12日:記事更新)
===(参考文献)===
[1] 年次経済報告(昭和31年(1956年)「技術革新と世界景気」)
http://www5.cao.go.jp/keizai3/keizaiwp/wp-je56/wp-je56-010303.html
[2] Schumpeter, J. A.(1926) Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 2(シュンペーター, J. A., 塩野谷祐一, 中山伊知郎, 東畑精一訳(1977)『経済発展の理論:企業者利潤・資本・信用・利子および景気の回転に関する一研究(上)』,岩波書店(岩波文庫)183頁)