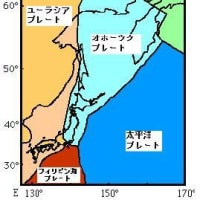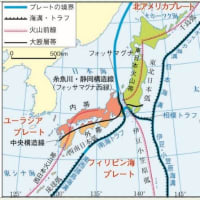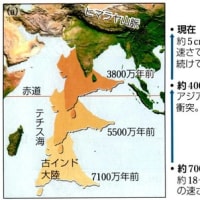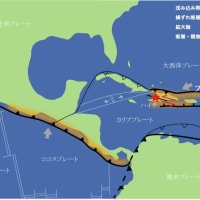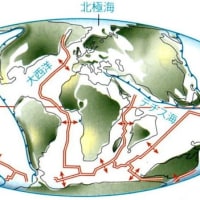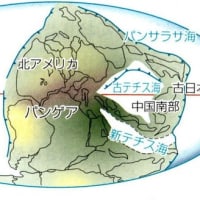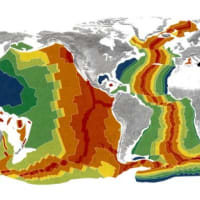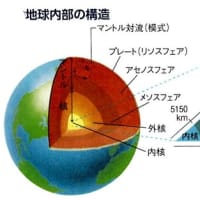日本の食料自給率が39%とか40%とか、日本の農業はまるで絶滅寸前の古典的産業のようにいわれる。
下図は2020年の食料自給率である。左図はカロリーベースの総合自給率39%である。右図は生産額ベース総合食料自給率では69%である。
食料自給率39%と、日本農業危機的状況といわれるのは、カロリーベース総合食料自給率の方である。

(クリックすると拡大)
金額、要するに食料として買った分が生産額ベース食料自給率である。ほぼ70%である。米を食べ、輸入肉と小麦(パン)の食べる量を減らせば、自給率は90%になる。食料自給の危機は、心配するほどのものではない。
しかし、この金額ベースの食料をカロリーベースで計算すると、自給率は40%以下の危機的状況になる。40%以下になった理由として、政策担当者の意図的操作を想像させるような、おかしな点が3つある。
その1
畜産物のカロリーベース自給率が低いこと、つまり輸入肉類の輸入依存が高いことである。これは下左図の追加図にあるように、日本国内で飼育されている家畜が、輸入飼料を食べると輸入畜産物として扱われるからである。
家畜・畜産物・肉類の国内取引はすべて国産であっても、牛・豚・鶏などが食べているのが輸入飼料なので、輸入畜産物となる。取引段階では国産肉が、食卓に並ぶと、輸入肉になる、という計算である。
世界各国から日本には畜産物の輸入圧力が強い。日本の畜産農家保護のため、日本政府が現在でも畜産物の輸入割合が多いことを示すための、意図的数字操作との批判がある。
その2
カロリーの高い食品を多めに入れている。つまり、サラダ油・天ぷら油はカロリーが非常に高く、天ぷら・天ぷらそば・天ぷらうどん・カツ丼・天丼のいずれかを食べると、たちまち300カロリーを越える。これらの原料は大豆・菜種油・ごまなどの安価な輸入品である。日本の輸入金額としては少ないものの、食事としては高カロリーとなる。農林水産省の政策担当者が、食料自給率を低くするため、高カロリーの食用油脂を加えているのであろう。
その3
2458cal/日というカロリー摂取量は成人男性の場合であり、ほぼ2000calが日本人の平均である。39%という低自給率を導き出すために、2458という数値を無理に設定したのかもしれない。実際の数値との差500calは、実際には食べられていない。考えられるのは
(1)宴会・給食など、大量の食料の一部が、食べ残しとして捨てられる。
(2)食堂・レストラン・弁当屋が、売れる予想を見込んで生産するが、予想が外れて捨てられる。
(3)各家庭の冷蔵庫にある食品が、賞味期限を切れて捨てられる。
(4)野菜・果実・肉・魚などは100%全部をたべることはできず、食べられない部位は捨てられる。
(5)油脂類の占める割合が多い。天ぷら油などは、食べるよりも捨てる量の方が多い。
(6)賞味期限の切れた食品・弁当が、食堂・スーパーなどから、大量に捨てられる。
(7)経済取引外だが、日本の野菜・果実は価格低下時には収穫されずに、廃棄される。
----------------------------------------------------
和牛
日本の在来種に交配を繰り返して改良された牛である。「黒毛和種」、「褐色和種」、「日本短各種」、「無角和種」の4種類が和牛である。高級なブランド牛として取引されるのは、この在来種の和牛である。日本で、日本国内のエサを一定産地で一定期間摂取しなければならない。

国産牛
国産牛は輸入牛である。輸入されてから3か月以上国内で飼育されると、国産牛となる。生きたまま輸入した牛は、アメリカ産でもオーストラリア産でも、日本で3か月以上飼育された牛は、国産牛である。
しかし、生きたままの牛を輸入するのは、エサや健康管理の問題が大きく、困難である。
実際には和牛指定の4種以外の牛が日本国内で育てられた場合、その牛をが国産牛とする。安価な輸入飼料で育てられ、カロリーベースの自給率の計算では輸入牛に区分される。乳牛のオス牛が大半であり、和牛よりは安値である。
輸入牛肉
冷凍肉として大量に輸入される。アメリカやオーストラリアで部位を単位に冷凍加工された牛が、冷凍船で運ばれて来る。一般の焼肉店やスーパーマーケットで売られている。最も安価な肉である。
下図は2020年の食料自給率である。左図はカロリーベースの総合自給率39%である。右図は生産額ベース総合食料自給率では69%である。
食料自給率39%と、日本農業危機的状況といわれるのは、カロリーベース総合食料自給率の方である。

(クリックすると拡大)
金額、要するに食料として買った分が生産額ベース食料自給率である。ほぼ70%である。米を食べ、輸入肉と小麦(パン)の食べる量を減らせば、自給率は90%になる。食料自給の危機は、心配するほどのものではない。
しかし、この金額ベースの食料をカロリーベースで計算すると、自給率は40%以下の危機的状況になる。40%以下になった理由として、政策担当者の意図的操作を想像させるような、おかしな点が3つある。
その1
畜産物のカロリーベース自給率が低いこと、つまり輸入肉類の輸入依存が高いことである。これは下左図の追加図にあるように、日本国内で飼育されている家畜が、輸入飼料を食べると輸入畜産物として扱われるからである。
家畜・畜産物・肉類の国内取引はすべて国産であっても、牛・豚・鶏などが食べているのが輸入飼料なので、輸入畜産物となる。取引段階では国産肉が、食卓に並ぶと、輸入肉になる、という計算である。
世界各国から日本には畜産物の輸入圧力が強い。日本の畜産農家保護のため、日本政府が現在でも畜産物の輸入割合が多いことを示すための、意図的数字操作との批判がある。
その2
カロリーの高い食品を多めに入れている。つまり、サラダ油・天ぷら油はカロリーが非常に高く、天ぷら・天ぷらそば・天ぷらうどん・カツ丼・天丼のいずれかを食べると、たちまち300カロリーを越える。これらの原料は大豆・菜種油・ごまなどの安価な輸入品である。日本の輸入金額としては少ないものの、食事としては高カロリーとなる。農林水産省の政策担当者が、食料自給率を低くするため、高カロリーの食用油脂を加えているのであろう。
その3
2458cal/日というカロリー摂取量は成人男性の場合であり、ほぼ2000calが日本人の平均である。39%という低自給率を導き出すために、2458という数値を無理に設定したのかもしれない。実際の数値との差500calは、実際には食べられていない。考えられるのは
(1)宴会・給食など、大量の食料の一部が、食べ残しとして捨てられる。
(2)食堂・レストラン・弁当屋が、売れる予想を見込んで生産するが、予想が外れて捨てられる。
(3)各家庭の冷蔵庫にある食品が、賞味期限を切れて捨てられる。
(4)野菜・果実・肉・魚などは100%全部をたべることはできず、食べられない部位は捨てられる。
(5)油脂類の占める割合が多い。天ぷら油などは、食べるよりも捨てる量の方が多い。
(6)賞味期限の切れた食品・弁当が、食堂・スーパーなどから、大量に捨てられる。
(7)経済取引外だが、日本の野菜・果実は価格低下時には収穫されずに、廃棄される。
----------------------------------------------------
和牛
日本の在来種に交配を繰り返して改良された牛である。「黒毛和種」、「褐色和種」、「日本短各種」、「無角和種」の4種類が和牛である。高級なブランド牛として取引されるのは、この在来種の和牛である。日本で、日本国内のエサを一定産地で一定期間摂取しなければならない。

国産牛
国産牛は輸入牛である。輸入されてから3か月以上国内で飼育されると、国産牛となる。生きたまま輸入した牛は、アメリカ産でもオーストラリア産でも、日本で3か月以上飼育された牛は、国産牛である。
しかし、生きたままの牛を輸入するのは、エサや健康管理の問題が大きく、困難である。
実際には和牛指定の4種以外の牛が日本国内で育てられた場合、その牛をが国産牛とする。安価な輸入飼料で育てられ、カロリーベースの自給率の計算では輸入牛に区分される。乳牛のオス牛が大半であり、和牛よりは安値である。
輸入牛肉
冷凍肉として大量に輸入される。アメリカやオーストラリアで部位を単位に冷凍加工された牛が、冷凍船で運ばれて来る。一般の焼肉店やスーパーマーケットで売られている。最も安価な肉である。