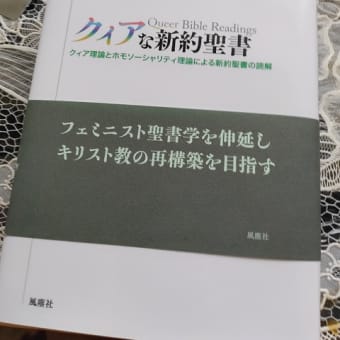J・ボードリヤールがリアリティーショーを議論している。1971年に米国で放送された「テレビ・ベリテ」という家庭にテレビカメラを持ち込み300時間密着取材するリアリティーショーに関してである。
家族はテレビカメラを意識しないで生活していることになっているが、実際はどうだったろうか。ボードリヤールは「見る権力者/見られる非権力者」という非対称性が失効していると分析している。これはフーコーの一望監視装置(パノプチコン)論を下敷きにしている。近代は見る側が権力で、見られる側は権力側が見ることを内面化しているという生権力論である。
しかし、生権力では見られることの不安があったが、この家族は見られることを進んで選んでいる。その意味であえて見られることを内面化し、抑圧とされていたことを抑圧ではないように主体化していくわけだ。
ところが、この家族は裕福な中産階級で理想的な家族であったが、リアリティショーはこの家族を変容させる。幸せな家族は崩壊してしまう。ここでテレビが持つ力学が幸せな家族を崩壊させたのか否かについては留保されている。
ここには見られること自体が欲望の対象になる原点が描かれているように思われる。ボードリヤールはこのようなリアリティショーを「監視の終わり」と称したが、「監視の終わり」を含む監視が作動し、つまり見られることの欲望を肯定し、それらを見ることが当然となるような社会が現れたのである。これはリアリティショーで論じられたことだが、現在のSNSを見れば、よりこのような状況が具体化し、我々に内面化しているのは理解しやすいだろう。
「見る/見られる」両者を内面化してしまう。そして、テレビカメラは「見られる」を作り出す。過去のテレビカメラで撮られることのない世界は特に意識化することもない普通の生き方を必然とするし、それが普通だとも意識化しない。
そこにテレビカメラが入り、撮られていることで、意識のあり方に変容が起こる。その変容された空間は臨場感空間を構築してしまう。メディアの力学が意識の変容を起こす。それは無意識化さえされるだろう。
「テレビ・ベリテ」というリアリティショーは、人々にテレビ画面を通して見られることを内面化する。家族は「テレビ・ベリテ」の人質になっているのだ。臨場感空間は人々を高揚させる。実は家族はテレビカメラを意識化していないかのように見えながら、テレビ映って、人々に見てもらっていることを意識するので、かつてあったテレビカメラのない普通の世界とは違う世界に高揚しているのだ。
その高揚は何かを変容させる。ストックホルム症候群では、人質はすべからく犯人に同情し、犯人の味方についた。そのうちの1人は犯人が獄中にいるにも関わらず結婚した。リアリティショーでも、出演者はテレビで人々が観ていることを意識もせずに内面化して、何かが変容している。少なくとも意識が変容する。これは普通の世界とは違うので、人々は高揚する。
僕自身もテレビ出演したことがある。もちろん自分自身がそれで高揚していたかといえば、そのような状況がおそらくは少なからずの高揚を僕にもたらしていた。ただたった1回だけの短い出演であるから、一時的なこととして、すぐに普通に戻る。
このように考えていけば、テレビ出演を続ける人は常に臨場感空間に存在する。それでも、それはテレビでの演技であり、仕事として割り切れるという側面を有する。だから普通にも戻りやすい。あくまで仕事なのだと。
臨場感空間はどこでも起こる。例えばコンサートに行けば生じる。ただコンサートだからという空間的限定および時間的限定があるので、エンターテイメントとして享受し、言い換えれば非日常として享受し、日常に戻るのである。おそらくかつては祭りがそういう役割を担っていた。
ところが、リアリティショーは仕事ではなく、実人生のようでもある。いや、リアリティと名乗っているのだから、実人生なのだ。テレビが入り、実人生が新たな実人生に変容したにもかかわらず、実人生なのだ。それが臨場感空間を作り出し、出演者に高揚感を作り出す。
リアリティショーは出演者を人質にとっている。あのストックホルム症候群が横滑りし、テレビによって機能してしまうのだ。機能というより自律運動といったほうがより正確でもある。そういうシステムに木村花さんも巻き込まれていたのだ。ここで日常と非日常が融合してしまう。
そして、臨場感空間は別の側面からももたらさられる。
(つづく)