▽前回『三省堂国語辞典のひみつ』(以下「三国のひみつ」)という本について書いたのだけれど、
昨日読み始めたサンキュータツオ著『国語辞典の遊び方』も数ある国語辞典の特徴が紹介されていてお薦めです。

ビブリオバトル地区大会に進むことになったのでちょっと背景知識の補足をしておきたい、こここそ求められている副賞でもらった図書カードの使い時でしょうと思って購入。
「わかりやすさ」「読みやすさ」をめちゃくちゃ意識してる本。
これから国語辞典を引く必要のありそうな論文・企画書・メールを書くことを強いられる学生や社会人の方、
子どもに国語辞典を引かせる必要のありそうな教員や保護者の方に特にお薦めしたいなぁなどと考えています。
なにより『三国のひみつ』を教えてくれた中学校図書館司書の母親にこの本は知っておいてほしいなぁと思って、
先日のビブリオバトルの報告も兼ねて電話。
▽まずは、おすすめいただいた本を読みましたよという報告から。
私「『三国のひみつ』読んだよー。おもしろかったー。」
母「おもしろかったでしょ?三省堂の国語辞典必要に思えてくるよね。」
私「たしかに中学校図書館にはあったほうがいいだろうねぇ。母さんが読んだのって文庫版?」
母「うん」
私「(え?文庫本には電子辞書のこと書いてなかったやん。)あれ新潮じゃなくて三省堂が出した元のやつもあるじゃん?かなり三省堂をよいしょしてるとかってあとがきに書いてあった」
母「単行本の方ね。」
私「そう。俺も読んだのは文庫の方だったんだけど、生協の本屋さんで取り寄せたら単行本と文庫と両方届いたんよ。で、どっち買われますか?って聞いてくれてね、じゃあ安い方お願いしますーで文庫本を買って。」
母「へー、そんなことが。私が読んだのも文庫の方。あれもおもしろかったよ、サンキュータツオっていう人の書いた」
私「(もしや)『国語辞典の遊び方』?」
母「そう。読んだ?」
私「今読んでる」
母「あれもいろんな辞書が欲しくなるよね。」
私「うん、ベネッセのやつ欲しくなった。」
・
・
・
▽オススメするまでもなかった。
母親に抜かりはなかった。
電子辞書より紙辞書どうこうは母親の記憶違いかな。
他の本で読んだことと混濁したか、自分の思想と混濁したかはわからんけど。
両方かな。
▽「興味がない人にとっては国語辞典はどれも同じ」
「俺もガンダムはよくわからん」
という意味のことを前回のブログでは書いたのだけれど、
この『国語辞典の遊び方』でも同じようにガンダムの例えが出てきいて、
表現がかぶってしまったのがなんか悔しい。
一般人にはよくわからないけれども細部にこだわっていてそれなりの人数のファンがついているコンテンツ=ガンダム
という式を安易に使って独創性を欠いてしまった。
▽今母親は嘱託で私の母校である中学校の図書室司書をやっていて、図書室辞書事情の話にもなりました。
「三国のひみつ」を読んで図書室に三省堂国語辞典を入れた、とだけ電話で聞いたからてっきり
図書室にある、書棚の一角の辞書コーナーみたいなのに何種類かの辞書が1冊ずつ置いてあり、その中に「三国」を追加した、という光景を想像したのだけれど、
10冊も入れていた。
それは別に「三国」だけひいきをしているわけではなくって、「新明解」や「岩波」や「明鏡」などの他の小型・中型国語辞典もそれぞれ10冊ずつくらいはあるらしい。
9種類の辞書があるって言ってたかな。
そしてなんとあの「日本国語大辞典」も図書室に置いてあるとか。
文学部で日本語学やってる人はたいそう驚くよ。
「中学生に使いこなせるのか!?」という感じ。
多くの大学文系科目の授業がそうであるように「日本語学」の授業には段階があって、
(「入門」)「概説」「講義」「演習」とレベルアップしていく。
日本国語大辞典の使用が強く求められたのは「日本語学演習」の講義が初めて。紹介は講義とか概説でもやるけど参考程度。
大学生が専門分野の調べものに使うレベル。
全13巻ある唯一の大型国語辞典。(精選版でも全3巻。)
個人で買うのはよっぽどの国語狂。あれは図書館で読むか、研究室に置くとしても経費で買うもの。
それぞれの意味の一番古い(と思われる)用例を載せていて、
その語の最も基本的な意味はこれだ!とか
この使い方はこの時期に初めて現れた用法だ!とか
その意味での使用は江戸期に初めて見られるから平安時代の文書の解釈がそういう意味には(専門家が調べた限りでは)ならない!
を調べる辞書。
それが新語・現代語にまで及んでいるやべぇやつ。
「この論文は語彙について調査していらっしゃいますけどもちろん国語大辞典は引いていらっしゃいますよねぇ?」
くらいの大権威。
そのレベルの辞書が中学校の図書室に・・・。
置くスペースあるんか?
▽私の中学生当時から日本国語大辞典は置いてあったのだろうか。
辞書にも日本語にもさほど興味がなかったから恵まれた環境にあることに気づかなかっただけ・・・?
ただ小型・中型辞書についてはそれぞれ10冊ずつあるというような環境では絶対になかった。
だって予算が多めに下りて入れたの今年らしいもん。
私が受けた授業では辞書は各自が家から持ってきてそれを使うという形式でした。
今は辞書による違いを知るためにも複数の辞書を引いてみさせるという方針。
普通、家に辞書は複数冊無い。
というか一冊も無い家だって多いと思う。
高いもん。重いもん。使わんもん。
だから図書室に。
授業で引くから複数冊。
▽学校というシステムの都合上機動力の低さは否めないものの、たとえ同じ教科書教材でも同じことを同じように続けているだけではなくって、
あれやこれや手を変えて、どんどん変わっていくものなのだなぁと、
気づかされた母親との会話でした。
最新の画像[もっと見る]
-
 前略、石見にて
5年前
前略、石見にて
5年前
-
 はじめましての人のために。
6年前
はじめましての人のために。
6年前
-
 大学生向けに自転車マナーを考えてもらう機会を作りたい【GW連続投稿チャレンジその3】
6年前
大学生向けに自転車マナーを考えてもらう機会を作りたい【GW連続投稿チャレンジその3】
6年前
-
 違う道だけど同じ轍を踏む【GW連続投稿チャレンジその2】
6年前
違う道だけど同じ轍を踏む【GW連続投稿チャレンジその2】
6年前
-
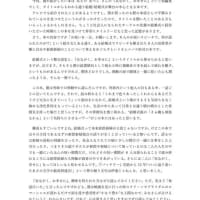 ラジオに出ました。
8年前
ラジオに出ました。
8年前
-
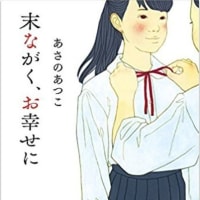 ラジオに出ました。
8年前
ラジオに出ました。
8年前
-
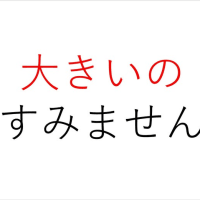 馬鹿と鋏は使いよう
8年前
馬鹿と鋏は使いよう
8年前
-
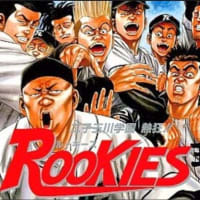 全国大学ビブリオバトル2017首都決戦
8年前
全国大学ビブリオバトル2017首都決戦
8年前
-
 全国大学ビブリオバトル2017首都決戦
8年前
全国大学ビブリオバトル2017首都決戦
8年前
-
 海自カレー巡り~僕たちの大和物語~
8年前
海自カレー巡り~僕たちの大和物語~
8年前










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます