▽西条に向かう鈍行列車で読んだ本の話。
『三省堂国語辞典のひみつ』

▽生家に進路報告の電話を入れた際に、ほとんど脈絡なく母親から「紙の辞書持ってる?」
との質問を受け、新明解を家から持ってきていると答えたら
「『三省堂国語辞典のひみつ』っていう本を読んだんだけど三省堂国語辞典がいいよ」と唐突に紹介された本。
「あー三省堂国語辞典は見たことないなー。新明解以外の辞書なら電子辞書に3冊分くらい入ってるけど」と言うと
「電子辞書じゃなくてやっぱり紙辞書がいいとかいうことも書いてあるから」と、紹介された本。
ともあれ、母勤務の中学校に今までなかった三省堂国語辞典を入れさせるくらいのこの本、実に興味深いではないですか。
落ち込んでいるときに『「落ち込み気分」が続いたときに読む本』という本を紹介してくれたり、
他にも母親から今までたくさんの本を勧めてもらって読んだら面白かった、参考になったという本は多く、
母親の推薦図書にはいくらかの信頼を置いている私。
今回の本も当たりでした。
▽三浦しおん著『舟を編む』で注目を浴びた辞書編纂の世界。
そのアニメ化にもかかわったらしい三省堂国語辞典編纂者の飯間浩明著の辞典エッセイ。
▽見出し語の説明が辞書により異なることはこの本を読む以前からある程度気にしていました。
言語学を学ぶものの端くれとして。
『問題な日本語』という本を出版するくらいの大修館の明鏡国語辞典はよく見聞きされる誤用についての言及が多く、失敗できない文章を書く時には大いに参考になるし、
「百科事典的な辞書」として代表的な、例えば動物なら生息分布や具体的な大きさにまで説明が及ぶ広辞苑は実際を知らなくてもすげー知ったような顔で「ヨーロッパ原産ですもんね」とか言うときに役立つし、
私の持っている新明解国語辞典は語釈そのものや例文での使い方が独特で、「辞書というよりも読み物としておいてあります」みたいな人も多い。それは絶対嘘だと思う。(けど『明解さんの謎』はおもしろかった。)
その『新明解国語辞典』と同じ出版社が出す『三省堂国語辞典』、
どういう方針の辞書なのか、何にこだわっているのか、そのためにどう頭を悩ませているのか、というのが大筋。
本文の言葉を借りると、
書店に並ぶ国語辞典の棚を見て、「どれも国語辞典には変わりないだろう。こんなに要らないのではないか」と思うのは、
ミステリー小説がの棚を見て、「どれも同じ推理小説なのだからこんなに要らないだろう」と思うのと同じくらい的外れな指摘で、
それぞれ特徴がある。そのことを知ってほしい!望むらくはぜひ三省堂国語辞典を使ってほしい!という本。
(とはいえやっぱり興味がない人にとっては推理小説であっても同じに見えるんだろうけれども。俺もガンダムとかよくわからんし。)
辞書と持ち主の関係は医師と患者の関係にあってほしいというのが著者の思いで、
医師(辞書)は患者(読者)に信用されなければ成り立たないが、担当医の判断だけで決断するのではなく他の医師(辞書)にも当たってほしい。
辞書のセカンドオピニオンだと。
▽読んだ気になってもらっても困るので三省堂国語辞典がどんな辞書かはあえて書きません。
このブログにここまで付き合ってくれている人ならきっと気に入るはず。
辞書編纂を中心にしながら、編纂にからめて「現代日本語」について色々な考察もされていたりと、「日本語」に興味のある人にぜひ私もお薦めしたい。
▽ということで、本日大学図書館で開催された「知的書評合戦-ビブリオバトル-」にて紹介させてもらいました。
「ビブリオバトル」というのは、1.本を紹介して 2.自分が紹介した本以外でどの本を一番読みたくなったかを投票して 3.チャンプ本を決める 読書会の一形式。
この「選ばれるのは発表者ではなくあくまで本」という公式ルールの姿勢が好き。
参加者数=発表者数の時もあれば、参加者数>発表者数の時もある。いわゆる観客にチャンプ本を選んでもらう方式。今回はこれ。
本の紹介は5分間(長くても短くてもダメ。)で、そのあと3分間質疑応答。タイマーを用いる厳密なルール。
大学生協の「読書マラソンの集い」というイベントに参加していたころにも何度か本を紹介してみたことがあり、
今回はその経験値が活きたか、運も味方し全4冊の中から『三省堂国語辞典のひみつ』がチャンプ本に選ばれました。
チャンプ本に選ばれた本の発表者として、来月は中国Cブロックの地区決戦にて発表することとなります。
副賞として図書カード5,000円分もいただきました。
▽やはり読んだばかりの本は記憶が鮮明で紹介しやすいな、というのが正直な感想。
読み終えたのはイベント開始1時間半前。
先週の木曜日に人員欠如で急遽エントリーを迫られ、
母上推薦図書というだけで面白い本だと決めつけ取り急ぎエントリーシートを即日提出し、
図書館の方と打合せをすませ、
注文していた本屋さんに本を取りに行き、
2,3日寝かせ、
読み始めたのが日曜日。
「この辺のエピソードを話そう」とかも考えながら読めたのもよかった。
あと質疑応答の時間に、観客(エプロンから察するに図書館の職員の方)からちょうど発表時間の関係で話すのを諦めた部分のことについて聞かれたのもよかった。
そもそも人に勧められて読み始めた本だったから「読みたくなる本かどうか」という吟味がそこまで要らなかったし。
サンキューマッマ。
けどわいの買った文庫版には「電子辞書より紙辞書が良い」とは書いてなかったよマッマ。
▽ちなみに今日の発表前にちょっと時間があったから大学図書館の蔵書を検索したら
三省堂国語辞典の最新版は入っていませんでした。
一個前の版はありましたが、普通の学生は入れず閲覧までに申請から半日かかる書庫に保管されておりました。
もし図書館の辞書コーナーに最新版が置いてあったなら発表の際に「ぜひ手に取って他の辞書との違いを見てみてください」というつもりだったんだけど。
この発表を機に図書館に入れてくれたりするかしら。
そこまでの影響力はお前にない。
『三省堂国語辞典のひみつ』

▽生家に進路報告の電話を入れた際に、ほとんど脈絡なく母親から「紙の辞書持ってる?」
との質問を受け、新明解を家から持ってきていると答えたら
「『三省堂国語辞典のひみつ』っていう本を読んだんだけど三省堂国語辞典がいいよ」と唐突に紹介された本。
「あー三省堂国語辞典は見たことないなー。新明解以外の辞書なら電子辞書に3冊分くらい入ってるけど」と言うと
「電子辞書じゃなくてやっぱり紙辞書がいいとかいうことも書いてあるから」と、紹介された本。
ともあれ、母勤務の中学校に今までなかった三省堂国語辞典を入れさせるくらいのこの本、実に興味深いではないですか。
落ち込んでいるときに『「落ち込み気分」が続いたときに読む本』という本を紹介してくれたり、
他にも母親から今までたくさんの本を勧めてもらって読んだら面白かった、参考になったという本は多く、
母親の推薦図書にはいくらかの信頼を置いている私。
今回の本も当たりでした。
▽三浦しおん著『舟を編む』で注目を浴びた辞書編纂の世界。
そのアニメ化にもかかわったらしい三省堂国語辞典編纂者の飯間浩明著の辞典エッセイ。
▽見出し語の説明が辞書により異なることはこの本を読む以前からある程度気にしていました。
言語学を学ぶものの端くれとして。
『問題な日本語』という本を出版するくらいの大修館の明鏡国語辞典はよく見聞きされる誤用についての言及が多く、失敗できない文章を書く時には大いに参考になるし、
「百科事典的な辞書」として代表的な、例えば動物なら生息分布や具体的な大きさにまで説明が及ぶ広辞苑は実際を知らなくてもすげー知ったような顔で「ヨーロッパ原産ですもんね」とか言うときに役立つし、
私の持っている新明解国語辞典は語釈そのものや例文での使い方が独特で、「辞書というよりも読み物としておいてあります」みたいな人も多い。それは絶対嘘だと思う。(けど『明解さんの謎』はおもしろかった。)
その『新明解国語辞典』と同じ出版社が出す『三省堂国語辞典』、
どういう方針の辞書なのか、何にこだわっているのか、そのためにどう頭を悩ませているのか、というのが大筋。
本文の言葉を借りると、
書店に並ぶ国語辞典の棚を見て、「どれも国語辞典には変わりないだろう。こんなに要らないのではないか」と思うのは、
ミステリー小説がの棚を見て、「どれも同じ推理小説なのだからこんなに要らないだろう」と思うのと同じくらい的外れな指摘で、
それぞれ特徴がある。そのことを知ってほしい!望むらくはぜひ三省堂国語辞典を使ってほしい!という本。
(とはいえやっぱり興味がない人にとっては推理小説であっても同じに見えるんだろうけれども。俺もガンダムとかよくわからんし。)
辞書と持ち主の関係は医師と患者の関係にあってほしいというのが著者の思いで、
医師(辞書)は患者(読者)に信用されなければ成り立たないが、担当医の判断だけで決断するのではなく他の医師(辞書)にも当たってほしい。
辞書のセカンドオピニオンだと。
▽読んだ気になってもらっても困るので三省堂国語辞典がどんな辞書かはあえて書きません。
このブログにここまで付き合ってくれている人ならきっと気に入るはず。
辞書編纂を中心にしながら、編纂にからめて「現代日本語」について色々な考察もされていたりと、「日本語」に興味のある人にぜひ私もお薦めしたい。
▽ということで、本日大学図書館で開催された「知的書評合戦-ビブリオバトル-」にて紹介させてもらいました。
「ビブリオバトル」というのは、1.本を紹介して 2.自分が紹介した本以外でどの本を一番読みたくなったかを投票して 3.チャンプ本を決める 読書会の一形式。
この「選ばれるのは発表者ではなくあくまで本」という公式ルールの姿勢が好き。
参加者数=発表者数の時もあれば、参加者数>発表者数の時もある。いわゆる観客にチャンプ本を選んでもらう方式。今回はこれ。
本の紹介は5分間(長くても短くてもダメ。)で、そのあと3分間質疑応答。タイマーを用いる厳密なルール。
大学生協の「読書マラソンの集い」というイベントに参加していたころにも何度か本を紹介してみたことがあり、
今回はその経験値が活きたか、運も味方し全4冊の中から『三省堂国語辞典のひみつ』がチャンプ本に選ばれました。
チャンプ本に選ばれた本の発表者として、来月は中国Cブロックの地区決戦にて発表することとなります。
副賞として図書カード5,000円分もいただきました。
▽やはり読んだばかりの本は記憶が鮮明で紹介しやすいな、というのが正直な感想。
読み終えたのはイベント開始1時間半前。
先週の木曜日に人員欠如で急遽エントリーを迫られ、
母上推薦図書というだけで面白い本だと決めつけ取り急ぎエントリーシートを即日提出し、
図書館の方と打合せをすませ、
注文していた本屋さんに本を取りに行き、
2,3日寝かせ、
読み始めたのが日曜日。
「この辺のエピソードを話そう」とかも考えながら読めたのもよかった。
あと質疑応答の時間に、観客(エプロンから察するに図書館の職員の方)からちょうど発表時間の関係で話すのを諦めた部分のことについて聞かれたのもよかった。
そもそも人に勧められて読み始めた本だったから「読みたくなる本かどうか」という吟味がそこまで要らなかったし。
サンキューマッマ。
けどわいの買った文庫版には「電子辞書より紙辞書が良い」とは書いてなかったよマッマ。
▽ちなみに今日の発表前にちょっと時間があったから大学図書館の蔵書を検索したら
三省堂国語辞典の最新版は入っていませんでした。
一個前の版はありましたが、普通の学生は入れず閲覧までに申請から半日かかる書庫に保管されておりました。
もし図書館の辞書コーナーに最新版が置いてあったなら発表の際に「ぜひ手に取って他の辞書との違いを見てみてください」というつもりだったんだけど。
この発表を機に図書館に入れてくれたりするかしら。
そこまでの影響力はお前にない。














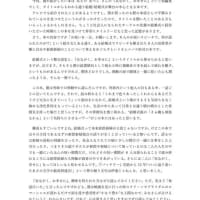
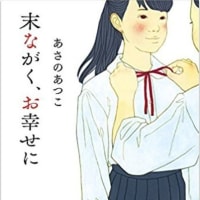
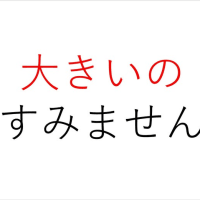
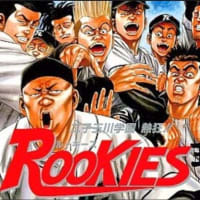


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます