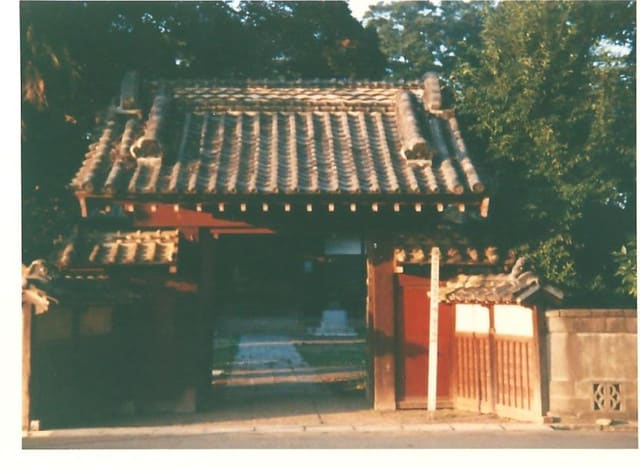神流川の下久保ダム上流は、美しい渓谷があります。
美しいとは言っても、新道開通によって大分興趣が減じたのですが・・。
2018年07月31日に訪問いたしました。
私が、初めてここを尋ねたのは、1986年の早春でした。
秩父鉄道の皆野駅から出発して、徒歩で志賀坂峠を越えて群馬県側に出たのですが、
さすがに、足が棒というよりも、ひざが反対側に曲がりそうでした。
なぜ歩いたか・・・。
それは資金不足だったからです。
さて、今回はさすがにそんな真似をしようとは思いませんでした。
さて、神流川の奇勝、丸岩です。岩の上に誰か住めそうですね。
盆栽のようです。







さて、この丸岩に並ぶようにして、珍しい名前の神社があります。
神流川鮎神社です。




祠の台座は対岸にある石灰岩鉱山、叶山の頂から降ろしたもののようです。
以前は、この他にも謂れのある奇岩があったのですが、どこに行ってしまったのか。
旧道を丹念に探さないと見つからないでしょうね。
いつか探したいと思っています。
美しいとは言っても、新道開通によって大分興趣が減じたのですが・・。
2018年07月31日に訪問いたしました。
私が、初めてここを尋ねたのは、1986年の早春でした。
秩父鉄道の皆野駅から出発して、徒歩で志賀坂峠を越えて群馬県側に出たのですが、
さすがに、足が棒というよりも、ひざが反対側に曲がりそうでした。
なぜ歩いたか・・・。
それは資金不足だったからです。
さて、今回はさすがにそんな真似をしようとは思いませんでした。
さて、神流川の奇勝、丸岩です。岩の上に誰か住めそうですね。
盆栽のようです。







さて、この丸岩に並ぶようにして、珍しい名前の神社があります。
神流川鮎神社です。




祠の台座は対岸にある石灰岩鉱山、叶山の頂から降ろしたもののようです。
以前は、この他にも謂れのある奇岩があったのですが、どこに行ってしまったのか。
旧道を丹念に探さないと見つからないでしょうね。
いつか探したいと思っています。