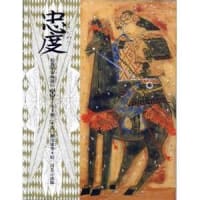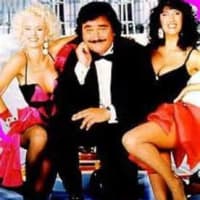53. cicala(チカーラ)とzanzara(ザンザーラ):これも日本語のような響きです。cicalaはセミ、zanzaraは蚊です。ちなみに、mosca(モスカ)はハエです。このmoscaはMosca(モスクワ)と同じです。英語でmosquitoと言えば、ハエではなく蚊のことです。mosquitoは発音から言えば、mosqua(モスカ)に小さいという意味の接尾辞-ito(スペイン語、イタリア語でゃ-ino)をつけて、モスキートと名づけたのかと想像出来ますが、ハエの小さいのが蚊になったことになりますね。実は、イタリア語でもmoschinoと言えば、ある種の蚊(ブヨのような小さな蚊の総称)をいいますが、一般的な蚊は、zanzaraを使います。Moschinoはブランド名で有名です。イタリアのcicalaは日本のに比べると、鳴き声が小さいような気がします。また、zanzaraも湿地帯へいけば別ですが、空気が乾燥しているせいか、市内ではそれほど多くなく、夏の戸外での食事を妨げるほどではありません。イタリアで大変気に入ったものに、zanzariera(またはzanzariere)という蚊帳があります。これは、べランダを完全に覆ってしまいますので、蚊を気にしないでベランダで過ごせます。これは、開閉式になっていますので、開けっ放しにすることも出来ます。これはぜひ日本でも採用してほしいものです。ただ、日本の湿度だと夜になっても暑いので、意味がないのかとも言えます。また、イタリアの蚊と日本の蚊の違いとして、イタリアの蚊は刺されてもすぐに痒くならず、大分経ってまたは翌日に痒くなると言います。虫も大分違うようですね。尚、イソップ物語に「蟻とキリギリス」という話がありますが、イタリアでは「アリとセミ(la cicala e la formica」といいます。これは、もともとイソップ(古代ギリシア)物語ではキリギリスは「セミ」だったのですが、欧州は北の方へ行けばセミはいませんので、キリギリスに変えられたのだと言われています。イタリアは、ギリシアと同じくセミがいる国なので、原文のまま残っているということ。日本へは、キリギリスへ変えられたものが輸入されて、翻訳されたらしい。なお、明治時代に翻訳されたものを見ると、キリギリスでもなく、イナゴです。これは福沢諭吉が訳したとも言われているが、ではなぜイナゴがいつの間にキリギリスになったのだろうか。まあ、この程度はいいかと。しかしいずれにしろ、このイソップの話は、夏の間に寒い冬に備えてせっせと働く蟻と、一方夏は歌ってばかりで何もしなかったセミは冬になって、蓄えも無く凍えてしまうという教訓なのですが、考えてみれば、キリギリスは秋の昆虫ですから、話に無理があるのではと言う気がします。イソップの意思を汲んで、蝉に戻してはいかが?