ううあにはじいじがいる。ばあばもいる。
そしてなにより大好きなママがいる。
加えて、クマのオジーがいた。
オジーは会うたび、花をプレゼントしてくれた。
いつも必ず違う花で、でもどれも気に入らないということは一度としてなかった。
どうしてこんなに色んな花を知っているの?と尋ねると、
クマははちみつが好きだからね、美味しいはちみつを探していると、
自然と、色んな花を見つけるのさと答えてくれた。
すごいねーと感心していると、決まってママは、そんなに花ばっかりもらっても
置く場所に困るだけじゃないと言っては、オジーを困らせていた。
小さいけれど、ううあには自信満々で知っていることがある。
ううあはハワイの言葉で雨のこと。
そして、オジーがとてもとてもママのことを大好きだということ。
オジーは時々、山から下りてママに会いに来ていた。
軽自動車もろくに駐車できないほどの不器用さで、
クマのくせに大して力持ちでもなかった。
また、いつも調子はずれな歌を口ずさんでいた。
でもなぜかオジーはお金にはまったく困っていないようだった。
どうしてあれこれへたっぴなのに困らないの?と尋ねると、
いつも困っているよ、鮭を取って暮らしているんだけど、
みんなすばしっこくてひとつも取れやしない。
それで途方に暮れてぼんやりしていると、いつか取り損ねた鮭が
大きくなって戻ってくるんだ。そうして仕方ない奴だなと笑って、
今度は僕に取らせてくれる。みんなが助けてくれているんだと答えてくれた。
ママはオジーがとった鮭の卵を食べ終えると、今度は蟹が食べたいなと言った。
ううあは、冷たい海に潜って蟹をとるオジーを思った。
ママ、オジーはシロクマじゃないんだから凍えちゃうよ。
大丈夫、オジーの毛皮はリバーシブルだから。裏返せばシロクマさ。
そう言って笑うオジーの眼は、とても寒い雪の日の朝を思わせた。
北の海でたくさんの蟹をとって帰ってきたオジーは、
ひどく痛んでしまっていた。毛皮はじゅうたんのようにふかふかではなくなり、
歯をぎしぎし言わせて、トドのような鳴き声を上げるようになった。
ママは蟹を食べている間、一言も発しなかった。
ママには、時に奇妙な常識に人生を規定されるところがあった。
そして、すっかり食べ終えた後、オジーに短い別れの言葉を告げた。
震えが止まり、鳴き声も止んだオジーはてくてくと山へと歩いて行った。
それ以来、ううあはオジーには会っていないし、
家でもオジーのことは話題に上らなかった。
だから、オジーのことはあまりよく覚えていない。
一度だけ、朝ごはんにトーストを食べているとき、
ばあばが、そういえば昔、はちみつが苦手なクマさんがいたねぇとこぼしたのを聞いただけだ。
大きくなったけれど、ううあには分からないことがある。
取り逃がした鮭が戻ってきて、今度は取らしてくれたなんてことがあるのだろうか。
あるいは自分が自己犠牲的な鮭だったとして、その機会に巡りあうのだろうか。
大きくなって、ママじゃない誰かが隣にいる夜もある。
だけれど、一人の夜も増えた。
そんなとき、世界に向かって言えることがある。
どんな夜だってへっちゃっらよ。
だって私には、どこの誰かも分からないオジーがいたんだから。
その日はとても深い夜だった。
まるで北の海のようだ。ううあは思った。
彼女にとって、北の海は恐怖の象徴でしかなかった。
闇の中になにか怖いものが潜んでいるような気がしたし、
自分自身の中にも恐ろしいものが潜んでいるような気さえした。
気づくと、ううあは歌を口ずさんでいた。
おいらはクマのオジー
失敗ばっかのまるきりドジー
キミが怖いもの見ないよに
おいらが代わりに見てあげる
おいらはクマのオジー
いつもかなわぬ恋ー
キミが悲しくないよに
おいらが代わりに悲しむさ
おいらはクマのオジー
キミがひとりの時
決してさみしくないよに
おまじないをしてあげる
いつの間にか彼女は眠りについていた。
もう闇の中には親密なものしか残っていなかったが、夜はまだ続いていた。
鳴くことに関してのみ生真面目な鶏が、タイミングを逸しながらも、
夜の中にささやかな朝の訪れを知らせようとしたその時、
一度だけトドのような、本当に大きな声が街に響いた。
その声に、登るのを渋っていた太陽は驚いて顔を出し、長過ぎた夜の終わりを告げた。
本当に、大きな音であったが、人間たちにはその音は届かなかったようで、街は平静のままである。
ようやく登った太陽の、その燦々たる光のうちの幾つかが、木々を照らし、レースのカーテンを通り抜け、
ううあの頬を優しく照らし出し、涙に濡れた彼女の頬の上に小さな虹を架けた。
その出来事は、ひっそりと、しかし、不思議なまでにしっかりと、彼女の幸せを約束しているようだった。
そしてなにより大好きなママがいる。
加えて、クマのオジーがいた。
オジーは会うたび、花をプレゼントしてくれた。
いつも必ず違う花で、でもどれも気に入らないということは一度としてなかった。
どうしてこんなに色んな花を知っているの?と尋ねると、
クマははちみつが好きだからね、美味しいはちみつを探していると、
自然と、色んな花を見つけるのさと答えてくれた。
すごいねーと感心していると、決まってママは、そんなに花ばっかりもらっても
置く場所に困るだけじゃないと言っては、オジーを困らせていた。
小さいけれど、ううあには自信満々で知っていることがある。
ううあはハワイの言葉で雨のこと。
そして、オジーがとてもとてもママのことを大好きだということ。
オジーは時々、山から下りてママに会いに来ていた。
軽自動車もろくに駐車できないほどの不器用さで、
クマのくせに大して力持ちでもなかった。
また、いつも調子はずれな歌を口ずさんでいた。
でもなぜかオジーはお金にはまったく困っていないようだった。
どうしてあれこれへたっぴなのに困らないの?と尋ねると、
いつも困っているよ、鮭を取って暮らしているんだけど、
みんなすばしっこくてひとつも取れやしない。
それで途方に暮れてぼんやりしていると、いつか取り損ねた鮭が
大きくなって戻ってくるんだ。そうして仕方ない奴だなと笑って、
今度は僕に取らせてくれる。みんなが助けてくれているんだと答えてくれた。
ママはオジーがとった鮭の卵を食べ終えると、今度は蟹が食べたいなと言った。
ううあは、冷たい海に潜って蟹をとるオジーを思った。
ママ、オジーはシロクマじゃないんだから凍えちゃうよ。
大丈夫、オジーの毛皮はリバーシブルだから。裏返せばシロクマさ。
そう言って笑うオジーの眼は、とても寒い雪の日の朝を思わせた。
北の海でたくさんの蟹をとって帰ってきたオジーは、
ひどく痛んでしまっていた。毛皮はじゅうたんのようにふかふかではなくなり、
歯をぎしぎし言わせて、トドのような鳴き声を上げるようになった。
ママは蟹を食べている間、一言も発しなかった。
ママには、時に奇妙な常識に人生を規定されるところがあった。
そして、すっかり食べ終えた後、オジーに短い別れの言葉を告げた。
震えが止まり、鳴き声も止んだオジーはてくてくと山へと歩いて行った。
それ以来、ううあはオジーには会っていないし、
家でもオジーのことは話題に上らなかった。
だから、オジーのことはあまりよく覚えていない。
一度だけ、朝ごはんにトーストを食べているとき、
ばあばが、そういえば昔、はちみつが苦手なクマさんがいたねぇとこぼしたのを聞いただけだ。
大きくなったけれど、ううあには分からないことがある。
取り逃がした鮭が戻ってきて、今度は取らしてくれたなんてことがあるのだろうか。
あるいは自分が自己犠牲的な鮭だったとして、その機会に巡りあうのだろうか。
大きくなって、ママじゃない誰かが隣にいる夜もある。
だけれど、一人の夜も増えた。
そんなとき、世界に向かって言えることがある。
どんな夜だってへっちゃっらよ。
だって私には、どこの誰かも分からないオジーがいたんだから。
その日はとても深い夜だった。
まるで北の海のようだ。ううあは思った。
彼女にとって、北の海は恐怖の象徴でしかなかった。
闇の中になにか怖いものが潜んでいるような気がしたし、
自分自身の中にも恐ろしいものが潜んでいるような気さえした。
気づくと、ううあは歌を口ずさんでいた。
おいらはクマのオジー
失敗ばっかのまるきりドジー
キミが怖いもの見ないよに
おいらが代わりに見てあげる
おいらはクマのオジー
いつもかなわぬ恋ー
キミが悲しくないよに
おいらが代わりに悲しむさ
おいらはクマのオジー
キミがひとりの時
決してさみしくないよに
おまじないをしてあげる
いつの間にか彼女は眠りについていた。
もう闇の中には親密なものしか残っていなかったが、夜はまだ続いていた。
鳴くことに関してのみ生真面目な鶏が、タイミングを逸しながらも、
夜の中にささやかな朝の訪れを知らせようとしたその時、
一度だけトドのような、本当に大きな声が街に響いた。
その声に、登るのを渋っていた太陽は驚いて顔を出し、長過ぎた夜の終わりを告げた。
本当に、大きな音であったが、人間たちにはその音は届かなかったようで、街は平静のままである。
ようやく登った太陽の、その燦々たる光のうちの幾つかが、木々を照らし、レースのカーテンを通り抜け、
ううあの頬を優しく照らし出し、涙に濡れた彼女の頬の上に小さな虹を架けた。
その出来事は、ひっそりと、しかし、不思議なまでにしっかりと、彼女の幸せを約束しているようだった。











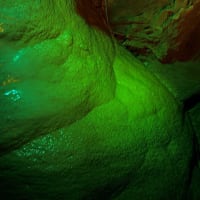








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます