小平市議会3月定例会で一般質問が始まりました。
私も今日26日朝9時すぎからトップバッターで質問に立たせて
頂きます。
今回も皆様から頂いたご意見を基に元気一杯取り組みます。
テーマは以下の3題です。頑張ります。 捨ててしまえばただのごみ、使用済み小型家電回収事業の今後について!
捨ててしまえばただのごみ、使用済み小型家電回収事業の今後について! 地域コミュニティーの形成、維持のために市は公共施設の設備整備をどう考えるか!
地域コミュニティーの形成、維持のために市は公共施設の設備整備をどう考えるか! 小平駅北口周辺地域の雨水管渠整備の現状について!
小平駅北口周辺地域の雨水管渠整備の現状について!


 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く

 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
日曜日午前10時から小平駅南口で出初式が行われました。
消防団の皆さん、今年も1年お世話になります。
▼東京ファイアーバードのフラッグ隊が華やかに
▼第三分団、第四分団の皆さんが凛々しく整列!




▼ 雲一つない冬晴れの小平の空に放水のアーチ
雲一つない冬晴れの小平の空に放水のアーチ


 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く

 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
▲ありがとう!森尾美穂さんが作ってくれたヒロシの福笑い
今日は朝から大忙し。第7小学校では恒例のどんど焼きが
行われ、地域ではたくさんの新年の寄り合いがありました。
中でも私がお邪魔した天神町の座談の輪では福笑いが行わ
れ、それも何と「あぶかわ浩」福笑いというものでみんなの
大笑いがはじけ、おめでたい初笑いとなりました。



「原野さんみたい!」 て、いーえ私は何も言ってませんてば。
爆笑、大笑いで今年もみんな元気にスタートです!
皆さん今年もますますお世話になります





 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く

 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
都内ホテルで2015年公明党東京都本部の新春賀詞交歓会
に参加しました。

高木美智代衆議院議員、竹谷 とし子参議院議員らが
お客様 をお出迎え!
各界を代表する方々、区市町村長など多くの来賓が参加し
新春を飾るに相応しい華やかな会合となりました。
さあいよいよ4月の統一地方選に向け一瀉千里に!



 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く

 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
2015年がいよいよ動き出しました。今年は4月に統一地方
選挙が予定されており、各陣営の動きが活発化しています。
市議会公明党は、選挙があってもなくても年間1000か所を
超える市内各所での市政、国政の街角報告会を地道に続け
て来ました。
厳しいお叱りを頂くこともあれば、暖かい激励を頂くこともあり
ますが、私たち地方議員はそんなご意見をどれだけ受け止め
られるかが重要な使命であると思います。
2015年の本年も、全力で小平の隅々に入り、実生活の声を
しっかりと受け止めていきたいと決意新たにしています。
みなさま今年もお世話になります。
本年もお気軽にご意見、ご要望をお寄せ下さいませ




 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く

 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
▲白梅大学デジタル写真部門大賞「仕合わせ」(photo by Kenichi.A) 2015年の小平の朝を迎えました。
2015年の小平の朝を迎えました。
皆さま、新年明けましておめでとうございます 
私虻川は2期8年間、「危ないを安心安全に」のテーマを掲げ、
徹して皆様のご意見を伺いながら、300を超える危険地点の
改善に取り組んでまいりました。
どうすればひとつひとつの問題に寄り添う事ができるのかを
真剣に考える中、感染症対策の分野ではヒブワクチン、肺炎
球菌ワクチン等の小平市独自の公費助成を実現、その後国
の定期接種に発展させることができました。
また事業継続BCPの観点から、震災対策として、市民を守る
市庁舎機能の強化を訴え、市役所南側に500人対応の
「災害用貯留式トイレ」を設置、健康福祉事務センターには
「非常用自家発電設備」の設置を実現して来ました。
さらに議会改革推進委員長として、議会と議員の基本原則を
定めた「議会基本条例」の全会一致の成立をリード。
今年はいよいよ市民のために働く議会が大きく前進します。
あぶかわ浩は今年も地域の皆さまのもとに駆け付け、本当に
住んでよかったと実感して頂ける小平市をつくるため、全力で
働いてまいります。

 皆さま今年もよろしくお願いいたします
皆さま今年もよろしくお願いいたします 



 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
▲美しい小平の夜景
今年もあと数時間となりましたが2014年も本当に多くの皆様
にお世話になり、心より感謝と御礼をもうしあげます。
今年もありがとうございました。
大晦日恒例のニュース配りで今年も打ち上げとさせて頂き、
さぁこれから大掃除って、どうでしょう。というかどうしましよ‥
ともあれ、来年もますます あぶかわ浩 がんばります♪♪
皆さま、来年もきっと良いお年をお迎えくださいね



 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く 

 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
今日11月25日から、小平市議会12月定例会が始まります。
私虻川 浩も27日木曜日の9時からトップバッターで質問に
立たせて頂きます。
今回も皆さまから頂いたご意見やご要望、地域の課題など
元気一杯取り組みます。
今回のテーマは以下の3題です。 小平市独自の成人用肺炎球菌ワクチン助成は
小平市独自の成人用肺炎球菌ワクチン助成は
いつまで続けるのか! 小平一信号無視の多い小平駅南口交差点の
小平一信号無視の多い小平駅南口交差点の
信号機の改善について! あかずの踏切小平駅西側の小平第1号踏切の
あかずの踏切小平駅西側の小平第1号踏切の
抜本的解決のために! 一歩前進へ向け頑張ります!
一歩前進へ向け頑張ります!


 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く

 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
▲十四小のシンボルの「巨大柳」。初代校長先生が中国から
取り寄せたものを植樹したそうです。ホントに大きいです!
報告が遅くなりましたが、先週末は小平第十四小学校の運動
会にお招き頂き参加させて頂きました。
台風直前の素晴らしい秋晴れの運動会となりました。


村松校長先生から様々お話を伺いました。今後は教員不足
が切実な課題となって来ます。総合的な対策が求められます。
先生たちが着ているユニフォームは今年のおニューです



午後からは浅倉議員、津本議員と共に遊説に繰り出しました。
街宣カーも少し小型の車にリニューアルです

小平の隅々に入って、元気一杯市政報告を行っています 




 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く
 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
 ワカモノのミカタ
ワカモノのミカタ
13日午後、小平市天神町の鈴天通り商友会では夏の終りの
お祭りが賑やかに開催。こちらの地域はけして大きくはないの
ですが、地域を盛り上げるため若者たちが挑戦をしてます。
昔ながらのやり方を尊重しながら新しい世代をどうしたら共感
させることができるか、千田会長を筆頭に真剣に取り組みを
進めています。今後のヒントはここにあると感じます。
夜はルネこだいらで、小平市商工会の主催で見守りカメラの
設置実現を推進するシンポジウムが開かれ、各種団体からの
ご意見を伺いました。
見守りカメラの設置については応援しながらも、カメラの設置
自体が犯罪防止とはならない、つまりカメラ自体が現実の犯罪
を防いでくれる訳ではない事は意識していくべきです。
はからずも商工会長が述べていたように、重要なことはやはり
カメラ設置の議論を通し、地域の問題意識と安全化へのコミュ
ニケーション作りが進むことが最も大切だと思います。
翌日14日午後からは、熊野宮の2年に一度の祭礼が勇壮に!
賑やかに神輿や太鼓が青梅街道を練り歩き、沿道を埋めた
市民の皆さんからの大喝さいを浴びていました。
鈴木囃子の子どもたちもほんとによく頑張りましたね






 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く
 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
 ワカモノのミカタ
ワカモノのミカタ
明日9月9日から、小平市議会9月定例会が始まります。
私虻川 浩も11日木曜日の9時すぎからトップバッターで質問
に立たせて頂きます。
今回も皆さまから頂いたご意見やご指摘の他、10月から定期
接種になる予防ワクチンについてや、市の施設やインフラの
今後の総合管理などについて、元気一杯取り組みます。
今回のテーマは以下の3題です。 小平駅北口、花小金井第5号踏切、大沼通りの諸課題と安全対策について!
小平駅北口、花小金井第5号踏切、大沼通りの諸課題と安全対策について! 水痘、成人用肺炎球菌等、予防ワクチンの現状と今後について!
水痘、成人用肺炎球菌等、予防ワクチンの現状と今後について! 公共施設等総合管理計画の策定について!
公共施設等総合管理計画の策定について! 各議員の一般質問のテーマは以下の通りです。
各議員の一般質問のテーマは以下の通りです。
|
氏 名 |
件 名 |
|
小野こういち |
(1) 街路樹や公園などの立ち木の維持管理について |
|
幸田 昌之 |
(1) 子どもたちを不審者から守る通学路対策を |
|
滝口 幸一 |
(1) 今後の空き家対策について |
|
川里 春治 |
(1) 今後の保育待機児童対策について |
|
石毛 航太郎 |
(1) 増加する空き家のさらなる対策を |
|
末廣 進 |
(1) 市の非核平和都市宣言の10周年に向け、非核平和事業の新たな展開を目指して |
|
細谷 正 |
(1) 地域見守り体制の検討状況はいかがか |
|
堀 浩治 |
(1) 全ての自然災害に強い小平市に |
|
山岸真知子 |
(1) 命を守るAEDの設置促進と効率的な活用のために |
|
虻川 浩 |
(1) 小平駅北口、花小金井第5号踏切、大沼通りの諸課題と安全対策について |
|
木村 まゆみ |
(1) 医療・介護総合推進法の実施では現在のサービス水準の維持、向上を図れ |
|
佐藤 充 |
(1) 安心して利用できる介護制度をどうすすめるか |
|
村松まさみ |
(1) 横田基地のオスプレイMV-22に関して |
|
吉池たかゆき |
(1) 喜平橋西側への人道橋設置について |
|
橋本 久雄 |
(1) 空き家、空き室、空き店舗の有効活用を |
|
磯山 亮 |
(1) ふるさと納税制度を生かし小平市をPRしよう |
|
立花 隆一 |
(1) 行政の役割を定めた地域公共交通ビジョンをつくるべきだ |
|
佐野 郁夫 |
(1) 小川駅西口再開発と周辺のまちづくりについて |
|
平野 ひろみ |
(1) 高齢になっても住みなれた地域で支援を受けるために |
|
常松 大介 |
(1) 学校給食、保育園給食のアレルギー対応は進んでいるか |
|
岩本 博子 |
(1) 女性職員が管理職をめざし活躍しやすい環境整備で202030の実現を |
|
小林 洋子 |
(1) (仮称)発達支援課を教育委員会に設置し、一貫した支援体制を |
|
津本 裕子 |
(1) 女性の元気を応援し男女共同参画社会を前進させよう |
|
日向 美砂子 |
(1) 自治基本条例が生かされているかの検証と評価を |
|
坂井やすのり |
(1) 自然災害、人災から市民の生命、財産を守る、安全で安心して暮らせる小平を目指して |



 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く
 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
 ワカモノのミカタ
ワカモノのミカタ
自民・公明両党の連立による第2次連立内閣が発足しました。
公明党からは、太田昭宏国土交通大臣が留任し3人の副大臣
と3人の大臣政務官が就任しました。
高木陽介衆院議員が経済産業・内閣府副大臣に、
山本香苗参院議員が厚生労働副大臣に就き、
浜田昌良参院議員が復興副大臣に再任されました。
また新たに、佐藤英道衆院議員が農林水産、
竹谷とし子参院議員が財務、
石川博崇参院議員が防衛の各大臣政務官に就任しました。
今後は、経済再生、復興加速、社会保障と税の一体改革に
加え、新たに地方創世、安全保障法制の整備、沖縄の負担
軽減、女性の活躍推進など全力を上げて取り組みます。
町では夏の終わりのお祭りが今年も秋を運んできます



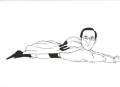


 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く
 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
大変だあ!FBのお友達情報で大沼町の神社に駆け付けると
見事な大木が倒れていました。
 こんなに立派な木が台風で真っ二つに折れてしまいました。
こんなに立派な木が台風で真っ二つに折れてしまいました。
直接的な被害はなさそうですが歩道の上に倒れていました。
東京街道ではお巡りさんが出て交通整理に当っています

 また以前も指摘した大沼団地ロータリー付近ではやっぱり
また以前も指摘した大沼団地ロータリー付近ではやっぱり
水があふれ、またまたプール状になってしまいました。
水が引くまで数時間とはいえ、プールとなって通行不能では
ホントに困ってしまいます。改善要望して行きたいと思います。
川のない小平市でも台風では様々問題がおきるのです
 大沼町の浸水関連その①はコチラ
大沼町の浸水関連その①はコチラ 大沼町の浸水関連その②はコチラ
大沼町の浸水関連その②はコチラ
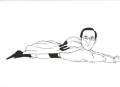


 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く
 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
 ワカモノのミカタ
ワカモノのミカタ
▲竹谷とし子参議院議員を迎えて市内で報告会
連日酷暑がつづいていますが皆さまお元気ですか?小平でも
市内全域で夏のお祭りやイベントが繰り広げられています。
そんな中私も、後半戦に向け地域の皆様への報告会と充実の
研修に元気に取り組んでいます。▼
▼富山県氷見市の本川祐治郎市長の自治体マネジメント
▼議会改革でお馴染の廣瀬克哉教授の講演(法政大学にて)



 充実の真夏の研鑽で後半戦に向けダッシュ
充実の真夏の研鑽で後半戦に向けダッシュ 


 クリックして拡大できます!
クリックして拡大できます!

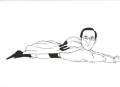


 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く
 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
 ワカモノのミカタ
ワカモノのミカタ
安全保障法制の整備について
(閣議決定全文) ※前文と4つの大項目の構成です!
我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家として歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、我が国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を遵守しながら、国際社会や国際連合を始めとする国際機関と連携し、それらの活動に積極的に寄与している。こうした我が国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにしなければならない。
一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間に、我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容するとともに、更に変化し続け、我が国は複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面している。国際連合憲章が理想として掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立っていないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとっても、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発及び拡散、国際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域において発生しても、我が国の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセス及びその活用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もまた、我が国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。
政府の最も重要な責務は、我が国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることである。我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制をもって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視することにより、紛争の平和的な解決を図らなければならない。
さらに、我が国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、域内外のパートナーとの信頼及び協力関係を深めることが重要である。特に、我が国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争を未然に回避し、我が国に脅威が及ぶことを防止することが必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するためには、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から報告書が提出され、同日に安倍内閣総理大臣が記者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党において協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必要な国内法制を速やかに整備することとする。
① 武力攻撃に至らない侵害への対処
(1)我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これにより更に重大な事態に至りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。
(2)具体的には、こうした様々な不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、各々の対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続を迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取組を一層強化することとする。
(3)このうち、手続の迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のために対応できない場合を含む。)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続を経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続の迅速化のための方策について具体的に検討することとする。
(4)さらに、我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の確保にとっても重要である。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含む。)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請又は同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。
② 国際社会の平和と安定への一層の貢献
(1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」
ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和及び安全が脅かされ、国際社会が国際連合安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、我が国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、我が国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、我が国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。
イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、我が国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境が更に大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。また、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、我が国の平和及び安全の確保の観点からも極めて重要である。
ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、我が国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。
(ア)我が国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。
(イ)仮に、状況変化により、我が国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止又は中断する。
(2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用
ア 我が国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家又は国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当するおそれがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。
イ 我が国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国際連合平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。
ウ 以上を踏まえ、我が国として、「国家又は国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、国際連合平和維持活動などの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。
(ア)国際連合平和維持活動等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」及び「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。このことは、過去20年以上にわたる我が国の国際連合平和維持活動等の経験からも裏付けられる。近年の国際連合平和維持活動において重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存及び武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。
(イ)自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づき、当該領域国における邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。
(ウ)受入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議における審議等に基づき、内閣として判断する。
(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。
③ 憲法第9条の下で許容される自衛の措置
(1)我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができないおそれがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。
(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
我が国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然であるが、それでもなお我が国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
(4)我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。
(5)また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それが国民の命と平和な暮らしを守るためのものである以上、民主的統制の確保が求められることは当然である。政府としては、我が国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続と同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記することとする。
④ 今後の国内法整備の進め方
これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、国家安全保障会議における審議等に基づき、内閣として決定を行うこととする。こうした手続を含めて、実際に自衛隊が活動を実施できるようにするためには、根拠となる国内法が必要となる。政府として、以上述べた基本方針の下、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、あらゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作業を開始することとし、十分な検討を行い、準備ができ次第、国会に提出し、国会における御審議を頂くこととする。


 あぶかわひろしは今日も行く
あぶかわひろしは今日も行く
 あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
あぶかわ浩(虻川浩)小平市議会議員のホームページ
 ワカモノのミカタ
ワカモノのミカタ



























