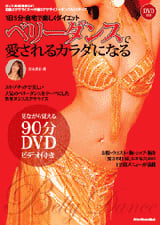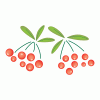鎌倉にある飲食店で行われた、養老先生と工業デザイナーさんとの対談。
2人の話は少し難しい箇所もあったが、興味深く聞いた。
椅子に座っている間中、養老先生がずっと脚を組んでいて、気になった。脚を組むのは骨盤に良くないということだが、きっと、そんなことは気にしないのかもしれないと思った。YouTubeでもよく脚を組む姿を見ているが、癖のように見える。
私も時々、つい、脚を組んでしまうが、
(骨盤がズレちゃう!)
と気づき、すぐ、やめる。
骨盤がズレると何故いけないのか具体的な理由は知らないが、ズレるのは良くないに決まっている。養老先生と違って私は筋肉も骨も弱いに違いないから、できるだけ脚は組まないようにしようと思っている。特に今後は加齢で筋肉も骨も弱くなったり減ったりしていくのだから気をつけなくては。
現在は幸運なことに肩も腰も膝も足も、筋肉痛は全然ない。肩凝り、腰痛、膝痛、脚痛のどれかがある人を周囲で何人か見ているが、辛そうである。けれど慣れてしまっているふうにも見える。
身体のどこにも痛みのない生活が、私にとっては平穏な日々を過ごせることになる。
さらに数年前から、食間が長時間の時の空腹感が強くなっても腹痛が起こらないのは、いいことだけれど、脳から司令が出なくなったのだろうか。それとも、自然治癒したのかもしれない。
最近、中村仁一医師の著書を2冊読んだ。著書の中に、
――自分の身体の不調や病気は自分の身体が自然に治す。自分の身体が治せない身体を他人の医者が治せるわけがない。自分の身体が治せない不調は病気ではなく老化である。――
というようなことが書かれていて、衝撃を受けたというか、発見したというか、驚愕させられた。もちろん自然治癒という言葉は知っている。
けれど――。
昨年、首の寝違いで生まれて初めて頭痛を経験した。あの頭痛だけは二度と経験したくない。肉体的にも精神的にも辛かったので病院へ行き、薬を処方されて飲んだら、首の筋肉の寝違いと共に頭痛も薄れ、数日間で完治した。
もし、徹底的に薬嫌い、病院嫌いだったら、病院へ行かず薬も飲まず、〈日にち薬〉で自然治癒したと思う。
〈日にち薬〉という言葉は、薬嫌いだった母がよく言っていたが、私もその言葉を信じている。〈日にち薬〉とは、日にちが経つことが薬、日にちがたてば治るという意味で、〈日柄〉という言葉も母はよく口にした。日柄とは大安・友引などその日の吉・凶のことの他、月日の意味もある。誰かが愚痴る腰痛とか風邪とか腹痛とか聞くと、いつも母は、「日柄よ、日にち薬よ」と言うのだった。本当に信じていて、自分の身体が不調の時も、日記にはそう書いてあった。風邪など不調だった日も、治った日にも書いてあるので、母らしいと思わずクスッと笑ってしまう。
けれど、昨年の初夏、母の言葉を何度も声と口調と共に思い出し、胸の中で呟いたが、日にちが経つその間中の精神的肉体的な辛さに耐えられなかった。だから、周囲から何と言われようと笑われようと、寝違いを治しに、初めて整形外科へ行って診察・レントゲン・薬の処方をして貰ったことは、私にとって正しい選択だったと今でも信じている。
――医療は利用するもの、医師の指示に唯々諾々(いいだくだく)と従う患者が多いが、医療の主役は医師ではなく患者で、医師は利用する存在である――
というようなことも、中村仁一医師の著書に書かれていて、印象に残った。
ともあれ、私の弱点は寝違い。寝違いだけは気をつけなければと、日々、自分に言い聞かせている。
2人の話は少し難しい箇所もあったが、興味深く聞いた。
椅子に座っている間中、養老先生がずっと脚を組んでいて、気になった。脚を組むのは骨盤に良くないということだが、きっと、そんなことは気にしないのかもしれないと思った。YouTubeでもよく脚を組む姿を見ているが、癖のように見える。
私も時々、つい、脚を組んでしまうが、
(骨盤がズレちゃう!)
と気づき、すぐ、やめる。
骨盤がズレると何故いけないのか具体的な理由は知らないが、ズレるのは良くないに決まっている。養老先生と違って私は筋肉も骨も弱いに違いないから、できるだけ脚は組まないようにしようと思っている。特に今後は加齢で筋肉も骨も弱くなったり減ったりしていくのだから気をつけなくては。
現在は幸運なことに肩も腰も膝も足も、筋肉痛は全然ない。肩凝り、腰痛、膝痛、脚痛のどれかがある人を周囲で何人か見ているが、辛そうである。けれど慣れてしまっているふうにも見える。
身体のどこにも痛みのない生活が、私にとっては平穏な日々を過ごせることになる。
さらに数年前から、食間が長時間の時の空腹感が強くなっても腹痛が起こらないのは、いいことだけれど、脳から司令が出なくなったのだろうか。それとも、自然治癒したのかもしれない。
最近、中村仁一医師の著書を2冊読んだ。著書の中に、
――自分の身体の不調や病気は自分の身体が自然に治す。自分の身体が治せない身体を他人の医者が治せるわけがない。自分の身体が治せない不調は病気ではなく老化である。――
というようなことが書かれていて、衝撃を受けたというか、発見したというか、驚愕させられた。もちろん自然治癒という言葉は知っている。
けれど――。
昨年、首の寝違いで生まれて初めて頭痛を経験した。あの頭痛だけは二度と経験したくない。肉体的にも精神的にも辛かったので病院へ行き、薬を処方されて飲んだら、首の筋肉の寝違いと共に頭痛も薄れ、数日間で完治した。
もし、徹底的に薬嫌い、病院嫌いだったら、病院へ行かず薬も飲まず、〈日にち薬〉で自然治癒したと思う。
〈日にち薬〉という言葉は、薬嫌いだった母がよく言っていたが、私もその言葉を信じている。〈日にち薬〉とは、日にちが経つことが薬、日にちがたてば治るという意味で、〈日柄〉という言葉も母はよく口にした。日柄とは大安・友引などその日の吉・凶のことの他、月日の意味もある。誰かが愚痴る腰痛とか風邪とか腹痛とか聞くと、いつも母は、「日柄よ、日にち薬よ」と言うのだった。本当に信じていて、自分の身体が不調の時も、日記にはそう書いてあった。風邪など不調だった日も、治った日にも書いてあるので、母らしいと思わずクスッと笑ってしまう。
けれど、昨年の初夏、母の言葉を何度も声と口調と共に思い出し、胸の中で呟いたが、日にちが経つその間中の精神的肉体的な辛さに耐えられなかった。だから、周囲から何と言われようと笑われようと、寝違いを治しに、初めて整形外科へ行って診察・レントゲン・薬の処方をして貰ったことは、私にとって正しい選択だったと今でも信じている。
――医療は利用するもの、医師の指示に唯々諾々(いいだくだく)と従う患者が多いが、医療の主役は医師ではなく患者で、医師は利用する存在である――
というようなことも、中村仁一医師の著書に書かれていて、印象に残った。
ともあれ、私の弱点は寝違い。寝違いだけは気をつけなければと、日々、自分に言い聞かせている。