「会長無謬神話」の崩壊を直視しよう
冨士大石寺顕正会向上委員会
冨士(創刊号)
妙信講再建当時、講中の様子がどんなものであったか、これからしばらく振り返ってみよう。
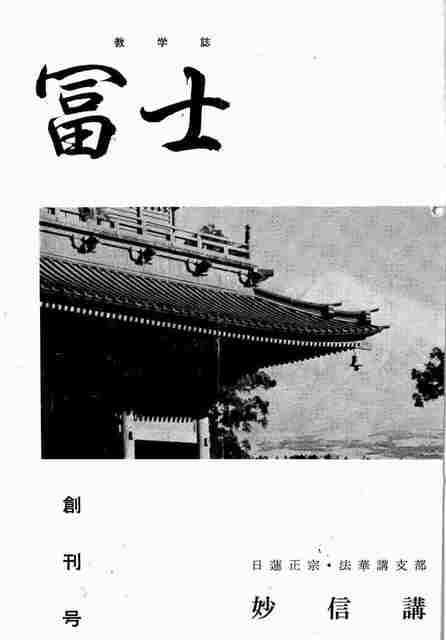
昭和36年の冨士(創刊号)と、顕正新聞(41号)が小生の手元にある。小生が入信する5年前の資料であるが、先輩諸氏からわたしに託されたものである。
昭和36年4月、細井日達上人は「事の戒壇とは富士山に戒壇の本尊を安置する本門寺の戒壇を建立することでございます。勿論この戒壇は広宣流布の時の国立の戒壇であります」(「大日蓮」一八三号)と指南した。
4月15日、教学部結成式が音羽の本部で開催され、浅井昭衛企画室長による六巻抄講義が始められた。
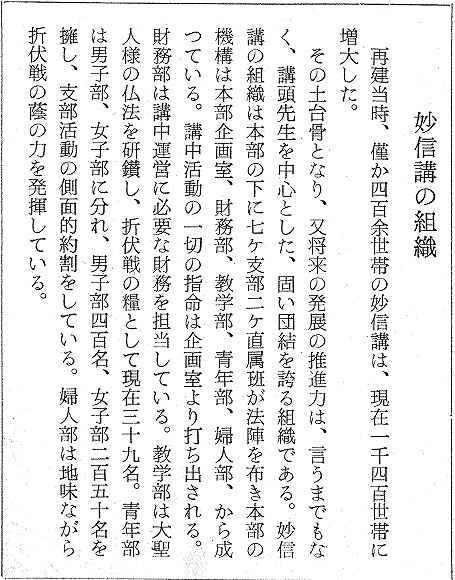
5月28日、妙信講は第七回総会を開催(千代田公会堂)、浅井企画室長は「使命あればこそ妙信講は試練に耐える。信心が仏意に叶えば必ず広布のお役に立つ」と講演した。
同月、創価学会は二百万世帯を達成した。池田会長は二百万世帯を背景に、「王仏冥合の実践の関所ともいうべき選挙戦は、日蓮大聖人の至上命令である」(「大白蓮華」一二一号、昭和三十六年六月)と述べた。
このとき妙信講は、1,400世帯となっていた。

9月1日、教学誌「冨士」が創刊された。
9月、法華講第一回全国連合登山会が挙行された。法華講連合会発足の、第一歩である。
11月、総本山の御会式に、妙信講員120名が参加した。
「妙信講の組織は本部の下に七ヶ支部二ヶ直属班が法陣を布き本部の機構は本部企画室、財務部、教学部、青年部、婦人部、から成っている」(冨士 創刊号) 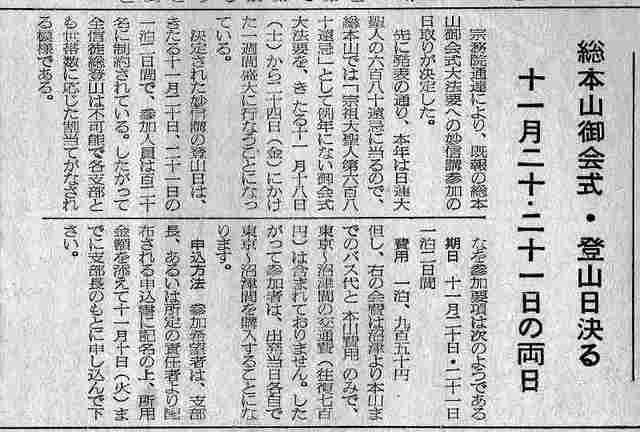
当時の妙信講では、講員はすべて各支部に所属し、支部長が組織運営の中核を担っていた。
しかしその後、浅井昭衛氏は支部を解体して四者体制に移行し、さらに壮年部を潰してしまった。
そして伝統ある教学部も、ひっそりと葬ってしまった。
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
| « 顕正会のタイ... | 二百万達成 » |





実は櫻川さんに教えて頂きたいことがありましてパソコンからメールしたのですが、何度送っても返送されてしまいました。( tadashi@sakuragawa.qee.jpです。)
やむなく携帯から送ってみましたが、私本人かどうかが判別がつかないかと思い(かつ携帯からも届いているかどうか不安)、こちらにコメントさせて頂きました。
大変お手数をかけて申し訳ないのですが、櫻川さんにご連絡の取れるアドレスを教えて頂けないでしょうか。
tochirou@rhythm.ocn.ne.jp
これは以前から私が使用しているアドレスなので、こちらに連絡可能なアドレスを送って頂けると非常に助かるのですが…。
お忙しい中を恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。
ご連絡いたします。(^^)