 奈良公園の鹿せんべいから、象牙やマンモス象の牙の鑑別の話になっていますが、脱線ついでにもう少し、分類というか、通関手続きと分析の話を続けます。
奈良公園の鹿せんべいから、象牙やマンモス象の牙の鑑別の話になっていますが、脱線ついでにもう少し、分類というか、通関手続きと分析の話を続けます。HSの分類表には、分類されないのは人間と空気ぐらいといわれるように、およそありとあらゆるものがルールに従って分類されます。空気も、アルプスの空気とかの缶詰が輸入されていると聞いたことがありますが、アルプスの空気と、アンデスの空気でHS番号が違うことはありません。
そこで分析のことに話題を戻すと、輸入品にはきちんと成分、組成、加工度合いなどを確定しないと、HSの分類を決めたり、輸入規制の該否を決定できないものが多々あります。
例を挙げると、
1 乳製品や・水産品、米粉製品、肉は、加工度合いや種類で関税率が違いますし、輸入制限に該当することもあります。
2 濃縮ジュースは糖分量、ミルクや米粉の調製品はたんぱく質・脂肪・糖質などで関税率が違います。
3 肉類は、輸入禁止の鯨肉と牛肉などとを、たんぱく質やDNAの塩基配列などで鑑別します。
4 木炭と活性炭、酸化アルミニウムと人造コランダムなどは組成元素やなどが一緒でも加工度合で関税率が違います。
:::::::::
このように、適切に関税率や規制を実行するため、現在全国の9つの税関には分析部門が置かれており、機器の配置の関係や習熟などの関係で中央分析所で対処すべきものは、千葉県の中央機関で分析をしています。
では、通関の実務ではどうなっているんでしょうか?
このような、分析をして確定することが適当な品目が輸入申告されると、逐一、通関を保留して税関の分析部門が分析し、その結果が出るまで引き取れないとなると、輸入者は困ってしまいますし、税関の分析官もたくさんが必要です。
このため、実際には、標準的な分析法で、輸入者本人か第三者に委託して分析した結果によってHS番号を決めて通関する「当事者分析」という方法が一般的に行なわれています。
この「当事者分析」は、あらかじめ税関の承認を受けて、輸入申告時に自分や委託して得た分析証明書を提出して通関する方法です。どの程度、この当事者分析が利用されているか分かりませんが、税関が、通関を保留して自ら行なうような分析は殆どないと想像できます。
但し、普段は、このような当事者分析の結果で通関しているが、時々、税関自らも、通関は保留せずに検証のための参考に分析することが行なわれています。
どうやら、このような税関の検証のための参考分析で、成分や加工度合が違うことが発見され、後で修正申告したり、更正されたりも有るようです。
//////////
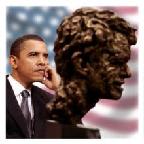 来週の火曜日は、米国大統領選挙です。オバマ候補が有力のようですが、意識してポーズを作っているのか、発言や、挙動には、J・F ケネデイを連想させるものがあるように感じます。
来週の火曜日は、米国大統領選挙です。オバマ候補が有力のようですが、意識してポーズを作っているのか、発言や、挙動には、J・F ケネデイを連想させるものがあるように感じます。



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます