6月22日(火)
津山洋学資料館へ見学に行ってきました
津山洋学資料館

「洋学ってなに?」
「西洋の学問」という意味ですが、「蘭学(らんがく)」といった方が分かりやすいかも知れません。オランダ(和蘭)語を使って研究する学問ですから、始まったころは「蘭学」と呼ばれていました。しかし、その研究の中身はオランダだけではなく、西洋の社会全体が生み出した、進んだ科学知識なのです。
みなさんがよくご存じの『解体新書』も元はドイツの医学書で、オランダ語に翻訳されたものをもとに、日本語に翻訳したのです。
津山に本格的に洋学を紹介したのは、江戸詰の津山藩医・宇田川玄随(うだがわげんずい)です。彼とその跡を継いだ玄真(げんしん)・榕菴(ようあん)は、いずれも洋学研究の大家で、彼ら三代によって日本に近代科学が紹介されたと言っても過言ではありません。また、津山出身の藩医で宇田川玄真に学んだ箕作阮甫(みつくりげんぽ)は、開国に迫られた幕末期の日本を学術・教養の面から支えました。彼の孫にも、幕末~明治の日本を代表する優秀な人材が数多くいます。
この宇田川・箕作両家の人々以外にも、たくさんの美作の洋学者たちが、さまざまな分野で活躍しています。ここに紹介しているのは、そのうちの一部分に過ぎません。
***優れた洋学者を生んだ津山***
古くから城下町として栄えた津山は、多くの洋学者を輩出した文化の地でもある。杉田玄白らの『解体新書』より十八年後、津山藩医宇田川玄随は、日本最初の西洋内科書『西説内科撰要』を訳述した。その子玄真は、江戸時代の解剖書では最も普及した『医藩提綱』のほか、多くの訳書を世に出した。さらに玄真の養子・榕菴も本格的な科学書『舎密開宗』、植物学書『植物啓原』を著わし、近代科学の生みの親と称されている。この宇田川三代に並び箕作阮甫は、幕府天文分訳員、続いて蕃書調所教授職となり、医学、語学、理学、地学など多くの著述を残した。また阮甫の養子・秋坪(しゅうへい)は、1861年福沢諭吉らとともに、幕府の開港延期交渉使節に随行してヨーロッパへ、1866年には樺太(からふと)国境交渉のためロシアへ出向した。
津山洋学資料館はこうした洋学者の関係資料を収集・保存・公開し、この業績の調査研究にあたっている。
(津山市観光協会 編 「津山観光必携」より)
津山洋学資料館は、今年3月の移転オープンから現在までに、市民や県内外の観光客の方々の入館が約8000人だそうです
現在、平成22年度企画展が開催されているので是非この機会にお越しください


*** ご存じでしたか!? ***
 津山洋学資料館には、あの有名な『解体新書』が展示されています
津山洋学資料館には、あの有名な『解体新書』が展示されています
 「珈琲」「酸素」「水素」「窒素」などの漢字をつくったのは、津山ゆかりの洋学者 宇田川榕菴なんです
「珈琲」「酸素」「水素」「窒素」などの漢字をつくったのは、津山ゆかりの洋学者 宇田川榕菴なんです
まだまだありますが、あとは津山洋学資料館で発見して学んでみてください
見学時間の目安:約1時間
※6月28日~7月2日(金)は、くん蒸作業のため休館されるそうなのでお気を付け下さい。


 ランキングに参加中
ランキングに参加中
↓↓クリックおねがいします


津山洋学資料館へ見学に行ってきました

津山洋学資料館

「洋学ってなに?」
「西洋の学問」という意味ですが、「蘭学(らんがく)」といった方が分かりやすいかも知れません。オランダ(和蘭)語を使って研究する学問ですから、始まったころは「蘭学」と呼ばれていました。しかし、その研究の中身はオランダだけではなく、西洋の社会全体が生み出した、進んだ科学知識なのです。
みなさんがよくご存じの『解体新書』も元はドイツの医学書で、オランダ語に翻訳されたものをもとに、日本語に翻訳したのです。
津山に本格的に洋学を紹介したのは、江戸詰の津山藩医・宇田川玄随(うだがわげんずい)です。彼とその跡を継いだ玄真(げんしん)・榕菴(ようあん)は、いずれも洋学研究の大家で、彼ら三代によって日本に近代科学が紹介されたと言っても過言ではありません。また、津山出身の藩医で宇田川玄真に学んだ箕作阮甫(みつくりげんぽ)は、開国に迫られた幕末期の日本を学術・教養の面から支えました。彼の孫にも、幕末~明治の日本を代表する優秀な人材が数多くいます。
この宇田川・箕作両家の人々以外にも、たくさんの美作の洋学者たちが、さまざまな分野で活躍しています。ここに紹介しているのは、そのうちの一部分に過ぎません。
***優れた洋学者を生んだ津山***
古くから城下町として栄えた津山は、多くの洋学者を輩出した文化の地でもある。杉田玄白らの『解体新書』より十八年後、津山藩医宇田川玄随は、日本最初の西洋内科書『西説内科撰要』を訳述した。その子玄真は、江戸時代の解剖書では最も普及した『医藩提綱』のほか、多くの訳書を世に出した。さらに玄真の養子・榕菴も本格的な科学書『舎密開宗』、植物学書『植物啓原』を著わし、近代科学の生みの親と称されている。この宇田川三代に並び箕作阮甫は、幕府天文分訳員、続いて蕃書調所教授職となり、医学、語学、理学、地学など多くの著述を残した。また阮甫の養子・秋坪(しゅうへい)は、1861年福沢諭吉らとともに、幕府の開港延期交渉使節に随行してヨーロッパへ、1866年には樺太(からふと)国境交渉のためロシアへ出向した。
津山洋学資料館はこうした洋学者の関係資料を収集・保存・公開し、この業績の調査研究にあたっている。
(津山市観光協会 編 「津山観光必携」より)
津山洋学資料館は、今年3月の移転オープンから現在までに、市民や県内外の観光客の方々の入館が約8000人だそうです

現在、平成22年度企画展が開催されているので是非この機会にお越しください



*** ご存じでしたか!? ***
 津山洋学資料館には、あの有名な『解体新書』が展示されています
津山洋学資料館には、あの有名な『解体新書』が展示されています
 「珈琲」「酸素」「水素」「窒素」などの漢字をつくったのは、津山ゆかりの洋学者 宇田川榕菴なんです
「珈琲」「酸素」「水素」「窒素」などの漢字をつくったのは、津山ゆかりの洋学者 宇田川榕菴なんです
まだまだありますが、あとは津山洋学資料館で発見して学んでみてください

見学時間の目安:約1時間
※6月28日~7月2日(金)は、くん蒸作業のため休館されるそうなのでお気を付け下さい。


 ランキングに参加中
ランキングに参加中
↓↓クリックおねがいします













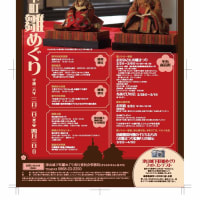









僕が入る前の作品ですが名作です。
上記 URLで大まかなあらすじは知ることができますよ(^^)
以前にそんな劇をしたんですね!?
ぜひ、また再演して欲しいです(^^)