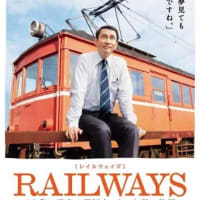通勤に利用する名古屋鉄道の電車での体験である。旅好きの私は、移り変わる景色を見て、毎日違った気付きを経験している。最近は景色が見える運転席の近くの座席に腰掛けるのが習慣になった。様々な運転手が一人で指差呼称しながら安全に電車を運行している。
昇進試験なのだろか、初老の太い金線帽子と若い細い金線の帽子の二人が運転席にいる。太い金線帽子の上司と部下なのだろう。部下が運転して、上司がチェックしている。させてみせているのである。
本日は上司が運転して、部下が動作を真似しているのである。珍しい光景で、熟練の運転技術である。やって見せている。無駄の無い動作で、余裕があり、乗り心地が良い。
教師役は命懸けで教え、生徒は真似しようとする真剣勝負を拝見すると、安全運転が確保されるだろうとの安心感が伝わる。運転技術の師事相承で地味な活動であるが、年功序列や終身雇用がまだ存在するのである。千日回峰等、行者の作法と同じに、末永く存続すると思う。古き善き日本の姿である。
そして民間航空機の機長は四条の金線の制服を着こなし、堂々とした態度を見ると無事に目的地に着ける安心感がある。制服の効用で、安全輸送の思想を具現化した形である。
山本五十六の語録の「やってみせ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば 人は動かじ」は私のお気に入りの言葉である。連合艦隊司令長官の山本元帥は終戦間際に、あえて敵に目立つ白の第一種軍装姿で航空機に搭乗、慰問の為に最前線に赴く時、敵の待ち伏せ攻撃で墜落死した。白色の制服は千日回峰行の死装束と同様に見えるのである。「米百俵の精神」による学校を卒業した山本元帥は死んだが、その魂は言葉で生き続けている。
「苦しいこともあるだろう 言いたいこともあるだろう 不満なこともあるだろう 腹の立つこともあるだろう 泣きたいこともあるだろう これらをじっと堪えてゆくのが 男の修行である」
地味で単純な活動を繰り返し実行した暁には、太い金線や四条の金線が似合う人間になり、世間から尊敬されるのである。
昇進試験なのだろか、初老の太い金線帽子と若い細い金線の帽子の二人が運転席にいる。太い金線帽子の上司と部下なのだろう。部下が運転して、上司がチェックしている。させてみせているのである。
本日は上司が運転して、部下が動作を真似しているのである。珍しい光景で、熟練の運転技術である。やって見せている。無駄の無い動作で、余裕があり、乗り心地が良い。
教師役は命懸けで教え、生徒は真似しようとする真剣勝負を拝見すると、安全運転が確保されるだろうとの安心感が伝わる。運転技術の師事相承で地味な活動であるが、年功序列や終身雇用がまだ存在するのである。千日回峰等、行者の作法と同じに、末永く存続すると思う。古き善き日本の姿である。
そして民間航空機の機長は四条の金線の制服を着こなし、堂々とした態度を見ると無事に目的地に着ける安心感がある。制服の効用で、安全輸送の思想を具現化した形である。
山本五十六の語録の「やってみせ 言って聞かせて させてみて 誉めてやらねば 人は動かじ」は私のお気に入りの言葉である。連合艦隊司令長官の山本元帥は終戦間際に、あえて敵に目立つ白の第一種軍装姿で航空機に搭乗、慰問の為に最前線に赴く時、敵の待ち伏せ攻撃で墜落死した。白色の制服は千日回峰行の死装束と同様に見えるのである。「米百俵の精神」による学校を卒業した山本元帥は死んだが、その魂は言葉で生き続けている。
「苦しいこともあるだろう 言いたいこともあるだろう 不満なこともあるだろう 腹の立つこともあるだろう 泣きたいこともあるだろう これらをじっと堪えてゆくのが 男の修行である」
地味で単純な活動を繰り返し実行した暁には、太い金線や四条の金線が似合う人間になり、世間から尊敬されるのである。