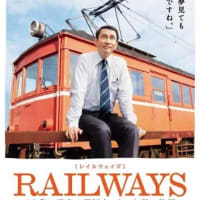市田柿は渋柿を冬の伊那谷の寒風にさらして乾燥させたドライフルーツである。柿は甘柿と渋柿がある。渋味成分は柿タンニンで、水溶性の時は渋く、加工して不溶性とすると、渋味が消滅する。甘柿は遺伝子DNAの指示で、収穫時には柿タンニンが不溶性になる。糖度を比較すると、渋柿の甘さが、甘柿に勝っている。
表面に白い粉が付着していることが多いが、これは柿の実の甘味成分であるぶどう糖が結晶析出したものである。援農ボランティアで農作業を手伝う市田柿は、柿色の果肉と白い糖の組み合わせの芸術品である。
干し柿に用いられる渋柿の主な品種は、種の多様性を司る遺伝子DNAの違いで、市田柿(長野県伊那谷)や紅柿(山形県上山市)、蜂屋(岐阜県美濃地方)、甲州百目(山梨県)などがある。甘柿の富有(ふゆう)・次郎は知名度がある。
脱渋の加工法は、市田柿、あんぽ柿の乾燥させる干し柿の他に、アルコール漬けにする樽柿や、温泉に入浴させる湯抜き、炭酸ガスによる大量に渋柿を加工する業務用の方法がある。冬の寒さの厳しい南信州伊那谷の正月に欠かせないご馳走が、市田柿である。
「桃栗三年柿八年、柚(ゆず)は九年の花盛り、枇杷(びわ)は九年でなりかねる、梅は酸い酸い十三年」といわれ、収穫するまでに時の経過が必要な、柿なのである。継続して農作業をする人がいなくなり、市田柿が消滅する事になれば残念である。
柿の渋が無くなると、元から存在する甘味成分が主役になる。同様に人は仏となる可能性を秘めているが、物質主義の強欲と利己心の渋を捨てれば、渋柿が甘くなるように、この世でこのまま仏になる。死んで仏になることは保証されているが、心掛け次第で、弘法大師空海の即身成仏が可能なのである。柿の渋抜きは簡単であるが、人間の渋抜きは、至難である。伝教大師最澄の言葉のように何世代も死に変わり、生まれ変わりを継続しないと、不可能である。私が、凡人であるのは、私の先祖の努力が、まだ不足しているのである。何世代か後には、きっと仏様のような子孫が現れることを夢見て、毎日を精進努力したい。
仏である自分に気づかず、迷い、悩み、苦しみの渋抜きが出来ずに、今の世が、極楽浄土であることに気が付かない私である。渋の抜けた市田柿は仏様なのであるから、大切に扱わなければならない。
柿を題材とした「青柿が熟柿弔う」という言葉がある。熟して落ちた柿の実を見て、まだ青い柿が「お気の毒に」と弔う。だが、その青い柿もいずれは熟して落ちる定めにある。人間はいつか死ぬ運命にあることを、熟柿から謙虚に知り、充実した残り少ない日々を過ごすことの大切さを学んだ。「散る桜、残る桜も、散る桜」と同様な、人生の機微に触れた名句で気に入っている。
正岡子規は「柿食へば 鐘が鳴るなり 法隆寺」
石田波郷は「柿食ふや 遠くかなしき 母の顔」
アルコールで渋抜きをする決意で、水割りのコップを積み重ねるが、なかなか渋が抜けない。温泉による渋抜きも考慮しながら、明日も継続して焼酎による渋抜きを誓い、心地よく酔っ払ったので寝ることにする。おやすみ。
表面に白い粉が付着していることが多いが、これは柿の実の甘味成分であるぶどう糖が結晶析出したものである。援農ボランティアで農作業を手伝う市田柿は、柿色の果肉と白い糖の組み合わせの芸術品である。
干し柿に用いられる渋柿の主な品種は、種の多様性を司る遺伝子DNAの違いで、市田柿(長野県伊那谷)や紅柿(山形県上山市)、蜂屋(岐阜県美濃地方)、甲州百目(山梨県)などがある。甘柿の富有(ふゆう)・次郎は知名度がある。
脱渋の加工法は、市田柿、あんぽ柿の乾燥させる干し柿の他に、アルコール漬けにする樽柿や、温泉に入浴させる湯抜き、炭酸ガスによる大量に渋柿を加工する業務用の方法がある。冬の寒さの厳しい南信州伊那谷の正月に欠かせないご馳走が、市田柿である。
「桃栗三年柿八年、柚(ゆず)は九年の花盛り、枇杷(びわ)は九年でなりかねる、梅は酸い酸い十三年」といわれ、収穫するまでに時の経過が必要な、柿なのである。継続して農作業をする人がいなくなり、市田柿が消滅する事になれば残念である。
柿の渋が無くなると、元から存在する甘味成分が主役になる。同様に人は仏となる可能性を秘めているが、物質主義の強欲と利己心の渋を捨てれば、渋柿が甘くなるように、この世でこのまま仏になる。死んで仏になることは保証されているが、心掛け次第で、弘法大師空海の即身成仏が可能なのである。柿の渋抜きは簡単であるが、人間の渋抜きは、至難である。伝教大師最澄の言葉のように何世代も死に変わり、生まれ変わりを継続しないと、不可能である。私が、凡人であるのは、私の先祖の努力が、まだ不足しているのである。何世代か後には、きっと仏様のような子孫が現れることを夢見て、毎日を精進努力したい。
仏である自分に気づかず、迷い、悩み、苦しみの渋抜きが出来ずに、今の世が、極楽浄土であることに気が付かない私である。渋の抜けた市田柿は仏様なのであるから、大切に扱わなければならない。
柿を題材とした「青柿が熟柿弔う」という言葉がある。熟して落ちた柿の実を見て、まだ青い柿が「お気の毒に」と弔う。だが、その青い柿もいずれは熟して落ちる定めにある。人間はいつか死ぬ運命にあることを、熟柿から謙虚に知り、充実した残り少ない日々を過ごすことの大切さを学んだ。「散る桜、残る桜も、散る桜」と同様な、人生の機微に触れた名句で気に入っている。
正岡子規は「柿食へば 鐘が鳴るなり 法隆寺」
石田波郷は「柿食ふや 遠くかなしき 母の顔」
アルコールで渋抜きをする決意で、水割りのコップを積み重ねるが、なかなか渋が抜けない。温泉による渋抜きも考慮しながら、明日も継続して焼酎による渋抜きを誓い、心地よく酔っ払ったので寝ることにする。おやすみ。