(3) 「動物歩きリレー」「折り返しリレー」
「動物歩きリレー」と「折り返しリレー」は、体育館で二教材を組み合わせて前後半で行います。運動量がかなりありますが、児童は喜んで取り組みます。
「動物歩きリレー」と「折り返しリレー」は、体育館で二教材を組み合わせて前後半で行います。運動量がかなりありますが、児童は喜んで取り組みます。
教育実習生の証言
「動物歩きリレー」
『体育館体育、一番はじめの授業が、この「動物歩きリレー」でした。子ども達が楽しそうに取り組んでおり、「私も将来、この教材を使わせて頂こう」と思い、印象に残っています。
1チーム4~5人という少人数であり、あざらし、クモ歩き、手押し車などが様々に組み合わされ子ども達が楽しみ、飽きず、かつ皆が常に動いていました。
また、全員が終わったら、整列し、手を挙げて順位をつけるということで、競争心もつきリレーにも熱が入る一方、整列もすばやくしっかりできるのだと思いました。
楽しみながらも、実は体はものすごく動いている、これが体育の基本なのだと感じました。』
(あ)「動物歩きリレー」
(A)「動物歩きリレー」の学習形式
ー四人一組のリレー形式ー

(補足1)「体をたがやす運動」
この運動を学んだ当時は「体をたがやす運動」と説明されていた。現代では、「体をつくる運動」になっているように感じられる。
(補足2)運動が心地よい
児童は、この運動が心地よいのか楽しいのか定かではないが、喜んで取り組んでいた。
(補足3)普段使わない部位もたくさん動かせる
普段使わない部位もたくさん動かせるように心がけた。
(B)学習の場

(補足4)バランスの取れた4人チームをつくる
背の順に4列を作ると、4人チームが背の高い者同士、背の低い者同士になってしまいます。2列はそのままで、残りの2列は背の高い者が先頭に来るようにするとバランスの取れた4人チームができます。
(C) 「動物歩き」の具体例
(ⅰ)手足走りり
手と足を使って4本歩行をします。
(ⅱ)前クモ歩き、後ろクモ歩き
「手足走り」を裏返しにした4本歩行です。頭方向に進むのが、後ろクモ歩き。足 方向に進むのが、前クモ歩きです。壁に向かっての「後ろクモ歩き」は、危険なので、例えば「走って行ってスライディングして壁にタッチしたら後ろクモ歩きで帰る」のように指示します。
(ⅲ)アザラシ
うつ伏せの姿勢から、上体を起こして腕の力だけであるきます。往復のアザラシ歩きは児童には無理があるので、「手足走りで行って、壁にタッチしたらアザラシ歩きで帰る」のように指示します。
(ⅳ)ワニ歩き
腹ばいになったまま、体をくねらせながらワニのように進みます。
(ⅴ)かた足けんけん
「右かた足けんけんで行って、壁にタッチしたら左かた足けんけんで帰ります」の ように使います。
(ⅵ)両足跳び
両足をそろえての「両足跳び」は、意外に難しいです。跳んで移動していると足が前後にばらけてしまいがちになります。
(ⅶ)ウサギ跳び
しゃがんだ姿勢から両足跳びで進みます。
(ⅷ)イモムシ歩き
しゃがんだ姿勢から、歩きながら進みます。
しゃがんだ姿勢から、歩きながら進みます。
(ⅸ)手押し車歩き
二人ひと組で、一人が腕立て伏せの姿勢になり荷車役になる。他の一人がその 両足を持って「荷車」を押すように前進する。壁にタッチしたら役割を交代してま た進む。
**持った両足を急に離すと、「荷車」役の児童は床に膝を打ちつけてしまい大けがになる恐れがあります。足の離し方を具体的に示して注意を喚起しておくことが必要です。
この他にもいろいろ考えられます。楽しい動き方を工夫してください。
高校柔道二連覇 神戸夙川高校柔道部
「”動物歩き”準備運動」の衝撃
2019年9月8日(日)放送のテレビ東京「YOUは何しに日本へ」で、紹介された兵庫県神戸市須磨学園夙川高校柔道部の練習風景は衝撃的でした。
夙川高校柔道部は、2019年世界柔道選手権大会金メダリスト阿部詩選手の母校で、2017年、2018年全国高等学校柔道選手権大会女子団体二連覇、2019年兵庫県高校大会個人戦7階級完全制覇の強豪校です。
練習は、「動物歩き」とよばれる準備運動から始まります。「クモ」「エビ」「逆エビ」「横エビ」「アザラシ」「ジャンプ」等の7種目を、30メートルの柔道場を1種目1往復するという約40分の激しい運動です。小学生の健康な生活をおくれるための「動物歩き」運動に慣れ親しんだ者には、競技で勝つための「動物歩き」は「衝撃」でした。フランスからこの高校に短期留学したアンジェル(16歳)は、「フランスでは実践練習しかしない。」といっていました。日本の高校生との練習試合では勝つことがある彼女も、この「動物歩き」は、ほとんどついていけない、真似できない状態でした。
内容の質がかなり違いますが、小学生も競技者の高校生も「体をたがやす」運動が必要であるという点で共通していると思いました。
「クモ」
夙川高校柔道部は、2019年世界柔道選手権大会金メダリスト阿部詩選手の母校で、2017年、2018年全国高等学校柔道選手権大会女子団体二連覇、2019年兵庫県高校大会個人戦7階級完全制覇の強豪校です。
練習は、「動物歩き」とよばれる準備運動から始まります。「クモ」「エビ」「逆エビ」「横エビ」「アザラシ」「ジャンプ」等の7種目を、30メートルの柔道場を1種目1往復するという約40分の激しい運動です。小学生の健康な生活をおくれるための「動物歩き」運動に慣れ親しんだ者には、競技で勝つための「動物歩き」は「衝撃」でした。フランスからこの高校に短期留学したアンジェル(16歳)は、「フランスでは実践練習しかしない。」といっていました。日本の高校生との練習試合では勝つことがある彼女も、この「動物歩き」は、ほとんどついていけない、真似できない状態でした。
内容の質がかなり違いますが、小学生も競技者の高校生も「体をたがやす」運動が必要であるという点で共通していると思いました。
「クモ」
「手足走り」の体勢から、手足の関節を伸ばしながら歩く。
「エビ」
「エビ」
仰向けの姿勢から、上半身と下半身をひねりながら頭の方向に、足で体を押して進む。
「逆エビ」
「逆エビ」
「エビ」運動で足方向に進む
「横エビ」
「横エビ」
「エビ」運動で、体は横向きになり横に進む。
「アザラシ」
「アザラシ」
うつ伏せの体勢で手を後ろで固定し、体をひねりながらかた足を使って進む。股関節の可動域を広げる運動。
「ジャンプ」
「ジャンプ」
仰向きの姿勢から、腕と足を上方に伸ばして浮き上がリながら足方向に進む。後半分は、頭方向に進む。
「クモ」「アザラシ」など小学生の「動物歩き」運動と名前は似ていますが、内容は全くちがいました。全体を通して体幹を鍛えながら、関節の可動域も広げているようです。
(D)結果の考察

(E) (研究を深めてくれる方募集)
「アザラシ歩き」などで手や腕だけを使って体を異動させる運動をすると、他の児童と比べて極端に腕の力が弱く、ほとんど体を動かせない児童がいます。そういった児童は、クラスの中でも他の児童との関わりがうまくいかないことが観察されました。しかし「動物歩きリレー」を1年間継続して行うと、運動面だけでなく精神面でも改善が見られることが複数のクラスで観察されました。
以上のことから、「腕の力と精神衛生」あるいは「動物歩き運動と精神衛生」等の研究に取り組んでくれる方がいらっしゃればうれしいです。
以上のことから、「腕の力と精神衛生」あるいは「動物歩き運動と精神衛生」等の研究に取り組んでくれる方がいらっしゃればうれしいです。
(い)「折り返しリレー」
(A)「折り返しリレー」の学習形式

(B)学習の場

(補足1)走る順番
①前の壁に向かって走り、壁にタッチしたら戻る。
②後ろの壁に向かって走り、後ろの壁にタッチしたら戻る。
③出発した所で次の走者にバトンパスする。
(補足2)走るコースを事前に指示
それぞれの列の走るコースを事前に指示してあげると、衝突の危険を減らすことができます。例えば、「自分の列の右側が、走るコースです」等。
それぞれの列の走るコースを事前に指示してあげると、衝突の危険を減らすことができます。例えば、「自分の列の右側が、走るコースです」等。
(C)結果の考察

《参考資料》
「ゴールしたら、全員で合図する」
順位を決める多くのやり方は、ゴールラインを最後の人が通過したときです。
しかしこの体育伝統的学習法では、「ゴールしたら全員で声を合わせて合図する。そして先生が、順位を言いう」と言う方法をとっています。ですから、先にゴールラインを通過してモタモタしていると合図が遅れ、順位が下がってしまうことがあります。
また、「順位が決まった後でもふざけたりしていると取り消しになることがある」ルールも伝えておきます。そのチーム全員の協力が必要になります。児童は率直ですから、順位を下げないためのチーワークは見事です。
小学校体育の「伝統的学習方法」で紹介した
①長なわ連続跳びゲーム
②動物歩きリレー
③折り返しリレー
等は、この方法で行っています。
ぜひ一度この方法を試してみてください。
しかしこの体育伝統的学習法では、「ゴールしたら全員で声を合わせて合図する。そして先生が、順位を言いう」と言う方法をとっています。ですから、先にゴールラインを通過してモタモタしていると合図が遅れ、順位が下がってしまうことがあります。
また、「順位が決まった後でもふざけたりしていると取り消しになることがある」ルールも伝えておきます。そのチーム全員の協力が必要になります。児童は率直ですから、順位を下げないためのチーワークは見事です。
小学校体育の「伝統的学習方法」で紹介した
①長なわ連続跳びゲーム
②動物歩きリレー
③折り返しリレー
等は、この方法で行っています。
ぜひ一度この方法を試してみてください。
《参考資料》 体育における運動量の持つ意味
(1)原点
自分自身の小学校時代の体育が、先生の説明や話し合いの時間が長過ぎ、動く量が少ないと子供心に感じていた。体育だからもっと動きたかった。
自分自身の小学校時代の体育が、先生の説明や話し合いの時間が長過ぎ、動く量が少ないと子供心に感じていた。体育だからもっと動きたかった。
(2)実践からの報告
①小学校の教員になってからは、児童の精神状態が体育の後落ち着き、雨の日には落ち着かないという現象を経験しました。そこで、体育館が比較的に開いている1時間目に体育館体育を設定して実践すると、その後の勉強がはかどることが分かりました。
②伝統的体育学習では、運動量がきちんと確保されていて成果が上がっていた。
「走り幅跳び」では、走ってきて両足でふみ切っていた児童が、たくさん経験することで自ら学び、「走ってきてかた足でふみ切る」ことができるようになりました。
「50m走」では、これまで全力で50mを走った経験がない児童が、50m走の体験を重ねるだけで記録を伸ばしています。 「動物歩きリレー」「折り返しリレー」では、筋肉痛になるくらい動いても全く文句は出ませんでした。児童の満足感を感じました
(3)日体大大学院生運動量調査 (注)
「50m走」では、これまで全力で50mを走った経験がない児童が、50m走の体験を重ねるだけで記録を伸ばしています。 「動物歩きリレー」「折り返しリレー」では、筋肉痛になるくらい動いても全く文句は出ませんでした。児童の満足感を感じました
(3)日体大大学院生運動量調査 (注)
町田市M小学校三年生2学級を、1996年に調査しました。体育授業が児童の心身にどのような変化を及ぼすのか、その差異について明らかにしようとしました。
調査対象のA組は体育が専門の筆者が担任する学級で、B組は体育が専門でない女性教員です。日本体育大学正木健雄教授に指導された大学院生平井貴子さん他大学院生、大学生10人ほどが調査を実施されました。そのチームワークと、手際の良さに感心させられたのを鮮明に覚えています。
調査対象のA組は体育が専門の筆者が担任する学級で、B組は体育が専門でない女性教員です。日本体育大学正木健雄教授に指導された大学院生平井貴子さん他大学院生、大学生10人ほどが調査を実施されました。そのチームワークと、手際の良さに感心させられたのを鮮明に覚えています。
(注)
「体育の授業における児童の心身の変化に関する研究ー小学3年生の場合ー」
平井貴子
平成8年度 日本体育大学大学院体育学研究科保健体育科教育学研究室修士学位論文集
(1997年3月10日発行)
(1997年3月10日発行)
①こころの変化(アンケートによる)
A組「いらいら」を低下させる、
B組「いらいら」を増加させる。
A組「いらいら」を低下させる、
B組「いらいら」を増加させる。
*体育をしても「いらいら」が増加することがあるという結果に驚きました。。いら いらしていては、「認め合い、高め合う心」も育ちにくいと思われます。
②ストレスが減る授業は、女子がよく動く。
*小学校の体育授業では、分からない、難しい教材に直面すると女子児童は動か ない、動けなくなることがよくあります
③体育授業中に占める活動時間の割合。
(高橋) 68.9%
A組 63.7%
B組 46.9%
(シーデントップ) 21-30%
(高橋) 68.9%
A組 63.7%
B組 46.9%
(シーデントップ) 21-30%
④体育授業中の歩数
(星川) 3212歩 (運動量を心掛けている学校)
1867歩 (一般の学校)
A組 3069.8歩
B組 2402.6歩
(星川) 3212歩 (運動量を心掛けている学校)
1867歩 (一般の学校)
A組 3069.8歩
B組 2402.6歩
* A組3069.8歩は、「動物歩きリレー」「折り返しリレー」を体育館で実施したときのものです。「作戦タイム」等をおりまぜながらも常に運動している授業でした。それと比較して、(星川)3212歩(運動量を心掛けている学校)は、驚異の歩数で、すごいり組みをしているなと感心しました。B組2402.6歩は、体育の専門知識が少ない教員が運動量を心掛けて行った授業として平均的な数字かと思われます。
⑤体育授業中の心拍数
(平均) A組152.66
B組141.84
(最高) A組208
B組206
B組141.84
(最高) A組208
B組206
(4)調査結果の感想
体育授業における運動量が心身の変化に大きな影響があることが分かりました。
「原点」で記した「先生の説明や話し合いの時間が長過ぎ、動く量が少ない。体育だからもっと動きたかった」という小学校時代の感想が、そのまま数値で表されたような研究でした。
「原点」で記した「先生の説明や話し合いの時間が長過ぎ、動く量が少ない。体育だからもっと動きたかった」という小学校時代の感想が、そのまま数値で表されたような研究でした。

















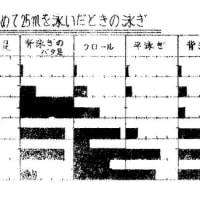

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます