前回の本ブログ
『ハードル走(4) ーハードルが怖いー』では、
「表現活動としてのハードル走」の練習過程として、「準備運動」と[1]「両足ふみきり、両足着地でとび」で、可能な限りハードルへの怖さをとる練習を紹介しました。
また練習課題の「3歩のリズム」では、ハードル間を3歩のリズムで走るリズムを体感できるようにしました。
今回は、 [2] 「かた足踏み切り、両足着地とび」です。
[2] 「かた足ふみ切り、両足着地とび」
① 「かた足ふみ切り」のとき、「ふり上げ足がまっすぐ足裏を見せるようにふり上げる」ようにするのが、今回の学習課題です。

② ①を行うと、「ハードルの遠くからふみきって近くに着地する」が自然にできます。

図 「遠くからふみきって、近くに着地する」
「ふり上げ足がまっすぐ足裏を見せるように」ふみきるためには、ハードルから少し離れてふみ切らないできません。ハードルに近くふみ切ると、ハードルにぶつかってしまいます。
③ 「両足ふみ切り、両足着地とび」で学習課題だった3歩のリズムは、できたことにしています。(できなくても、知識として理解できればOKとします)
④ハードルの歴史の追体験
1837年~1864年頃のハードル走は、「走ってきては両足で着地し、そのたびにスピードは完全に止まってしまい、また再び走り出す」というものでした。走ってきたスピードが、ハードルによって止められてしまうのは気持ちが良くないものです。
「かた足ふみ切り、両足着地とび」は、この頃の走り方を再現しています。
そして、次の練習段階「かた足踏み切り、かた足着地とび」を経験すると、スピードを止めない走りの素晴らしさが実感できます。
ハードル走の歴史の追体験です。
このブログのサッカー・ルールでは、歴史的な発展を追体験する方法を使うと、とても良く理解できりることを繰り返し説明しています。
『《参考資料》「ハードル走のうつりかわり」』(注)からは、以下のことが読み取れると考えます。
(注)次回の本ブログに掲載します
(あ)ハードル走の歴史の追体験
表現活動としてのハードル走では、
「両足踏み切り、両足着地とび」
「かた足踏み切り、両足着地とび」
「かた足踏み切り、かた足着地とび」
「カモシカとび」
「オリンピックとび」
の練習活動が、ハードル走の技術発達における歴史の追体験をすることになります。
①(1837年~1864年)「走ってきては両足で着地し、そのたびにスピードは完全に止まってしまい、また再び走り出す」は、練習活動「両足踏み切り、両足着地とび」「かた足踏み切り、両足着地とび」と共通します。
②(1864年~1877年)「ハードルを1台とび越すたびにスピードが完全に止まる走り方を改善しようと登場したのがセーリングフォームといわれる走り方です」は、練習活動「かた足踏み切り、かた足着地とび」の「カモシカとび」と共通します。
③(1886年~1908年)「ディップを開発することによって、ハードル走は「とび越す」ものから「またぎ越す」という考え方に変わった」は、練習活動「かた足踏み切り、かた足着地とび」の「オリンピックとび」と共通します。
(い)「セーリングフォーム」と「かもしか跳び」
「セーリングフォーム」と「かもしか跳び」は大きな部分では同じですが、振り上足の処理の仕方が少し異なります。
(う)セーリングフォームからディップへ
「セーリングフォーム」から「ディップ」技術への発展は、自然発生的な跳び方から人間の考え方が大幅に加えられた跳び方への転換で、大発見でした。 それだけに、一部の児童、生徒は理解しにくい面があるように思われます。そのために「かもしか跳び」と「オリンピック跳び」両方の跳び方を経験して、区別がしやすいように扱っています。
本ブログに掲載されている「ハードル走」に関係した記事です。
(1) 『表現活動としての 「ハードル走」」』
(その1)
(その2)
(2) 『ハードル走の学年別発達の研究ー1年から6年までの児童を「同一の方法」で指導した実践研究ー』
(その1)
(その2)
(その3)
(3)『小学校三年生のハードル走 ー発育、発達的観点からみた意味ー』
(4)『表現活動としての「ハードル走」』
何かのお役にたてば幸いです。

















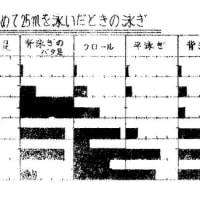

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます