(1)「ハードル走」教材を使って、1年から6年までの児童を「同一の方法」で指導したことがあります。(注1)
(注1) [実践研究] ハードル走の学年別発達の研究
ー1年から6年までの児童を「同一の方法」で指導した実践研究ー 」
「体育科教育学研究」日本体育科教育学会第16巻第2号1999年11月p27
(2)低学年の意欲の高さ、「もっととびたい、もっととびたい」に驚かされました。ハードルの質、高さを工夫すれば低学年の方が指導しやすいと感じました。
(3)高学年は身体能力は高いですが、「怖さ」がましてくる感じがしました。難しいことは高学年になってからという常識は、ハードル走に関しては少しちがうなと思いました。
(4)身体能力の発達と意欲の高さがちょうど良く合わさったのが三年生でした。このことを「三年生の発見」と表現しました。
(5)専科で空いた時間を利用して他学年の授業を受け持たせていただきました。児童へのアンケートは、全面的に担任の先生にお任せしました。
他学年の先生方のご協力なしにはできない実践研究でした。感謝の気持ちしかありません。またそれだけのゆとりが学校にあったということでしょう。
(6)論文が掲載されたときは、ハードル走教材は四年生以上からでした。この後しばらくしてから、三年生もハードル走教材を行うことになりました。
論文の中で、三年生の優秀さを取り上げていた筆者は、「やっぱり」と感じ、少しは決定に貢献できたかな思いました。
「三年生からはじめるハ-ドル走」は、伝統的教育技術になるでしょう。
(注2)
(注2)(参照)当ブログ 前掲
「3年生の発見 ーハードル走の学年別発達の研究(その1)ー」
「3年生の発見 ーハードル走の学年別発達の研究(その2)ー」
「3年生の発見 ーハードル走の学年別発達の研究(その3)ー」
『表現活動としての 「ハードル走」』

















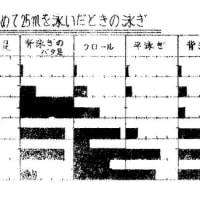

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます