日米衝突の根源 1858-1908/渡辺惣樹/草思社/2011
在野の研究者、渡辺惣樹が書いたアメリカの歴史書。
世界史の歴史教科書で学んだ、アメリカ史が如何に薄っぺらいものか驚くと同時に、アメリカ史について英語史料の原典に遡って調べで書いているはずの、世界史教科書執筆者たちの不勉強ぶりがわかる。
歴史教科書執筆者に読ませたいくらいの本である。
http://soshisha.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/--329e.html
〇米側資料によって明治期を読み解く
著者の渡辺惣樹氏はカナダ在住の在野の歴史研究家ですが、これまで看過されてきた英米の資料を使って日本の近現代史を見直すという構想のもと、『日本開国』を書き、『日本 1852』(チャールズ・マックファーレン著、初版は一八五三年刊)を翻訳し、草思社より上梓しました。『日本開国』はペリー艦隊を派遣したアメリカの目的が、中国市場に向けたシーレーンの確保にあったとの見方を示しました。本書はこれに続いて、一八五八年の日米修好通商条約締結から、一九〇八年、セオドア・ルーズベルト大統領が派遣した「白い艦隊〔ホワイト・フリート〕」の日本来航まで、半世紀にわたるアメリカの歴史を取り上げ、明治時代を「アメリカの歴史という燈火」に照らして読み解こうとするものです。内向きの歴史観ではとらえきれない明治期日本の姿を、米側資料を読み込む力量、経済に対する造詣、優れた筆力をもって浮き彫りにした画期的な「明治史」と言えます。
〇日米開戦はアメリカの宿命だった
アメリカではこの間、南北戦争、米西戦争、移民排斥、ハワイ併合、フィリピン領有と重大な出来事が起きています。これらを丹念にたどることで何が見えてくるのか。それは日本との衝突の不可避性です。この半世紀は、東部エリート(=WASP)をメインストリームとするアメリカが、フロンティアを貪欲に拡大し、イギリスの干渉を排除し、国内産業保護を主軸とするアメリカン・システムによって強力な国家建設に邁進し、やがてそこから人種問題、労働問題が派生し始める時代です。アメリカは中国市場でイギリスの優位に立つべく、新たなフロンティアたる太平洋の覇権を握らなければなりませんでした。その橋頭堡としてフィリピンを領有するのですが、このとき日本が、フィリピンを軍事的に脅かす可能性のある存在として立ちはだかってきたのです。一方の日本は海軍力こそアメリカをしのぐようになっていましたが、対米戦の意思など毛頭なかったことがわかります。のちの日米開戦の根源はこの時代のアメリカの国内事情、もっと言えばその行動原理そのものにあったことを明らかにした本書は、太平洋戦争の起源を日本にのみ求める通説に一石を投じるものであることは間違いないでしょう。
〇「ガラス細工の対日外交」が壊れるとき
ルーズベルト大統領はこのとき、国内の排日移民の動きを牽制し、ポーツマス講和で仲介の労をとる一方で「白い艦隊」を派遣し日本を威圧します。著者はそれを「ガラス細工の対日外交」と評し、大統領の真意は「アメリカの軍事力が優位になるまでは何としてでも日本との和平を維持する。そして必ずや訪れるであろう日本との衝突に備えて軍事力を強化する」ことにあったと「おわりに」で書いています。アメリカは日本との開戦をとっくの昔に想定しており、実際、一九〇四年には日本による米本土攻撃に備え、太平洋岸にコロンビア要塞を築いています。このガラス細工が壊れていき、日米衝突の悲劇へといたる経緯は著者の次の作品で詳しく描かれることになるのでしょう。
在野の研究者、渡辺惣樹が書いたアメリカの歴史書。
世界史の歴史教科書で学んだ、アメリカ史が如何に薄っぺらいものか驚くと同時に、アメリカ史について英語史料の原典に遡って調べで書いているはずの、世界史教科書執筆者たちの不勉強ぶりがわかる。
歴史教科書執筆者に読ませたいくらいの本である。
http://soshisha.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/--329e.html
〇米側資料によって明治期を読み解く
著者の渡辺惣樹氏はカナダ在住の在野の歴史研究家ですが、これまで看過されてきた英米の資料を使って日本の近現代史を見直すという構想のもと、『日本開国』を書き、『日本 1852』(チャールズ・マックファーレン著、初版は一八五三年刊)を翻訳し、草思社より上梓しました。『日本開国』はペリー艦隊を派遣したアメリカの目的が、中国市場に向けたシーレーンの確保にあったとの見方を示しました。本書はこれに続いて、一八五八年の日米修好通商条約締結から、一九〇八年、セオドア・ルーズベルト大統領が派遣した「白い艦隊〔ホワイト・フリート〕」の日本来航まで、半世紀にわたるアメリカの歴史を取り上げ、明治時代を「アメリカの歴史という燈火」に照らして読み解こうとするものです。内向きの歴史観ではとらえきれない明治期日本の姿を、米側資料を読み込む力量、経済に対する造詣、優れた筆力をもって浮き彫りにした画期的な「明治史」と言えます。
〇日米開戦はアメリカの宿命だった
アメリカではこの間、南北戦争、米西戦争、移民排斥、ハワイ併合、フィリピン領有と重大な出来事が起きています。これらを丹念にたどることで何が見えてくるのか。それは日本との衝突の不可避性です。この半世紀は、東部エリート(=WASP)をメインストリームとするアメリカが、フロンティアを貪欲に拡大し、イギリスの干渉を排除し、国内産業保護を主軸とするアメリカン・システムによって強力な国家建設に邁進し、やがてそこから人種問題、労働問題が派生し始める時代です。アメリカは中国市場でイギリスの優位に立つべく、新たなフロンティアたる太平洋の覇権を握らなければなりませんでした。その橋頭堡としてフィリピンを領有するのですが、このとき日本が、フィリピンを軍事的に脅かす可能性のある存在として立ちはだかってきたのです。一方の日本は海軍力こそアメリカをしのぐようになっていましたが、対米戦の意思など毛頭なかったことがわかります。のちの日米開戦の根源はこの時代のアメリカの国内事情、もっと言えばその行動原理そのものにあったことを明らかにした本書は、太平洋戦争の起源を日本にのみ求める通説に一石を投じるものであることは間違いないでしょう。
〇「ガラス細工の対日外交」が壊れるとき
ルーズベルト大統領はこのとき、国内の排日移民の動きを牽制し、ポーツマス講和で仲介の労をとる一方で「白い艦隊」を派遣し日本を威圧します。著者はそれを「ガラス細工の対日外交」と評し、大統領の真意は「アメリカの軍事力が優位になるまでは何としてでも日本との和平を維持する。そして必ずや訪れるであろう日本との衝突に備えて軍事力を強化する」ことにあったと「おわりに」で書いています。アメリカは日本との開戦をとっくの昔に想定しており、実際、一九〇四年には日本による米本土攻撃に備え、太平洋岸にコロンビア要塞を築いています。このガラス細工が壊れていき、日米衝突の悲劇へといたる経緯は著者の次の作品で詳しく描かれることになるのでしょう。













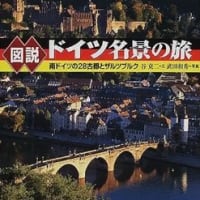
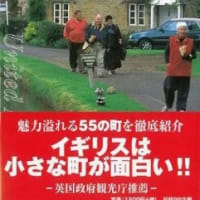
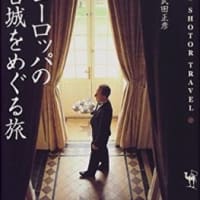
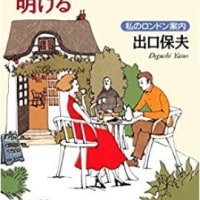
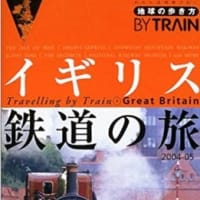







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます