数多くの施設患者に対応する在宅医療
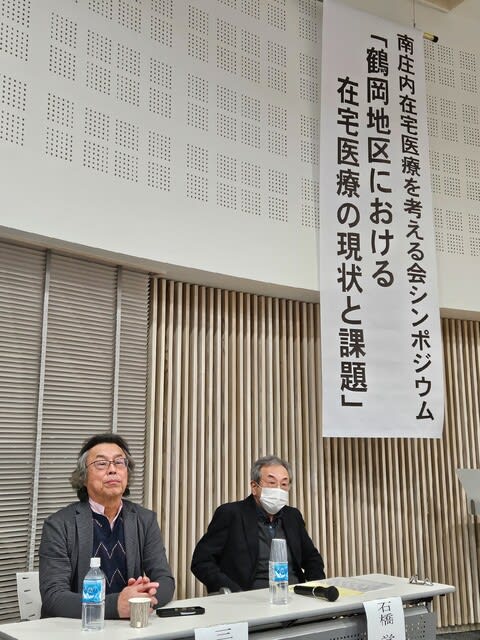



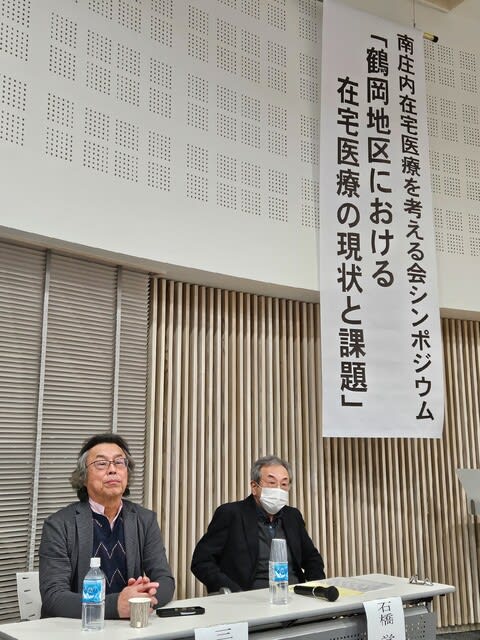



ほたる多職種研修会を開催しました。今回はヒアリングフレイルという目新しいテーマで、その概念の提唱者である中西 真一路 氏から、とても分かりやすく、貴重な講演を拝聴しました。
日時:R6年2月9日 18:45-20:15
場所:ニコフル
演題「ヒアリングフレイル ~高齢者の耳を学ぼう~」
包括的な地域医療のおけるNet4Uを活用の現状を寄稿文として書かせて頂きました。下記にアップロードしてあるようですので、参照下さい。▼HTML版 https://www.igaku-shoin.co.jp/paper/archive/y2024/3551_02 ▼PDF版 https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/7117/0599/3189/3551_02.pdf
12月9日、東京第一ホテル 鳳凰の間
荘内病院が主催して、地域医療連携推進協議会・鶴岡地区医師会・登録医・荘内病院 合同懇談会が開催されました。
病院、医師会、歯科医師会、薬剤師会から70名程の出席がありました。
第一部の話題提供として
1「当院腹腔鏡手術の現状と展望」
荘内病院産婦人科主任医長兼婦人科医長 矢野亮氏
腹腔鏡手術は、開腹手術に比較して圧倒的に患者にメリットがあり、今後進めていくべき手技、
一方で、山形県の産婦人科内視鏡技術認定医は7名(荘内病院2名)、腹腔鏡認定研修施設は3施設のみであり、他県に比し非常に少ないのが現状である。2020年に荘内病院は山形大学に次いで県内2施設目である認定研修医となった。2022年では子宮全摘の9割以上が腹腔鏡で行われ、全体の腹腔鏡手術件数は73件であった。2023年んからは、国立がん研究センター東病院との連携のもと、全国でも先駆的な取り組みである遠隔アシスト手術が開始された。一方で、糸球体癌に対する腹腔鏡手術は施設基準を満たしておらず、今後の課題である。今後、荘内病院が婦人科領域の県内における腹腔鏡手術の指導的役割を担っていきたい。
2「当院における骨粗鬆症遅漏の現状と課題」
荘内病院整形外科副主任医長 土屋潤平氏
骨粗鬆症は放置することで、骨折のリスクとなる。高齢者の骨折は寝たきりへのきっかけとなることが多く、予防すべきである。
予防薬の第一選択はビスホスホネート製剤であり、閉経~70歳までの比較的若年者には選択的エストロゲン受容体作動薬を、重症骨粗鬆症と判断した場合には、副甲状腺ホルモン製剤や抗スクレロチン抗体製剤を推奨している。
骨粗鬆症と骨折予防を継続していくためには、整形外科医師単独では限界がある。そのためFLS(Fracture Liasion Service、骨折リエゾンサービス)を立ち上げ、多職種連携による治療、服薬、説活指導を行う取り組みを開始している。
3「MRONJ(薬剤関連顎骨壊死)予防に向けて医歯薬連携の取り組みについて」
荘内病院歯科口腔外科副主任医長 武石 越郎 氏
MRONJを年間数例経験する。
ビスホスホネート製剤内服+抜歯で顎壊死へ至る例が典型であるが、それ程多い疾患ではない。
歯槽膿漏~歯周病など感染病変が契機になるので、十分な観察が重要である。
そのためには、ビスホスホネート製剤を内服しているという注意喚起が必要であり、
ビスホスホネート製剤内服患者には、それと分かるようなシールをお薬手帳に薬局で貼布する取り組みを開始した。
<懇親会~二次会>
病院の先生たちを交えて、楽しい時間を共有しました。
付記
荘内病院は地域医療支援病院には、地域の連携を推進するための協議会設置が義務付けられています。この会は、連携推進協議会の活動の一環として行われいます。
地域医療支援病院とは、
患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を行い、かかりつけ医等への支援を通じて地域医療の確保を図る病院として、平成9年の医療法改正において創設(都道府県知事が個別に承認)。※承認を受けている病院(令和5年9月現在) … 700
趣 旨
• 紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む)
• 医療機器の共同利用の実施
• 救急医療の提供
• 地域の医療従事者に対する研修の実施
主な機能
• 開設主体:原則として国、都道府県、市町村、社会医療法人、医療法人等
• 紹介患者中心の医療を提供していること。具体的には、次のいずれかの場合に該当すること。
ア)紹介率が80%以上であること
イ)紹介率が65%以上であり、かつ、逆紹介率が40%以上であること
ウ)紹介率が50%以上であり、かつ、逆紹介率が70%以上であること
• 救急医療を提供する能力を有すること
• 建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること
• 地域医療従事者に対する研修を行っていること
• 原則として200床以上の病床、及び地域医療支援病院としてふさわしい施設を有すること 等
医師会、歯科医師会、薬剤師会、荘内病院、鶴岡市、三川町、庄内保健所、ほたる による定例合同ミーティング。
医学書院から発刊されている「週刊医学会新聞」に、先日埼玉で開催された第23回日本クリニカルパス学会学術集会の模様が報告された(添付画像)。内容は、当地区の地域連携パス推進協議会のパスマネジャである三原美雪氏も登壇したパネルディスカッション「うちでは、これもパスです!」の報告であった。
以下、新聞からの抜粋。
最後に登壇した三原美雪氏(三原皮膚科)は、山形県鶴岡地区の地域共通電子カルテシステム(Net4U)を活用した地域一体型NST「たべるを支援し隊」の活動を紹介。「たべるを支援し隊」は医療系専門職のほか、保健所職員から構成されており、電子カルテを地域で共有して最終アウトカムをめざし活動している。氏は、「パス表という形式をとっていないが、まさしくパスの概念に則った活動であり、これもパスの一つのかちである」と述べ講演を締めた。
12月12日、第43回 市町長・部課長、庄内保健所、荘内病院、こころの医療センター、医師会役員懇談会が開催されました。鶴岡地区医師会からは「南庄内在宅医療を考える会」の紹介をさせて頂きました。
M

以下、在宅医療を考える会MLへの投稿、
12日に開催された五者懇談会での在宅医療を考える会の報告ですが、遠藤さんがプレゼン予定でしたが、発熱とのことで私から急遽発表させて頂きました。冒頭に、在宅医療が必要な背景を鶴岡市の今後の人口推移予測をデータで示し解説しました。その後、遠藤さんがつくってくれたパワポで、在宅医療考える会の歴史、理念、取り組んできたテーマ(とくに在宅看取り相互支援システム)、最後に先日行った訪問看護師との意見交換会でのトピックを示しながら、在宅医療現場での困難感や課題などについて説明させて頂きました。結構反応は良かったと思います。
昨日(12月7日)、表記会議がオンラインで開催されました。
来年、地域保健医療計画が見直されますが、そのなかの在宅医療関連部門を議論検討する会議です。参加者は、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町など医療、看護、介護などの関係者と山形県、保健所など行政側から30名程参加しての会議でした。
次期計画策定での主な追加項目
・在宅医療のおいて積極的役割を担う医療機関
・在宅医療に必要な連携を担う拠点
鶴岡市医療と介護の連携研修会は、15年程前から鶴岡市が主催し始まった研修会で、主な目的は病院と介護との連携推進でした。その後、参加職種が増え、コロナ禍前には、220名を超える程の参加者がありグループワークの場所を確保するのも大変な状況でした。
コロナ禍で開催できない時期が続きましたが、今年は、4年ぶりに対面での研修会を開催することができました。本年度は、コロナの状況も鑑み、基本的に病院とケアマネに限定した会としました。それでも、70名を超える皆さんに集まって頂きました。参加者内訳 ケアマネ:45名、社会福祉士(MSW):8名、病院看護師:9名、保健師:4名などです。
私の冒頭のあいさつでは、2040年問題に触れ、今後、85歳以上の高齢者がさらに増加し、一方で、これからの15年で、現役人口(20-65歳)が1000万人も減少するという現実を述べ、医療・介護従事者には厳しい時代を迎える。これを解決するキーワードは、「多職種・多施設連携」と「ICTの活用を含む情報共有」であることを述べました。
次いで、山形県立保健医療大学看護学科の菅原京子教授から基調講演をいただき、下記3つのテーマに沿った、グループディスカッションを行いました。