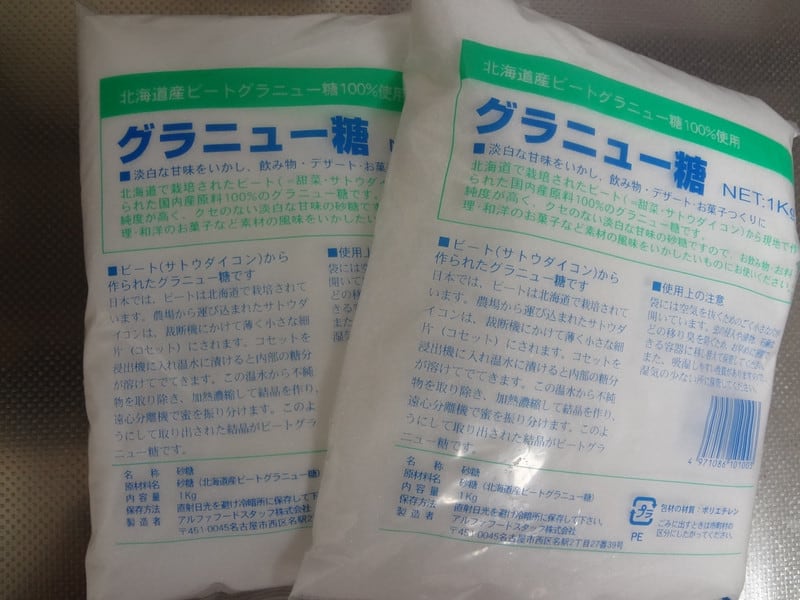今年も10株くらい、唐辛子(品種は鷹の爪)を栽培して、無事青唐辛子を収穫することができました。今年もできはよく、ぷりっぷりのいい実になりホクホクしていました。
鷹の爪は完熟させると赤唐辛子で一年保存でき薬味として欠かせないものだし、青いうちに使えば三升漬けや柚子胡椒、青南蛮の甘酢漬けの材料にもなってくれて本当に使える素材なんですよね。
毎年8月くらいのまだ青い唐辛子を収穫して、三升漬けを仕込み、これからあたらしく出てくる実は完熟させて秋に第2弾で赤唐辛子として収穫します。
三升漬けは、もう何年も前に福島県郡山ご出身の医学博士の渡部和男先生(元浜松医科大学)から、東北の郷土調味料で「すごく辛いよ~ふふふ」と先生手づくりの(もちろん青唐辛子もご自身で栽培されたものです)三升漬けをいただいたことがあり、あまりの汎用性の高さに驚愕しました。
すごく辛いので一度に使うのはほんのちょっとなんですが、なんとも芳醇でまろやかでいてさわやかな辛みがあって、タレや、下味付け、うどんなどの薬味、煮込みや炒め物の辛み付けなどなんでも使えてしまい、以降わたしは毎年自分の畑で唐辛子を栽培して夏になると麹と醤油を用意して三升漬けを漬けるようになりました。

今年は三升漬け用に、岩手の生麹をつかってみました。やはり東北がルーツのものなので、東北の麹使ってみたいな~なんて思って♡
「三升漬け」は、その名前の通り、1升、1升、1升で漬ける…という感じで青唐辛子と麹と醤油の割合を1:1:1で仕込めばいいだけなのです!
だから仕込むのは至極簡単です!!!!

青唐辛子をよく洗いヘタを取り、5ミリ以下に刻みます。(手に青唐辛子の汁がつくと手から辛みが取れなくて、その手で目などこすろうもんなら目がひりひりしてしまうので必ずポリ手袋などで防御して刻んでいます。)

刻んだ青唐辛子は、手でよくほぐしておいた麹とよく混ぜ合わせます。これも直手で触らず木ベラなどで…。

清潔な保存容器に青唐辛子と麹を混ぜたものを入れ、醤油を静かに注ぎます。
…これを1日2~3回優しく混ぜていると1週間程度でバラバラだった素材がとろ~んと混ざり合い、発酵が進み混然一体となります。

これは2日目くらいの姿。上の方にちょっと液が上がってきて、発酵が進みガスが発生してかすかに空洞ができるようになります。

これは5~6日経った姿です。夏なので発酵が早いです。空洞がかなりできていて…

上の表面はこんな感じで汁気が広がっています。
空洞や液体など全部が一体となるように木ベラなどを使い、都度、やさしくやさしく混ぜ合わせていきます。
とろんと溶け合い、芳醇でいい香りがしてもういいな!と思ったら、保存用の清潔な容器に移します。

今年は青唐辛子、麹、醤油をそれぞれ600gずつで仕込んだので合計1800g、1升の三升漬けが完成しました。冷蔵庫で一年保存してます。冷蔵庫でも発酵が少しずつ進むのでだんだんまた美味しくなります。
なんでも仕込み立てって、塩角があるというか、味がばらけているというか、美味しくなく感じる時ありますよね。わたしも仕込みたてよりもそれから1~2ヶ月くらい経った方が好きなので、もう使えるんだけどあと1~2ヶ月冷蔵庫で寝かせてから使おうと思っています。
昨年仕込んだやつもあとちょっと残っているので…♡
この量で我が家の一年分です。すごく辛いので毎回ちょっとずつしか使わないのでこれで我が家は十分もちます。
…三升漬けが来てから、我が家はあまりほかの辛み調味料を使わなくなりました。意外なくらい、なんにも要らないです。
ベーコンエピを作る時のコショー、ホットドッグを作る時のマスタードがたま~にほしいな~って思うくらいですかね~?
このような遠い地方の伝統的な調味料を教わることができて本当に幸運だったなと思い毎年先生に感謝しつつ仕込ませていただいています。
先生は現在各務原で「各務原カンファレンス」を主催されていて、化学物質過敏症などの患者さん方の相談にのられたり、関連書籍の執筆などをされてみえます。
先生も今年も仕込まれたかな~??