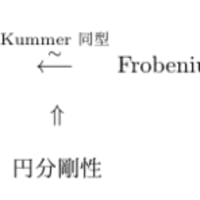原文のGoogle翻訳抜粋+筆者の補足。別記事チャーチルという名の災厄⊃背景から リンク。
# 実勢価格ではなく戦前の金価格でポンドと金の交換を再開=ポンドの10%切り上げ
「戦前の金の価値より約 10 パーセント低いポンドの外国為替価値を、戦前の金の価値まで
引き上げる政策」=「為替レートを 10 パーセント引き上げる政策」
→「我が国の輸出産業のポンド収入を 10 パーセント削減することを意味」
「国内産業の賃金と費用が全体的に 10 パーセント下がらない限り、価格を 10 パーセント
下げることは不可能」←前提の実現を目指すデフレ政策は、多大な社会的軋轢を招く
# ポンドの10%切り上げはデフレを招く
「為替レートを 10 パーセント改善するという政策は、遅かれ早かれ、すべての人の賃金を
1 ポンドあたり 2 シリング削減するという政策」←当時1 ポンド=20 シリング
「ポンドの国際価値を上げる→国内と海外の価値の既存の格差を大幅に悪化させる」
∵「デフレに私たちを陥れることで、国内の資本拡大の積極的な措置、たとえば国内産業
への労働力の移転を促進する措置を必然的に延期」
# ポンド切り上げの結果であるデフレは社会的不公正と経済の衰退を招く
「チャーチル氏がしたことは、単にトラブルを招く…愚かなこと」
∵「残りの国民のポケットから 10 億ポンドほどが利子所得者のポケットに」+
「国債の実質負担が 7 億 5 千万ポンドほど増」←↑高金利→↓投資目的のポンド買い
## ∵金本位制での高過ぎるポンド価格→貿易赤字での金流出相殺のため高金利が必要
+「貿易収支の赤字←わが国の物価が高すぎる」
→「物価を下げる←高値を付けたお金と信用を制限(=金融引き締め⊃高金利政策)」
→「名目賃金を下げ、それを通じて生活費を下げる」=「失業を意図的に激化させる」
∵「信用制限」→「現在の価格と賃金の水準で労働者を雇用するための資金を奪う」
=「イングランド銀行は、金本位制のルールにより、信用を縮小」→「失業の激化」
## 高金利政策を取らなければ→貿易赤字での金の流出が続く→保有する金が枯渇
→「強者と弱者への不平等な影響」+「経済的および社会的浪費」∵労働力の不使用
## 金本位制下での「自動調整」への盲目的信頼は、↓支配層の無知と傲慢の所産
「金本位制は、純粋な偶然に依存」+「システムの最上層に座る人々の象徴/偶像」→
「(支配層の)漠然とした楽観主義『本当に深刻なことは何も起こらない』→非常に無謀」
∵「自動調整」への盲目的信頼←「社会の詳細を無視」←↑cf. 小栗上野介の警句
# デフレを止めるにはポンド切り上げの撤回による緩和的な信用政策が急務
「1925 年の予算で発表された金融政策(ポンド切り上げ)が我が国の産業問題の本当の
原因であるため、それを逆転させる以外に本当に満足のいく方針を推奨することは不可能」
「繁栄を取り戻すために必要なのは、緩和的な信用政策」
∵「我々は、ビジネスマンが新しい事業に参入することを奨励したいのであって、
現在行っているように、彼らを思いとどまらせたいのではない。デフレは賃金を
「自動的に」減らすわけではない←失業を引き起こすことによって賃金を減らす」
「デフレは、ほんの少し始まっただけでも、累積的に進行」
∵「経済界で悲観論→お金の循環の遅れ→デフレをはるかに進めてしまう」
# まとめ
「貨幣価値の意図的な変更(現在の政策)」←「正義と便宜の反対」=不公正で愚劣
∵「現在の政策=他の理由から緩和されるべきときに信用を厳しく管理→意図的に失業を
激化させ、経済的必要性という武器を使って個人や特定の産業に対して調整を強制」
## 主流派経済学の仮定(=市場での価格調整だけで経済は安定する)は単なる幻想
最近の「経済」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事