中小企業診断士試験、経済学・経済政策の科目から一つ。
貨幣需要の動機について。
マクロ経済学では、資産を、収益を生む資産と収益を生まない資産の大きく2つに分類して考えることが多い。通常、収益を生まない資産を総称して貨幣とよぶ。また、収益を生む資産およびその収益率を、それぞれ債権、利子率とよぶ。
収益を生まない資産である貨幣を、あえて需要しようとする理由には、①取引動機、②予備的動機、③投機的動機があると考えられている。
①取引動機とは「取引の量が増加すれば、支払いなどにあてる貨幣が必要になり、需要を増やそう」とすることを意味する。②予備的動機とは「将来に予期せぬ事態に備えるために貨幣を必要とし、需要を増やそう」とすることを意味する。これら、取引動機と予備的動機の2つをまとめて「取引需要」とよび、貨幣の取引需要は“国民所得”の増加関数(所得が増えれば貨幣の需要が増える関係)となる。
また、③投機的動機とは「ケインズが流動性選好理論として提示した考え方で、“利子率”が低く(高く)なることで貨幣の取引需要が増加(減少)する」ことを意味する。
以上をまとめると、
取引需要:国民所得が増加⇒貨幣需要が増加
投機的動機:利子率が減少⇒貨幣需要が増加
となる。
貨幣需要の動機について。
マクロ経済学では、資産を、収益を生む資産と収益を生まない資産の大きく2つに分類して考えることが多い。通常、収益を生まない資産を総称して貨幣とよぶ。また、収益を生む資産およびその収益率を、それぞれ債権、利子率とよぶ。
収益を生まない資産である貨幣を、あえて需要しようとする理由には、①取引動機、②予備的動機、③投機的動機があると考えられている。
①取引動機とは「取引の量が増加すれば、支払いなどにあてる貨幣が必要になり、需要を増やそう」とすることを意味する。②予備的動機とは「将来に予期せぬ事態に備えるために貨幣を必要とし、需要を増やそう」とすることを意味する。これら、取引動機と予備的動機の2つをまとめて「取引需要」とよび、貨幣の取引需要は“国民所得”の増加関数(所得が増えれば貨幣の需要が増える関係)となる。
また、③投機的動機とは「ケインズが流動性選好理論として提示した考え方で、“利子率”が低く(高く)なることで貨幣の取引需要が増加(減少)する」ことを意味する。
以上をまとめると、
取引需要:国民所得が増加⇒貨幣需要が増加
投機的動機:利子率が減少⇒貨幣需要が増加
となる。










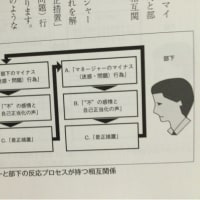








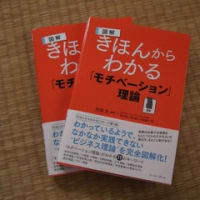
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます