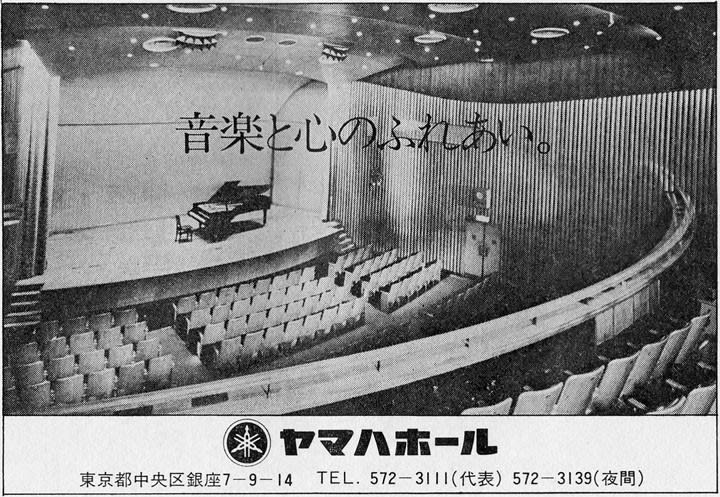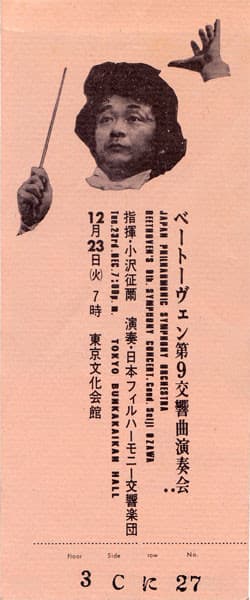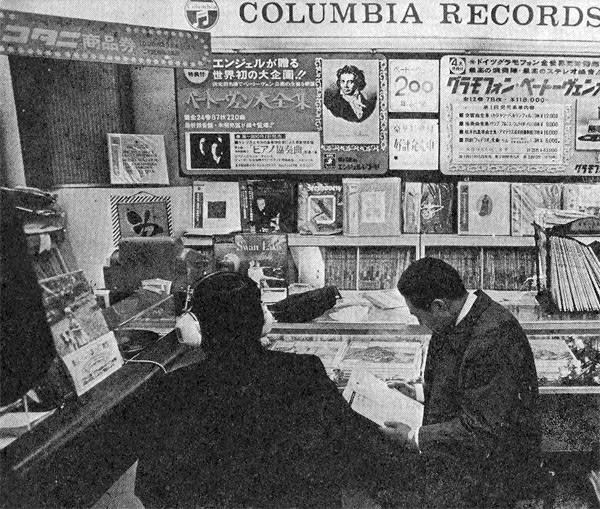ブルックナーが1873年にワーグナーの家に第2番と第3番の楽譜を持っていって、結局ワーグナーは3番の献呈を受けることになったんだけど、ワーグナーにすすめられるままビールを飲んだブルックナーはベロベロに酔っぱらってしまいどっちの交響曲か忘れてしまった。
そこでブルックナーは「トランペットで始まるほうでしょうか?」とワーグナーにあたらめてきいたところ、ワーグナーから「そうです!」と返事があった。。という話は有名ですよね。でも、なんとなく作り話っぽい感じもしていました。
ところが、そのやり取りの手紙の画像がHans-Hubert Schönzelerという人のブルックナー本(1970年)に載っていました。

Symfonie in Dmoll, wo die Trompete das Thema beginnt.
A Bruckner
Ja! Ja! Herzlichen Gruss!
Richard Wagner
トランペットで主題が始まるニ短調交響曲でしょうか。
A・ブルックナー
そうです! そうです! 心からよろしく!
リヒャルト・ワーグナー
。。。一枚の便箋にワーグナーとブルックナーのサインが入ったこの手紙、きっと値打ちもんですよね。
それとWikipediaによるとこの紙は「ホテルに備付けられた便箋」ということですが、左上の文字を見ると"Hotel Goldener Anker Bayreuth"のようです。現存するんですね。

もし将来バイロイトに旅行することがあったりしたら、ブルックナーがこの手紙を書いたホテルに宿泊してみたいです。
(2015年7月1日の記事を一部変更しました)