
AIJ問題は必然だった――問われる企業年金運用
2012-03-06
http://www.morningstar.co.jp/stock/analyst/2012/1q/STA120120306.html
AIJ投資顧問による企業年金資金の巨額消失事件を通じ、改めて日本の弱点が露呈された。
実質的な詐欺行為そのものはともかく(詐欺はいつの時代にも、どこの国でも存在する)、
問題は被害がここまで広がった原因と考えられる、ゆがんだ企業年金の構造だ。
また、投資顧問業者の一斉調査が実施された影響が、思わぬ形で株式市場に波及している可能性がある。
金融庁から業務停止命令を受けたAIJは、これまで虚偽の運用実績を掲げ、
多くの事業法人や企業年金基金と投資一任契約を結んできた。オプション取引を駆使し、
リーマン・ショックや震災による混乱の最中にも安定的に収益を伸ばしていたと、表向きにはされていたのだから、
いかにも有力な委託先に映ったのだろう。昨年末時点の運用額は2,000億円を超え、顧客の数は100に迫るという。
年金担当者はプロじゃない
しかし、勝ち続けるファンドなどそうはない。年間最大240%をうたう異常なパフォーマンスを、なぜもっと疑わなかったのか?
企業年金の担当者に今さら問い詰めても無駄だ。
そもそも、彼らは金融のプロではない(金融商品取引法の下では「プロ」とみなされるのだが)のだから。
被害の多かった、中小同業者が集まる総合型の厚生年金基金の場合、
主なメンバーは基金を構成する企業のOBや官庁出身者。
企業年金向けの営業を担当していたある大手運用会社の関係者は、
「ほとんどが資産運用とは縁のない部署でサラリーマン人生を送ってきた人たち。金融の知識は乏しい」とする。
素人同然の企業年金を甘い話で釣り、資金をかき集める。
そんな手口がまかり通ったのは、適材探しよりも、まずは身内を優遇する文化、
天下りにも通じる日本社会の体質が背景にある。
もちろん、それを放置した当局の責任も大きい。
実際AIJは、細かなデューデリジェンス(投資対象の適格性調査)を求める相手を避けたという。
仕手株暴落の序章?
一方、今度の件に対する株式市場の反応は一見薄い。だが、別の見方もできる。
最近、いわゆる仕手系材料株の一角の下げが目立つが、これをAIJ問題と関連付ける声がある。
投資顧問業者に詳しいある情報ベンダーの関係者は、
「業者の一斉調査に発展したことで、保有理由が説明しにくい高リスク銘柄を処分する動きにつながったのではないか」と話す。
透明性が今後厳しく要求されそうな状況で、投機的な資産は敬遠されるというわけだ。
また、ファンドの運用自由度縮小を警戒した顧客が解約を急いだことで、換金売りを迫られている可能性も指摘される。
アクセスランキング(過去1週間)
いずれにしても、年金運用のあり方が問われていることは間違いない。事態の収拾に躍起になるあまり、国が過度に強力な規制を導入すれば、まともな投資顧問業者までもを窮地に陥れることになりかねない。それよりはむしろ、ちまたにあふれる金融機関出身の求職者を、年金基金の「ゲートキーパー」として徴用するよう促してみてはどうだろうか。
(鈴木 草太)


















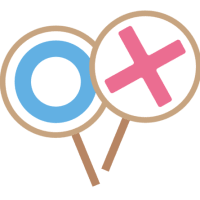






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます