 新型コロナウイルスをめぐり、日本国内で感染経路が「不明」の感染者が相次いで見つかり、日常生活の中で広がる「市中感染」が現実味を帯びている。
新型コロナウイルスをめぐり、日本国内で感染経路が「不明」の感染者が相次いで見つかり、日常生活の中で広がる「市中感染」が現実味を帯びている。
専門家は「新しい局面に入った」と警戒感を強め、重症者の早期発見と適切な治療の必要性を呼びかける。いまだに3千人超の乗客乗員を抱え、感染者が後を絶たないクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応も続く中、国内の検査・医療態勢は十分といえるのか。
国内初の死亡例を含む13日に公表された4人は、湖北省・浙江省への渡航歴を含めた中国との明確な接点がなかった。肺炎患者との接触も見受けられず、人から人への感染が連鎖的に起きた末の市中感染が強く疑われるケースといえる。
神奈川県の80代女性の感染が確認されたのは13日の死亡後だった。ただ、1月22日から倦怠(けんたい)感などの初期症状を見せており、湖北省武漢市の空港が閉鎖される前の同月中旬ごろには感染していた可能性がある。
日本感染症学会の舘田一博理事長は「当時武漢市から来た人が無症状のままウイルスを持ち込んでいてもおかしくない。そこから感染した人がいても、初期なら風邪のような症状だから分からない」と感染拡大の経緯を推測。その上で「国内でも発見された症例以上に、水面下で感染が広がっている」と指摘する。
国内の感染者はチャーター機やクルーズ船関連を除き、11都道府県にまたがる。ただ、大半が感染経路をたどれ、厚労省は「流行が認められている状況ではない」と一貫して説明。同日の加藤勝信厚労相も「流行している状況ではないとの見解を変更する根拠はない」との姿勢を崩さなかった。一方で、感染拡大の流れを否定せず、検査・医療態勢の強化方針を示している。
クルーズ船の検査に追われる中、民間会社や大学などの協力も得て、1日の処理能力を約1100件に増強。最短15分でウイルスの有無を判定できる検出機器も3月末までに導入する。
医療面では同船の感染者の入院先が当初の神奈川、東京では収まらず、北関東や長野、山梨にも依頼。今後も感染が爆発的に広がった場合、患者を受け入れきれるのかの懸念が募る。(WEB抜粋引用)
<iframe id="google_ads_iframe_/6974/izanews/Inread_0" style="border: 0px currentColor; vertical-align: bottom;" title="3rd party ad content" name="google_ads_iframe_/6974/izanews/Inread_0" width="1" height="1" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" data-load-complete="true" data-google-container-id="8"></iframe>Drが他人事事のように言っているが治療薬がないのにどうして適切な治療が出来るというのだろうか、次から次えと何処からともなく湧いてくる。日本はこれからどうなるか心配だ。
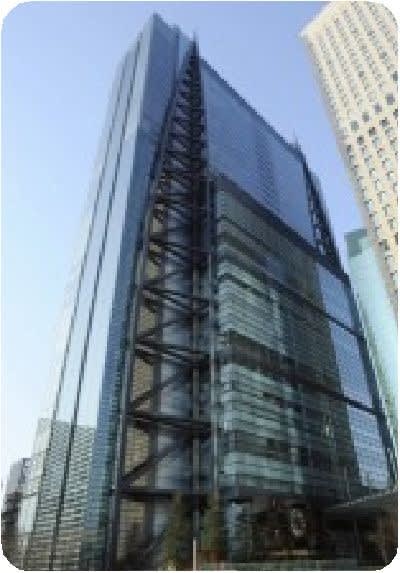










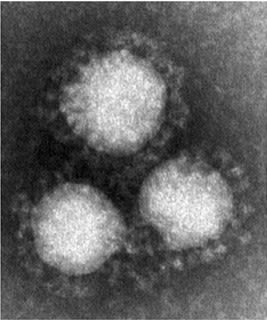



 新型コロナウイルスをめぐり、日本国内で感染経路が「不明」の感染者が相次いで見つかり、日常生活の中で広がる「市中感染」が現実味を帯びている。
新型コロナウイルスをめぐり、日本国内で感染経路が「不明」の感染者が相次いで見つかり、日常生活の中で広がる「市中感染」が現実味を帯びている。


 ウィリスに五輪が飲み込まれければと・・・余計な心配するなと言われるか?
ウィリスに五輪が飲み込まれければと・・・余計な心配するなと言われるか?