毎年、必ず行っている、めちゃめちゃ楽しみにしている旭区民祭り。
何が楽しみって、タージンのジャンボクイズの名司会


ところが、夕方から雷雨 でどしゃぶりに・・・
でどしゃぶりに・・・
でもまあ少しずつ小雨になってきたし、いちおう行ってみようとバスで向かうことに。
わ~グラウンドはとても使えた状態じゃなく、もちろん中止


区民センター前でバスを降りたとき、センターからたくさんの人が手に手に何か持って出てきたので、
もしかしてタージンのジャンボクイズはセンター内でやったのでは!?
・・・・と、思ったらやっぱりそうだったようだ
センター大ホールで「タージンのトーク&クイズ(ビンゴゲーム)」や、その他のプログラムが。
残念や~つくづく残念やわ~
雨天の場合は区民センターで・・・って書いてあったのを見逃してたし
(ま、どっちゃにしても主人が仕事から帰って来て、家を出た時点で終わってたけどね。)
旭区民祭りを見ないと、いや、タージンの司会を見ないと私の夏は終わらないのにぃ~
来年は晴れてや


Mameshiba  今年の盆踊りの音頭とりは河内音頭・鉄砲菊春さんでした。
今年の盆踊りの音頭とりは河内音頭・鉄砲菊春さんでした。
(7月のお話(^^ゞ)
どんだけ夏祭りに行くねん!という感じだけど、好きなもんで(^^ゞ
夏祭りが好きというより、大阪の夏の風物詩が好きなんかな~ 暑くて街歩きも休憩してるしね
暑くて街歩きも休憩してるしね
参道、境内は子供たちでいっぱい (暗いけど)
(暗いけど)
こどものだんじりがあるからみたいだ。

たくさんの子供たちが、綿菓子を買って食べたり、りんごあめを食べたり。楽しそう~

かつてこの一体は幾度も淀川の洪水に見舞われ、後白河法皇がこの地に行幸されたおりに、
その惨状を哀れみ、当地の守護神として神社を建てるように命じられました。
そこで、毛馬、滓上江、友渕など8か村の人々が協力して、永暦元年に建てたのがこの神社です。
旧本殿その他は戦災で消失しましたが、昭和24年に再建されました。(↓より抜粋)
あちこちいたるところに「きけん のぼるな」の張り紙が 以前誰かのぼってケガでもしたのかな。
以前誰かのぼってケガでもしたのかな。
子供のころ、地元のお祭りが楽しみだった。花火大会もあるし。
お菓子がいっぱいもらえる地蔵盆、大神宮さんも、わくわくしてた。
なんか今でもその気持ちは変わってないかも?お菓子はもらえないけどー
都島神社 大阪市都島区都島本通1-5
地下鉄谷町線「都島」駅下車 北西へ100m
Mameshiba 
(7月のお話(^^ゞ)
玉造稲荷神社~難波宮跡の次は露天神社の夏祭りを見に行った。ちょっと疲れてきたぞ
露天神社(つゆのてんじんじゃ)(通称 お初天神)
元禄16年(1703年)に当神社の境内で実際にあった心中事件を題材に、
近松門左衛門が人形浄瑠璃「曽根崎心中」を書きました。
以後、そのヒロインの名前「お初」にちなんで「お初天神」と呼ばれるようになったのです。(HPより)
「誰が告ぐるとは曽根崎の森の下風音に聞え。
取伝へ貴賎群集の回向の種。未来成仏疑ひなき恋の。手本となりにけり。」
お初、徳兵衛


むむっ!こんなのこれまでなかったで!
水掛難転石
「難を転じて災いを避ける」という意味らしくて、水の力でクルクル回っていた。
私もクルクルしておいた

左:開運稲荷社 玉津稲荷 右:おみくじをくくりつけるためのもの

牛神舎
「神牛さん」「撫で牛さん」と呼ばれ、身体の病む処と神牛さんのそれを交互に撫で摩るという信仰が、
古来より続いている。神牛さんに身代わりになっていただく、
または神牛さんが霊力を持って病を治癒していただこうというものである。(HPより)
浪速七名井「神泉 露の井戸」
真水の少ない大阪で、周辺地域のもならず社地横を通る旧池田街道を行き通う人々にとっても
貴重な井戸であった。梅雨時期には清水を地上に湧き出したと伝えられ、
当社社名の起こりともいわれる。境内に現存するが、水量は少ない。(HPより)
本殿
境内がこんなに広いなんて驚き!
この神社に寄るときは居酒屋帰りが多いので、暗くて全体が把握できてなかったのねー。
猿田彦大神
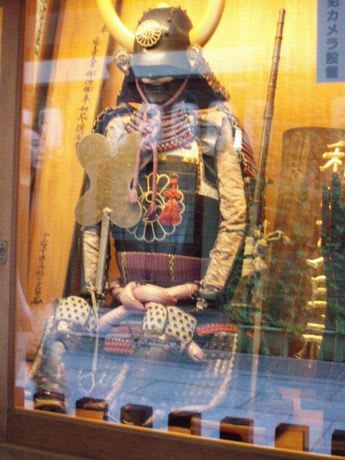
一歩外に出ると高層ビル街。
曽根崎お初天神通り
終戦直後からお初天神の境内に飲食店が集まり始め、30店舗ほどのお初天神食堂街として栄えました。
当時あったお店、例えばしゅうまいの阿み彦や小料理の扇屋は現在でも近くに場所を移して昔の味を守りながら営業中です。

こちらに出ると、狭い路地に新旧の居酒屋さん、スナックなどがたくさん。

大阪のこういう場所、大好~き
露天神社 大阪市北区曽根崎2-5-4
地下鉄谷町線「東梅田」駅 地下鉄御堂筋線・阪急・阪神「梅田」駅
地下鉄四ツ橋線「西梅田」駅 JR「大阪」駅 JR「北新地」駅
より徒歩5分~10分
Mameshiba 
(7月のお話(^^ゞ)
玉造稲荷神社に行ったあと、周辺をぶらぶら歩いてみた。
なにやら、いろいろありそうだ

「歴史の散歩道」(森ノ宮勝山線) があるぞ!

難波宮跡東辺
「難波宮跡はここから400m西方にある大極殿を中心とした1km4方に広がる宮殿遺跡であり
昭和29年(1954年)以来の山根徳太郎文学博士を中心とする発掘調査により発見された・・・・」

越中井
「この付近は細川越中守忠興(ただおき)の邸跡で、越中井はその邸内にあったものといわれている。
慶長5年(1600)関ケ原戦の直前、忠興が家康に従い上杉攻めに出陣中、
石田三成は在坂諸大名の妻子を人質にしようとしたが、忠興夫人玉子(洗礼名ガラシャ)はこれに従わず、
家臣に胸を突かせて37歳の生涯を閉じた。近くのカトリック教会には、
ガラシャ夫人像とキリシタン大名の高山右近(たかやまうこん)像がある。」(大阪市HPより)
「散りぬべき 時知りてこそ 世の中の 花も花なれ 人も人なれ」
史跡 越中井由来
「ガラシャ夫人の名だけ聞いてもどんな人なのか知らない人が多いのではないでしょうか。
ガラシャは細川越中守忠興公の夫人で熱心なキリシタン信者でありました。
慶長5年(1600年)忠興公が徳川家康に従って会津上杉を征伐ん出陣した留守中。
反家康の石田三成が大名妻子たちを大阪城中に人質にしようとしたが、ガラシャ夫人は聞き入れず
石田三成に取囲まれ、ぜひもなく家来に首を討たせ家屋敷に火を放ちいさぎよく火中に果てました。
この越中井はその屋敷の台所にあったと古くから伝えられています。
昭和9年(1934年)当時地元の越中町内会の人々相寄り、ガラシャ夫人の徳をしのび顕彰碑を建立したものです。
碑の正面表題の文字は徳富蘇峯先生の筆で、側面(左側)の由来説明は京都帝大文学部長新村出先生の文です。
改めてそれを読みながらガラシャ夫人の壮烈な最後を想い起こしてください。」

法円坂の団地が立ち並ぶ間から大阪城が見える。
西のほうに歩いていくと 史跡 難波宮跡(なにわのみやあと) に着いた。
法円坂の地に広がる遺跡を公園として整備した場所で、
「大化の改新」後に造営が始められた「難波長柄豊碕宮」跡、聖武天皇が神亀3年(726年)から
造営を行った「難波宮」跡と考えられている。敷地内には難波宮の大極殿の基壇を復元した石造りの壇がある。




回廊跡の復元。 この横に八角殿があったが写し忘れ(^^ゞ
というか、おっさんがお腹を出して下のベンチで寝てたので撮りたくなかった
あんなとこで寝てたら、いやというほど蚊に刺されたんとちゃうかな~

この周辺には「大阪あそ歩」でまた訪れると思う
越中井 中央区森の宮中央二丁目12 越中公園そば
地下鉄中央線・JR大阪環状線「森の宮」下車 南西約500m
難波宮跡 中央区法円坂1丁目
JR大阪環状線「森ノ宮」駅下車 地下鉄谷町線「谷町4丁目」駅下車
Mameshiba ![]()
![]()
豊臣秀頼公奉納鳥居
慶長8年に秀頼公より奉納され、400年の歴史を刻む。
大阪の石製鳥居としては、四天王寺正門の鳥居と共に古いといわれている。(神社HPより)
下半分がない。倒れたのかな。

千利休居士顕彰碑
豊臣時代、玉造禰宜町の地で千利休が屋敷を構えていたと言われ、恒例の秋のだんご茶会も、
秀吉や淀君、秀頼公らが野点の利休の茶会を楽しんだという故事にちなんだものである。(神社HPより)
難波・玉造資料館  難波・玉造について
難波・玉造について

夜店などの業者の車が境内のあちこちに停められていて、全体の写真が撮れなかった。
神社の・・・側
大阪城の玉造門(現・大阪市中央区玉造1丁目)が黒塗りの門であったことから、
この門を別名黒門と呼び、江戸時代にこの黒門付近で作られ名産となった瓜の事を
「玉造黒門越瓜(たまつくりくろもんしろうり)」という。一般に、くろもんと呼ばれ、実は最も長大、
濃緑色で八~九条の白色の縦縞があり、糠漬けにしておいしかった事から浪速名産の一つとされた。(神社HPより)

玉造くろもんちゃん
神社の・・・側。
大坂三十三所巡り・第十番札所碑
元禄時代、玉造稲荷神社に観音堂があり大坂三十三所観音の第十番札所であった。
それは近松門左衛門の「曽根崎心中」や「卯月の紅葉」など、浄瑠璃の中に多くの参拝者でにぎわっていた
当時の情景が描かれている事でも知られている。(神社HPより)
小野小町歌碑
昔、上町台地の東側は海水の侵入する港湾地帯であった。生駒金剛連山を見渡す景勝の地であり、
平安時代に至っては大和川が流れ、その玉造江を小町が通った際に詠んだ歌である。(神社HPより)
玉造稲荷神社には初めて行ったが、いろいろな由緒があっておもしろかった。
玉造稲荷神社 大阪市中央区玉造2丁目3番8号
JR大阪環状線「玉造」駅または「森ノ宮」駅下車 徒歩8分
地下鉄中央線「玉造」「森ノ宮」駅下車 徒歩6分
Mameshiba ![]()
(7月のお話(^^ゞ)
中央区玉造にある玉造稲荷神社の夏祭りを見てきた。
まだ時間が早くて人がほとんどいない。夜になると賑やかなんだろうな。
「江戸時代に全国的に大流行したお伊勢参り。『一生に一度は伊勢参り』
『伊勢に七度、熊野に三度、お多賀様には月参り』といわれたように江戸時代の人々は
こぞって伊勢参りの旅へ出た。当時西の玄関口として賑わった玉造。」(HPより)
胞衣塚大明神(よなづかだいみょうじん)
豊臣秀頼と淀殿を結ぶ胞衣(えな/よな)を祀る。
大阪築城400年を機に地元、政・財・文化界有志により、ゆかりの当神社に祀られた。
子の悩み、夜泣きに霊験あらたかとされている。(神社HPより)


左:新山稲荷神社(しんやまいなりじんじゃ) 右:万慶稲荷神社(まんけいいなりじんじゃ)
厳島神社(いつくしまじんじゃ)
境内の池は白龍池(はくりゅういけ)と呼ばれ、白龍の
観音を頂き出現されたところで、雨乞いに霊験ありと伝えられている。(神社HPより)
なで子持曲玉石
社殿の前の“子の悩み”「なで子持曲玉石」は子孫繁栄、子授け、芸能向上、事業振興に
霊験あらたかでありますようにと願いなでられる。また、神から見れば「我々もみな産みの子」となる。(神社HPより)
玉造稲荷神社 大阪市中央区玉造2丁目3番8号
JR大阪環状線「玉造」駅または「森ノ宮」駅下車 徒歩8分
地下鉄中央線「玉造」「森ノ宮」駅下車 徒歩6分
Mameshiba ![]()
愛染堂のお隣の「大江神社」がある。
茅の輪神事斎行
「「水無月の夏越えの祓いする人は千歳の命延ぶるといふなり」
と繰り返して唱え、茅の輪を三度くぐって、神前にて拝礼の後、お神酒をお受け下さい」
「境内奥に鎮座する狛虎は江戸時代に祀られていた毘沙門天の守護で、
明治の神仏分離で「吽形」が滋賀に移され、残った「阿形」も大阪大空襲で焼夷弾を受け、
耳がとれ、歯もかけてしまいました。そこで平成15年8月、地元有志が、
「狛虎を一対にしたら優勝するのでは」
と「吽形」の狛虎をつくり、そしてその年、阪神タイガースは18年ぶりに優勝しました。
マスコミにも大きく取り上げられ、今ではタイガースの守り神として、多くのファンがお参りされています。」
左:タイガースファン奉納の「吽形」狛虎、 右:戦火に焼け残った「阿形」の狛虎



西側の階段を降りて駅まで歩いて行こう。
大江神社
〒 543-0075 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町5-40
地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅5番出口から徒歩2~3分
JR天王寺駅から谷町筋を北へ徒歩15分
Mameshiba 
今年も天王寺の愛染堂(勝鬘院)で行われる愛染祭に行って来た。(6/30~7/2)

大坂天満八軒家から4.1km。



愛染娘さんたちが取材を受けてました。後姿だけで失礼!

愛染さんじゃ~、ほえかご~!
べっぴんさんじゃ、ほえかご~!
商売繁盛、ほえかご~!
このかけ声は平成13年より、「21世紀に残したい音風景」に選定されている。
最後は大阪締め
打~ちまひょ 

もひとつせ 

いおうて三度 



まんなかの男性の頭は「愛」の字に刈られていた
その頭をこちらに向けるパフォーマンス?をやってたけど、シャッターチャンスが訪れず

多宝塔
「推古天皇元年(593年)聖徳太子によって創建され、
その後、織田信長の大阪石山寺攻めの際に焼失したが、
慶長2年(1597年)豊臣秀吉により再建された。
大阪市最古の木造建造物として国の重要文化財に指定されている。」
愛染かつら 詳細は 愛染祭り2010
愛染祭り2010

密かなパワースポットとして人気の腰痛封じの石
主人も私も腰痛持ちなので、今年もやっておいた。


大阪に夏がやってきた!
愛染さん(愛染堂=勝鬘院)
〒 543-0075 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町5-36
地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅5番出口から徒歩2~3分
JR天王寺駅から谷町筋を北へ徒歩15分
![]() 愛染さんに関する7つのお話
愛染さんに関する7つのお話
Mameshiba 
三休橋筋にある昭和5年開業の吉田理容所。
このたたずまいに目がとまり、写真を撮る人が多いようだ。

お客さんには著名人も多いそう
白髪のおじいさんがハサミ片手に世間話でもしながら散髪してるのかなあ
主人を引っ張り入れて散髪してもらったら良かった
あ!あのカミソリを研ぐ皮のベルトなんかもありそう。懐かしい。
私、ひげを剃る時に使う白くて良い香りの泡(シェービングフォーム)がおもしろくて、
小さい頃、父や兄が散髪に行くのに一緒についていって、
散髪屋さんのおっちゃんに、あの泡泡を顔につけてもらって喜んでたっけ。
すごく清潔そうな、良い香りがするんだよな~

今回の街歩きで歩いた総歩数は13433歩 8.6km 



こんなに歩くとは思わず、靴底の薄いシューズ を履いて行ったので足が疲れた~
を履いて行ったので足が疲れた~
Mameshiba 

![]()

![]() ポチッとクリックよろしくです
ポチッとクリックよろしくです

大川を後にして、大阪城方面まで歩いて行こう。
京阪本線
大坂橋
大阪市の寝屋川と府道石切大阪線を跨ぎ、大阪城公園と毛馬桜ノ宮公園を結ぶ自転車・歩行者専用橋。
東横堀川の凌渫中に「大坂橋 天正13年」の銘が刻された擬宝珠(ぎぼし)が発見されたことにちなんでいる。
この「大坂橋」が当時どこに架かっていたのかは不明である。

大阪城の北西・京橋口の近くにある赤いレンガの建物は「大阪砲兵工廠*」。
明治初期に建てられた日本軍のアジア最大の40万坪、6万8千人もの従業員を抱える巨大兵器工場。
終戦直前に米軍の爆撃によって多くの建物が破壊され、がれきと不発弾などは放置されて、
危険なため20年間手付かずのままであったが、その後、自衛隊大阪地方連絡所そして使用されたが、
1998年(平成10年)以降は自衛隊が撤退し再び放置されている。
窓はすべて黒いベニヤ板で覆われていて中は見えない。廃墟。


筋鉄門跡(すじがねもんあと)
元和6年(1620年)に開始された徳川幕府による大阪城再築工事で、
筋鉄門はその西の入り口で、門扉は筋状の鉄板で補強されていた。

大阪城が見えるが、今回はパス。
大阪OBP クリスタルタワー
新鴨野橋(しんしぎのばし)
かつてこの地には鴫野橋と呼ばれた橋があった。初めて架けられた時期は明確ではないが、
豊臣氏の大坂城築城の後には、城と鴫野村の間にあったと推定される。徳川時代にはこの付近に京橋口御定番下屋敷や、
その他の幕府の施設がおかれ「公儀橋十二ヶ所」の一つと定められた。また近くには弁財天の祠もあり、
梅の花ざかりの頃は多くの人々で賑わったと言われている。
明治時代になって、この辺りは、大阪砲兵工廠の敷地となり、橋も軍の施設となったが太平洋戦争後に大阪市へ引き継がれ、
この間に新鴫野橋と改称された。廃墟と化した大阪砲兵工廠跡も、大阪城公園と大阪ビジネスパークという
新しい街として生まれ変わった。昭和61年より、大阪府の河川改修事業の一環として、
歴史と環境に調和した新しい橋の工事が始められた。(大阪市HPより)

*廠 = しょう 壁仕切りのない、だだっ広い建物
つづく
Mameshiba 

公園のトイレ。デザインがきれい。
難波橋
イベントが何も行われていないと、こんなに広々としてるんやね

天神橋
『天神橋は文禄3年(1594)に架けられたと伝えられ、当初は橋の名はなく新橋と呼ばれていたが、
天満天神社が管理することからしだいに天神橋と呼ばれるようになったという。
天神橋の架設は上町台地と大坂の北部方面を結ぶという意味で大変重要であり、
後に天満組となる現在の北区の一部の発展を約束するものであった。』
(「大阪橋ものがたり」より)


天満橋
『天満橋・天神橋・難波橋は江戸時代以来、大坂の町にとって最も重要で、最も親しまれてきた橋である。
当時としては最大級の橋で、この三橋は浪華の三大橋と呼ばれた。』
(「大阪橋ものがたり」より)

川崎橋
『江戸時代、大阪城京橋口から、幕府の役人宅や諸藩の蔵屋敷があった対岸の川崎(北区天満一丁目の一部)へは
「川崎渡」が通っていた。明治10年になってこの地に橋が架けられたが、
私設の橋で通行料一人三厘を徴収したことによって 「ぜにとり橋」と呼ばれたらしい。
この橋も明治18年7月初めの大洪水によって下流の橋ともども流失し、以降再建されることはなかった。
現在の川崎橋は、中之島公園と千里の万博記念公園を結ぶ大規模自転車道の一環として
昭和53年に架設された。形式は高い塔から多くのケーブルを出し、桁を吊った斜張橋というタイプで、
技術的にすぐれ、景観を重要視した橋として、土木学会の賞を受けている。』
(「大阪橋ものがたり」より)

桜の花を真上から見る



桜宮公園 
つづく
Mameshiba ![]()
栴檀木橋(せんだんのきばし)
『江戸時代、中之島には諸藩の蔵屋敷が建てられ、船場との連絡のために土佐掘川には多くの橋が架けられていた。
栴檀木橋もそうした橋の一つであった。橋名の由来は『摂津名所図会』では
この橋筋に栴檀ノ木の大木があったためとしているが、詳らかではない。』
(「大阪橋ものがたり」より)


橋から北方向を見る
栴檀木橋を渡ると中ノ島に中央公会堂がある。
中央公会堂の前を通り過ぎて、鉾流橋(ほこながしばし)を渡る。
鉾流橋(ほこながしばし)
『天神祭の際行われる鉾流しの神事にちなむ橋名がつけられているため古い印象を受けるが、
初めてこの地に橋が架けられたのは大正7年のこととされている。大正5年に大阪控訴院が新築されており、
大正7年には中央公会堂が、同10年に大阪市庁舎が完成するなど周辺の整備が進められる中で、
橋の需要が高まっていたものと思われる。』(「大阪橋ものがたり」より)
『天神祭の宵宮に神鉾を川に流す行事「鉾流しの神事」は現在も鉾流橋のたもとで行われている。
現在の橋は、昭和4年完成した。高欄、照明灯、親柱など日本調にクラシックなデザインが採用されたのは
天神祭の船渡御が行われることを考慮したデザインであろう。
その後、戦争中の金属供出などによって、これらの高欄、照明灯は失われたが、
昭和55年に中之島地区にマッチしたクラシックなデザインの高欄や照明灯、レンガ敷きの歩道などが整備された。』
(「大阪橋ものがたり」より)

鉾流橋から東洋陶磁美術館を見る。
遠くに難波橋(なにわばし)が見える。
反対の西側には水晶橋が見える。
川では水上バイクが走って?いた。
難波橋
橋の下をくぐって、中ノ島公園へ。
つづく
Mameshiba ![]()











 友達同士ならかまわないけど、相手は母親かおばあちゃんやで。
友達同士ならかまわないけど、相手は母親かおばあちゃんやで。
 楽しそう
楽しそう























