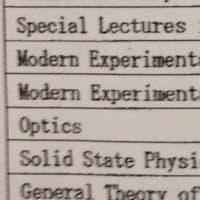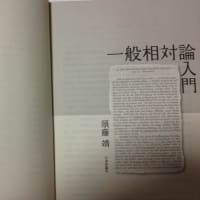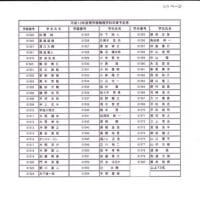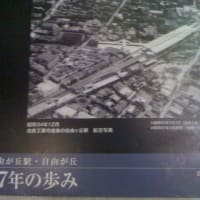いずれかというと、人生短いので、後者しかないだろう。
アメリカと日本の、ベンチャー企業のあり方に反映される、思想の違いは、
金融の自由化以前のあり方と、自由化した金融の違い。
間接金融と、直接金融の違い。
国費で研究費が下りて配分されるのと、自らグラントを申請して研究費と運用費を獲得することの違い。
と言った違いと相似な気がし始めた。
まさか、
天然資源が切り売りできるのと、不足しているのとの違い。
大陸なのと、島国なのと違い。
などのように、
物理的な、いわば、脳の環境変数に作用する力学的ハミルトニアンの違いではないとは思うが、
これも疑わしいと思っている。
その場合は、行動がほぼ無意識に決定しているので、これを意識的に変えるのは、非常に困難極まりない相違に相似なものごととなる。
学習で補うには深すぎる溝である。
その違いとは?
皆さんなら既にお気づきかもしれません。ある程度、私の勘違いなら良いのですが・・・
「投資を優先するのは、既に出来上がっているものや技術をどう売り込むかという段階のもの。言い換えると、マーケットはそのままだと既存のもので、単なる新規参入では既存の競争を宿命として余儀なくされる製品や技術やサービスに、主に投資する。したがって、必然的にいわゆる継続的イノベーション(大企業・既存優良企業の取るべき行動タイプ)のタイプの製品やサービスが多くなる。」
この逆のベクトル。これこそベンチャービジネスのテキストに必須事項として登場する考え方、
「マーケットを仮定し、そこに必要な製品や技術やサービスを定義し、それが完成すると、かなり高い確率でそのビジネスが成長すると言うモデルを売り込み、それに投資することを優先する。」
アメリカのVCはこれをやって、10の企業の仮定が実現できる前に何らかの制約で崩壊しても、1つの企業がそれを実現し、急成長することで元が取れるという構造とともに生きているのですよね。
日本の思想は、前者のタイプより、ですよね。
違うでしょうか。
うーーん気になります。

近年販売されているMOTの教科書を読んでみても、そこで学べそうなものは、既に立ち上がった企業がどう振舞うといいかというモデルばかり。どう仮説を立てて、実行すると、どんな未来があり、そのために準備することは何かなど・・・胡散臭がって書いていないものばかり・・・
他方、洋書の訳本はまだしも、その受け売りっぽいものは胡散臭さが倍増していると言った始末・・・
思想を進歩させるには、
例えば有力な政治家が、専門力の発揮できそうな官僚と協力して、
例えば私有林や国有林を担保に入れてでも(よくわかんない例えですが)、
欧米のVCが投資しやすい環境作りを大胆に実行するような、
そんな社会科学的実験をまずやってみないと、始まらないのでは?
と思ったりします。
こんな考えを著した実務思想家の方って、日本にいないのだろうか?
アメリカと日本の、ベンチャー企業のあり方に反映される、思想の違いは、
金融の自由化以前のあり方と、自由化した金融の違い。
間接金融と、直接金融の違い。
国費で研究費が下りて配分されるのと、自らグラントを申請して研究費と運用費を獲得することの違い。
と言った違いと相似な気がし始めた。
まさか、
天然資源が切り売りできるのと、不足しているのとの違い。
大陸なのと、島国なのと違い。
などのように、
物理的な、いわば、脳の環境変数に作用する力学的ハミルトニアンの違いではないとは思うが、
これも疑わしいと思っている。
その場合は、行動がほぼ無意識に決定しているので、これを意識的に変えるのは、非常に困難極まりない相違に相似なものごととなる。
学習で補うには深すぎる溝である。
その違いとは?
皆さんなら既にお気づきかもしれません。ある程度、私の勘違いなら良いのですが・・・
「投資を優先するのは、既に出来上がっているものや技術をどう売り込むかという段階のもの。言い換えると、マーケットはそのままだと既存のもので、単なる新規参入では既存の競争を宿命として余儀なくされる製品や技術やサービスに、主に投資する。したがって、必然的にいわゆる継続的イノベーション(大企業・既存優良企業の取るべき行動タイプ)のタイプの製品やサービスが多くなる。」
この逆のベクトル。これこそベンチャービジネスのテキストに必須事項として登場する考え方、
「マーケットを仮定し、そこに必要な製品や技術やサービスを定義し、それが完成すると、かなり高い確率でそのビジネスが成長すると言うモデルを売り込み、それに投資することを優先する。」
アメリカのVCはこれをやって、10の企業の仮定が実現できる前に何らかの制約で崩壊しても、1つの企業がそれを実現し、急成長することで元が取れるという構造とともに生きているのですよね。
日本の思想は、前者のタイプより、ですよね。
違うでしょうか。
うーーん気になります。

近年販売されているMOTの教科書を読んでみても、そこで学べそうなものは、既に立ち上がった企業がどう振舞うといいかというモデルばかり。どう仮説を立てて、実行すると、どんな未来があり、そのために準備することは何かなど・・・胡散臭がって書いていないものばかり・・・
他方、洋書の訳本はまだしも、その受け売りっぽいものは胡散臭さが倍増していると言った始末・・・
思想を進歩させるには、
例えば有力な政治家が、専門力の発揮できそうな官僚と協力して、
例えば私有林や国有林を担保に入れてでも(よくわかんない例えですが)、
欧米のVCが投資しやすい環境作りを大胆に実行するような、
そんな社会科学的実験をまずやってみないと、始まらないのでは?
と思ったりします。
こんな考えを著した実務思想家の方って、日本にいないのだろうか?