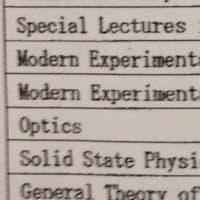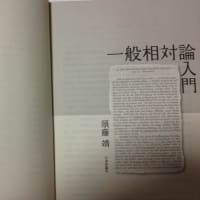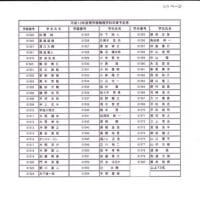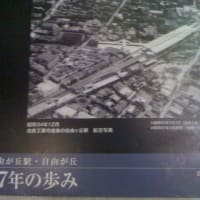おおざっぱにいって、自分にとってどうあって欲しかったか!?
という質問に答える形でいうなら、わりと答えは簡単。
専門家や、プロ、元専門家や、元プロが教師になって、
中学校で少し、高校ではたっぷり、
その面白い内容を指導して欲しかった。
もちろん、現在それができるのは、大学以上だし、
そのための基礎を学ぶために、
専門的な偏りのない手助けをする教師がいれば良い、
ということになっているのは分かる。
勉強一般を面倒見てくれれば、最悪のことにはならないのかも、
知れない。
でもそれでは、私には物足りないし、
私の状況には間に合わなかった、と思っている。
確かに世の中アメリカ資本主義の影響で学歴社会、
それも、日本独特の学歴社会が、かなり幅を利かせている。
つまり、就職口を確保するために、或いは、
優秀な企業の正社員になるために、まれには、
研究者になるために、大学や大学院に進むために、
勉強を始める人がほとんどだ。
そして、その勉強は、
いい意味で中立的な、間主観的、つまり
主観を仲立ちする客観的な対象を相手として
取り組むものである。
それ故その効果により、各主観の間での付き合い方の能力を計る
尺度とも言える学力を身につけるものだ。
しかし、身につけるべき学力を、
そのように付き合い方の能力、
コミュニケーション力、のように再定義するのなら、
言わゆる、「勉強」だけが、
それを身につけさせてくれるものではないのは、
言うまでもないだろうと思う。
勉強の仕方はいろいろである。
人の話から学ぶのが得意なタイプ、
文字情報から学ぶのが得意なタイプと、
大きく分けて二つあると、
経営の父のようなあの、ピーター・ドラッカー氏が
言っていたではないか。
心理学でも、パーソナリティー理論というもの
性格論というものがあり、専門的には、
もっと細かく分類されていたりもする。
それらの、多様性を忘れて、
「勉強」で生徒の能力を計るだけであると、
現在きめられた科目の受験を控えた「勉強」が、
逆に生徒たちの将来を狭くしていることも、
十分考えられないだろうか。
現在形成されつつある教育観は、
いってみれば、
これまでの教育システムで上手く適応できた、
登りつめることのできた成功者の視点である。
そんなマイナーな人の視点で、
多様な社会の多くの成員にとってフェアなもの、
社会全体にとって、より良いものは
できてこないのではないか・・・と、
せめて一日5分だけでも、疑ってみてもいいのではないか。
教師が各々の専門家ならいい、
というわけでもないので、
教育の仕組み自体の方をもっと工夫することで、
より理想的な教育に近づけないだろうか。
教師の質の低下うんぬんよりも。
人間なんて、そういうものだ、
ということを考慮したら、もっと前に進むはずともいえるし。
教育には、上手く、
現実界の多様性への応答を組み込んでおいて欲しい。