
◆世界一の江戸の水道◆
江戸時代を題材にした映画を観ると、地方の農民や侍がスゴク垢で汚れてる。
着物も汚れ、歯も黄ばんでいる。
映画もリアルにメイキングされてるためか、匂ってきそうな風情。
幕府に吸い取られ続ける地方は、生きるので精一杯…
これが江戸時代における地方の様相なんだろうと推測出来るほど。
だが「お江戸」は180度違った。
十七世紀の江戸は水道が張り巡らされていた。
しかも自然流下式で、
長屋ですら共同の水道桝には一定の水位が保たれていた。
「水番屋」というお役人が、
水を汚す者や異物を投げ込まれていないか監視していた。
江戸の水道設備は世界に類のないもの。
パリですら水道が出来たのは19世紀になってからだという。
その潤沢な水道は<湯や>という江戸独特の文化を生んだ。
と、、ここまでは
大昔、受験科目に日本史を選択していたから知ってた。。。。
が、
そこから先の江戸っ子の実態までは教科書には載ってなかった。
驚くような<湯や>の進歩的な活用と面白い実態があるとも思ってなかった。
ウン十年前、NHK「お江戸でござる」で湯やに纏わる話を聴くまでは…
そして江戸風俗評論家/杉浦日向子さんの見てきたような?
嘘みたいで愉快な話にツボってしまった。
♨湯やとフリーパス♨
江戸っ子は湯やが大好き!
アスファルトとコンクリートの生活の現代では考えられないほどの土埃。
着物も身体もすぐにザラザラと真っ白になった。
そのせいか、一日二回もしくは三回と入りに来る。
いわゆる<カラスの行水>というやつ。
町民だけではなく、武家屋敷の武士も湯やに来る。
立派なお屋敷でもお風呂を持つのは大変なお金がかかる。
湯やは大繁盛しあちこちにあったが、問題も多かった。
それは痴漢行為、、、、
バカは世界中にいるが、このバカは気の毒で同情してしまう。
なぜなら男女混浴だからだ。。
男女別風呂にするには、経費がかさみ過ぎるため混浴にせざる得なかった。
ただでさえ江戸は女不足で男やもめばかり、、
なのに湯やへ行けば、若い娘も武家の娘もいるわけで。
年配女性が頑張ってガードしてても、湯船は一緒。。。。
今のように電気がないため暗がりとはいえ、
潜水をし触りにくるという、、一か八かの痴漢行為が絶えなかった。
それでも法で裁かれることもなく、
おかみさん連中に水をぶっかけられ、啖呵を切られる程度で済んだ。
なんとも江戸らしい話だと思わされた。
湯やは士農工商関係なく、長閑なコミニケーションの場でもあり、
そこから<連>と言われる趣味のクラブ活動のような繋がりもあった。
それでも混浴禁止令は度々出るものの、暫くするとまた復活。
明治になるまでデンジャラスな混浴は続いた。
杉浦日向子さん曰く
『江戸の人は こざっぱりとした清潔な風情でした。
毎日湯やに行くので パサパサしてたんですね~
そこから
江戸っ子は垢ぬけてる🎵って言葉が出来たんです』
そして江戸っ子は身なりを綺麗にするのがモットー!
男たちはフンドシ着用のため、お尻の毛を剃るのが当たり前。
<湯や>ではお手入れ道具を借り、お手入れをしていた。
現代女性のTバックの逆バージョンです(苦笑)
石鹸がまだない江戸では、
ほとんどの人が米ぬかを入れた袋で身体を擦っていた。
ただし洗髪は禁止だが、
湯やは今の時代よりも利用頻度が多かったため、
フリーパス148文(2200円)があったほど。
それでも湯やのない地域はあるため、
どうしてたかというと<屋形風呂>があった。
これは杉浦日向子さんが体験されたと本に書かれているが、、
**杉浦日向子「江戸アルキ帖」をお読みクダサイ
びっくり!する不思議な本デスヨ
↓ほら貝を吹いて屋形風呂が来たことを知らせる。
湯やが8文で120円(大人料金)屋形風呂は4文で60円

これが江戸の文化にツボったキカッケになったお話しデス。
次は深いお話しを書きます( *´艸`)

人気ブログランキングへ←ランキングに参加してます。
応援クリックがとても励みになります!( `・∀・´)ノヨロシクお願いします












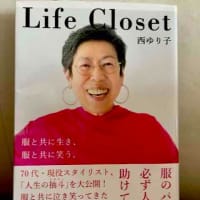


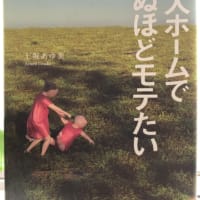



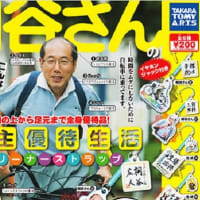






ためになります有難うございます
又々期待して待ってます
たいへん、勉強になりました。
最近、テレビでも、歴史の紐解き風な番組を、見るのが、好きです。
江戸の町は、その様な生活だったのですね。
時代劇には、あまり、風呂屋へ行くシーンは、無いですが、現実は、絶えず入っていた事になります。
今ほど、仕事に追いまくられる事は無いから〜
やはり、お洒落は、大切ですね。(笑)
また、いろいろ、教えてください。
「江戸っ子は垢抜けている」の語源って
湯やから生まれたのですね。
楽しいお話でした。