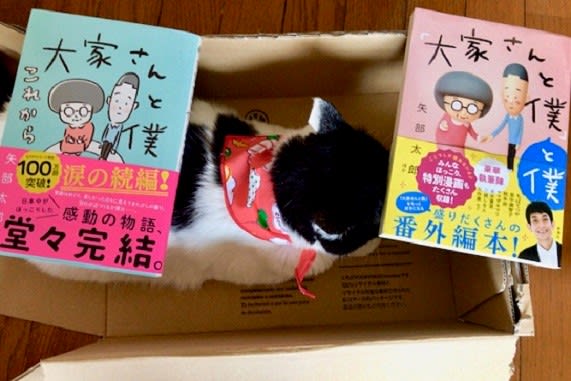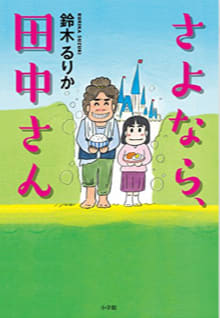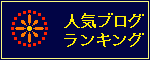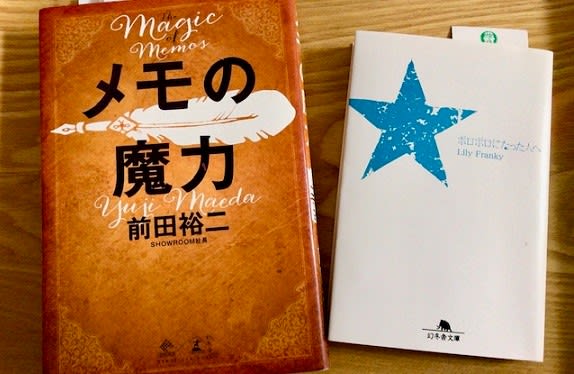前回のブログは、矢部太郎氏「大家さんと僕」の番外編と完結編。
番外編「大家さんと僕」と僕には、
沢山の著名人から寄せられた言葉が詰まっていた。
その中で、グラッとよろめいたのが、15歳の小説家<鈴木るりか>さん。
矢部太郎という人となりを、鮮やかな切り口で言い表していた。
短い文面なのに、一瞬で惹きつられてしまったワタシ。
若干15歳で、プロの小説家。
その若さに反し、言葉を知り尽くしていて、
鈴木るりかという物書きの目線が、えらく老成しているような気がした。
彼女が生まれ育った家の隣は、図書館。
その図書館で、沢山の絵本をめくり、小説を読んで過ごした。
そして
いつの間にか、頭の中で物語りを描くことが日常になった。
この感受性を持つ少女の本が読みたい!!
ワタシの小さな脳みそは、昂る気持ちでプリプリし始めたのだった。
◇14歳の作家デビュー 「さよなら田中さん」◇
読み始めた時から読み終わるまで、退屈する暇のない物語りだった。
近所の激安堂や
夕方のスーパー最終見切り品が、生活の根っこを支えている家庭。
田中さんちは、母子家庭だった。
しかも、お母さんは男たちに交じってキツイ仕事をしている。
だが、
どんな局面にもお母さんは強く、生きるための戒めの哲学を持っている。
その子供が、物語りの主人公<田中さん>なのだ。
小学校の同級生、大家さんと大家さんの引き籠り息子、激安堂の店主が、
田中さんの気持ちをオトナの入り口へと彩っていく。
母と娘はかなり経済的には苦しいが、お母さんは弱音を吐かず、
自分が出来る最大公約数で乗り切ってくる。
それでも、
思春期の娘にとっては、チョット切なかったりもするが、
母の最大公約数はいつもカッコよく、
がんばる母の哲学を、その細い背中を、誇らしく思っている。
そんな風景を少女作家は、
イソップ童話『すっぱいぶどう』の狐とたわわに実る葡萄に例えたり。
もらい物に関して異常な記憶力の母を、
ホイットマンの『寒さに震えたものほど、太陽を暖かく感じる』を引用したり。
彼女の想像力が描く物語りは、
機知に富み、どんな局面もヘコタレナイ、
なのにフワッとした優しい光が寄り添ってくる。
この筆力の豊かさは。。
出掛ける前に、入念にチェックする白髪もない、、
視力の衰えに憂うこともない、、15歳の少女が書いた物語りだった。。
◇二作目「14歳、明日の時間割」◇
一時間目~六時間目、放課後と一つ一つの時間割が物語りに。
懐かしい匂いがした。
セピア色になったはずの中学生のワタシを思い出した。
家庭科や数学は苦痛で、早くオトナになってこの呪縛から逃れたい、、
それは、
社会に出て、この夥しい複雑な数式が、役に立つとは思えなかったからだった。
だが、今になると分かってくる。
小難しい勉強や運動の多くの苦しさは、ある地点に到達するまでの過程を知ること。
それは、到達した瞬間に、風景が変わることを記憶すること。
多分、
これが人の精神的な体力を作っていくと気づく頃には、
社会で生きていく一員となっている。
今思えば、
ヘンな先生、孤立する同級生、立ち回りの巧いヤツ、妙に生真面目な友人、
何処かずれてる面倒な校則やら、、
全部が、生き抜く体力を培うのだと。。
そういう過程を描いたのが『14歳、明日の時間割』だと思う。
その中の五~六時間目の体育の章は、
いくつもの人生がスクランブル交差点のように交差する。
ここに込められた言葉は、とても老成した哲学だった。
そして、
この二作目の小説で知ったのは、
鈴木るりかという作家は、あらかじめ物語の帰結点を設定していない。
登場人物の設定をし、書き始め、
物語りがどう動いて行くのか、書きながら決めていく。
コレをやってる人は、物語りを紡ぐために生まれたような村上春樹氏だ。
全くタイプの違う作家だが、光のある小説を書きたい。。という鈴木るりかさん。
沢山の光を放ってくれる作家になって欲しいと思う。
**今回の表紙**
「14歳、明日の時間割」の表紙は、矢部太郎氏の作品ですよ🎵