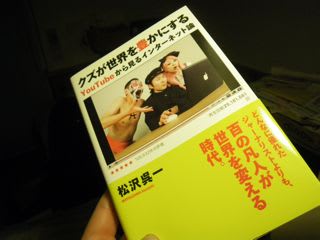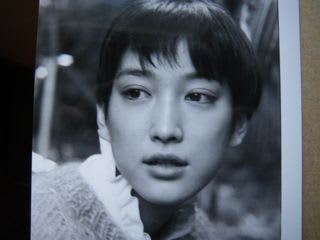エロ表現を考えるにあたって、ひとつ気になったことがあった。「そうだ、俺は松沢呉一さんの著作を読んだことがない」ということ。
それで都内に出たついでに大書店で探してみた。
お、これはいいタイトルじゃないですか『クズが世界を豊かにする』だと。思わずジャケ買いならぬタイトル買いしてしまいました
内容は映像に関するものだけれどYouTubeをネタにしたネット論みたいなもので、あまりエロとは関係してこない。でも、タイトルに感服いたしました。
そうだよ。
大量に生産されるクズな表現があってこそ、その「掃き溜め」のなかから、これまでにないユニークな表現がハイブリット合成されてくる。
だって、日本映画がそうだったでしょ。プログラムピクチャーと呼ばれた、大量のまるで評価されないようなたぐいの映画があってこそ、特異な変種としての『仁義の墓場』や『(秘)色情めす市場』が生まれたんじゃないでしょうか。
と、すれば。
ここ20年ぐらい、いや25年ぐらいかな。大量に生産され、消費されているエロビデオから、なにか新しい表現が生まれてきているはずではないか。自分のアンテナにはキャッチされていないけれど、すでに、そんなふうなユニークな表現は生まれているのではないか。
それで都内に出たついでに大書店で探してみた。
お、これはいいタイトルじゃないですか『クズが世界を豊かにする』だと。思わずジャケ買いならぬタイトル買いしてしまいました
内容は映像に関するものだけれどYouTubeをネタにしたネット論みたいなもので、あまりエロとは関係してこない。でも、タイトルに感服いたしました。
そうだよ。
大量に生産されるクズな表現があってこそ、その「掃き溜め」のなかから、これまでにないユニークな表現がハイブリット合成されてくる。
だって、日本映画がそうだったでしょ。プログラムピクチャーと呼ばれた、大量のまるで評価されないようなたぐいの映画があってこそ、特異な変種としての『仁義の墓場』や『(秘)色情めす市場』が生まれたんじゃないでしょうか。
と、すれば。
ここ20年ぐらい、いや25年ぐらいかな。大量に生産され、消費されているエロビデオから、なにか新しい表現が生まれてきているはずではないか。自分のアンテナにはキャッチされていないけれど、すでに、そんなふうなユニークな表現は生まれているのではないか。