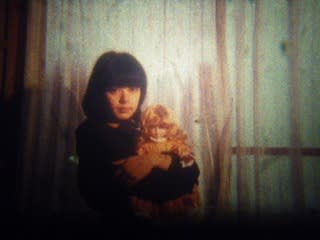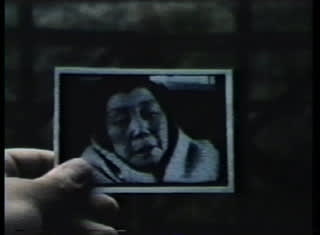上映作品は次の3本。
新川保茂+山崎幹夫『The Musical Box』1980年/25分
内村茂太『猿!ゴリラ!チンパンジー!』1995年/16分
山田勇男『追分』1991年/20分
まずはじめに、今年(2012年)の7月、府中で内村さんの「ほぼ全作」上映が催されたとき「おや、あの作品が入ってないじゃないの」と思ったのが、今回上映する『猿!ゴリラ!チンパンジー!』だ。
内村さんも妻も猫のチャコも出ていない。若いがそこらへんにごろごろいそうな女性3人が、街中でコントっぽい行動をしていくという作品。内村さんはナレーションはなく、ただあのちょっと鼻詰まり気味の声で「だばだばだ♪」とずっとスキャットしているだけ。
でも、おもしろいですよ。タイトル忘れていたけど。
そう言えばこの作品、私のうちで「持ち寄り上映&飲み会」をしたときに内村さんが持ってきて、見せてもらった作品だった。
そこで「上映させてよ」と頼んだところ、
「山崎さんも自分が恥ずかしいと思って上映してない作品をやってくれるなら」と言われたのだった。
いろいろ考えた。
恥ずかしいと思って上映していない作品なら、いくつかある。
そうして「これでいこうか」と思ったのが『The Musical Box』。
北海道大学内の教室を借りて1回だけ上映して、そのあと90年代のラ・カメラ@乃木坂でもどさくさまぎれに1回だけ上映したことがある。
共作者の新川保茂は『猫夜』のセル君がこの頃使っていたペンネーム。添付画像もこの作品。『極星』『猫夜』のカーコさん。
さて、この2作品だけでは足りないので、山田さんにも電話して、留守電にこのプログラムのコンセプトを伝えておいた。
自分の心づもりとしては、前々から山田さんが「恥ずかしい」と言って上映したがらない『夜窓』でどうだろうと考えていたのだけれど、折り返し山田さんから連絡があって、きっぱりと「じゃ『追分』で」と。
なぜ『追分』が「恥ずかしい」のか、電話で確かめようとすると、急にごにょごにょ言い出したので「じゃ、その言い訳は会場で来たお客さんに言ってちょ」ということで切ってしまったので、理由(になるような理由かどうかはわからないけれど)は会場で聞いてみることにしましょう。
これで大西健児プログラムをのぞいた5プロについて、記事にしました。
もう前日です。今夜、機材を搬入してきます。
上映は27日(土)28日(日)、時間とプログラム詳細は過去記事(9月27日アップの記事)を見てください。
料金は当日のみ1000円。
両日とも、上映終わったあとにワンドリンク(酒)と食べ物がついて1000円で交流会(打ち上げ)あります。
neoneo坐の場所はHPを参照くだされ。
新川保茂+山崎幹夫『The Musical Box』1980年/25分
内村茂太『猿!ゴリラ!チンパンジー!』1995年/16分
山田勇男『追分』1991年/20分
まずはじめに、今年(2012年)の7月、府中で内村さんの「ほぼ全作」上映が催されたとき「おや、あの作品が入ってないじゃないの」と思ったのが、今回上映する『猿!ゴリラ!チンパンジー!』だ。
内村さんも妻も猫のチャコも出ていない。若いがそこらへんにごろごろいそうな女性3人が、街中でコントっぽい行動をしていくという作品。内村さんはナレーションはなく、ただあのちょっと鼻詰まり気味の声で「だばだばだ♪」とずっとスキャットしているだけ。
でも、おもしろいですよ。タイトル忘れていたけど。
そう言えばこの作品、私のうちで「持ち寄り上映&飲み会」をしたときに内村さんが持ってきて、見せてもらった作品だった。
そこで「上映させてよ」と頼んだところ、
「山崎さんも自分が恥ずかしいと思って上映してない作品をやってくれるなら」と言われたのだった。
いろいろ考えた。
恥ずかしいと思って上映していない作品なら、いくつかある。
そうして「これでいこうか」と思ったのが『The Musical Box』。
北海道大学内の教室を借りて1回だけ上映して、そのあと90年代のラ・カメラ@乃木坂でもどさくさまぎれに1回だけ上映したことがある。
共作者の新川保茂は『猫夜』のセル君がこの頃使っていたペンネーム。添付画像もこの作品。『極星』『猫夜』のカーコさん。
さて、この2作品だけでは足りないので、山田さんにも電話して、留守電にこのプログラムのコンセプトを伝えておいた。
自分の心づもりとしては、前々から山田さんが「恥ずかしい」と言って上映したがらない『夜窓』でどうだろうと考えていたのだけれど、折り返し山田さんから連絡があって、きっぱりと「じゃ『追分』で」と。
なぜ『追分』が「恥ずかしい」のか、電話で確かめようとすると、急にごにょごにょ言い出したので「じゃ、その言い訳は会場で来たお客さんに言ってちょ」ということで切ってしまったので、理由(になるような理由かどうかはわからないけれど)は会場で聞いてみることにしましょう。
これで大西健児プログラムをのぞいた5プロについて、記事にしました。
もう前日です。今夜、機材を搬入してきます。
上映は27日(土)28日(日)、時間とプログラム詳細は過去記事(9月27日アップの記事)を見てください。
料金は当日のみ1000円。
両日とも、上映終わったあとにワンドリンク(酒)と食べ物がついて1000円で交流会(打ち上げ)あります。
neoneo坐の場所はHPを参照くだされ。